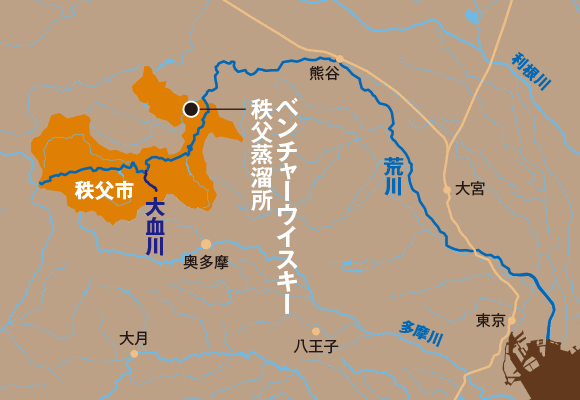機関誌『水の文化』63号

【洋樽】
薫り高きウイスキーを熟成する日本の樽
フランスをはじめとする海外で、日本製のウイスキーが「ジャパニーズウイスキー」として注目されている。ウイスキーの味を左右するのは樽だ。小規模ながらジャパニーズウイスキーとして世界に名をはせるのは、埼玉県秩父市に蒸留所を構えるベンチャーウイスキー。2004年に設立したこの会社が今、自社で洋樽をつくるところまでこぎつけている。

たくさんの樽が並ぶベンチャーウイスキーの貯蔵庫。静かに出荷のときを待っている
ミズナラ樽ならではのオリエンタルな風味
伽羅(きゃら)や白檀(びゃくだん)など高貴なお香を想わせる芳香。まろやかな口あたりのあと、喉越しの奥からほのかな甘みさえ立ちのぼってくる——。
類いまれな味わいの「イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ」は、ジャパニーズオークと呼ばれるミズナラ材の樽で瓶詰め前に熟成されたウイスキーだ。製造販売する株式会社ベンチャーウイスキー秩父蒸溜所の社長、肥土伊知郎(あくといちろう)さんは「さんざんウイスキーを飲んできましたが、初めてミズナラ樽熟成のウイスキーを口にしたときは衝撃を受けました。オリエンタルなフレーバーは独特です。ぜひミズナラ樽を使いたい」と2004年(平成16)の創業時から考えていた。
ウイスキーは大麦麦芽などのでん粉を糖化し、これに酵母を加えて発酵させたのち、蒸留して木の樽で熟成させてつくる。その味を左右するのは熟成・貯蔵で用いる樽だ。「樽熟成が品質に与える影響は全体の6〜7割に及ぶと言われています」と肥土さん。樽にオーク材がよく使われるのは、タンニンなどの成分が溶け出し樽酒ならではの香味が生まれるから。またオークは、根から水分を運ぶ導管が機能を失うと「チローズ」という物質が充填され水止めの役割を果たすので漏れが少なく、樽材に適している。ところが同じナラ類でもミズナラにはチローズが発生せず、その名(水楢)のとおり水分を吸収して漏れやすいから、樽材に加工するのは難しい。
「チローズがあればねじれた材をノコギリでまっすぐに引いて導管を切断しても平気ですが、ミズナラでそれをすると、樽にしたとき内部の液体が導管を伝って漏れ出してくるんです。だから反りやねじれのない通直材を選ばなければなりません。そうすると歩留まりが悪く高価な樽になってしまいます」と肥土さん。
ミズナラ材は北海道で買い付ける。通直材は現地の製材所で加工するが、反りやねじれのある材は秩父まで運び自前で製材している。ミズナラ樽を自作するために樽工場を新設したのが2013年。廃業した樽メーカーの設備を買い取り、そこの社長に樽づくりの指導を受けた。巨大な「薪割り機」スプリッターを導入。これなら繊維に沿って材を割れるので導管を切らず、反りやねじれのある材でも漏れの少ない樽をつくれるという。
地場のミズナラ材も使っている。埼玉県の秩父でも標高900m以上の山にはミズナラの群生林があることがわかった。登山が趣味の肥土さんは自ら2年ほどかけてミズナラが生えていそうなところを8割以上は山歩きして見つけた。2018年に許可を得てミズナラを8本伐採し、地場産のミズナラ樽を10個つくった。「思いのほかよい材でした」と肥土さんは言う。
見捨てられなかった二十歳目前の子どもたち
肥土家は江戸時代からの造り酒屋で、ウイスキーも1980年代にスコットランド式の蒸留設備を導入し、シングルモルト(大麦麦芽のみを原料とし単一の蒸留所で製造)をつくった。肥土さんは大学で醸造学を修め酒造会社に就職したが、経営状態が思わしくないので手伝ってほしいと父親に懇願され1995年(平成7)に家業へ。自社のウイスキーを飲んでみると個性豊かなシングルモルトが出来上がっていた。しかし、当時は水割りにして飲みやすいウイスキーが好まれており、社員自身が「ウチのは飲みづらい」とこぼしていた。
今でこそジャパニーズウイスキーは世界の5大ウイスキーの一つとして知られるが、ウイスキーの国内市場は1985年(昭和60)をピークに2007年まで右肩下がり。しかし、バーに行けば老若男女が目をキラキラさせショットグラスで飲み比べている。「愛好家に飲まれるものをつくれば可能性はある」と肥土さんは考えた。
だが家業の経営状態は悪化し、民事再生法を申し立て、2004年には人手に渡る。新オーナーはウイスキーに興味がなかった。
「約400樽、引き取り手がなければ廃棄ということになりましたが、なかには20年近く熟成していたものもあります。二十歳目前の子どもたちを見捨てるわけにはいきません。幸い、福島県郡山市の酒造メーカーさんが『そんな貴重なものを廃棄するのは業界の損失だ』と預かってくださったのです」と肥土さんは振り返る。
その原酒をもとにベンチャーウイスキーを創立、「Ichiro's Malt」(イチローズモルト)のブランド名で売り出した。2年かけて全国のバーを延べ2000軒近く回り、バーテンダーを通じて評価を得て、口コミでファンを増やしていった。
「3年以上熟成させるウイスキーは今つくったものを未来の財産として残す商売です。売る以上はつくらなければいけない。蒸留所を立ち上げるのは必然」と肥土さんはウイスキー製造の認可を取得。故郷の秩父で土地を探し、仕込み水として荒川水系・大血川(おおちがわ)源流の良質な軟水を得られる場所に秩父蒸留所を設立、2008年2月に稼働した。折しもハイボールのブームでウイスキー市場は回復基調へ。イチローズモルトは全国の愛好家に支持を広げ、「ワールドウイスキーアワード」などの受賞も重ね、十余年足らずで世界に名を馳せるブランドになった。
100%ミズナラ樽で熟成させたウイスキーを
2019年7月から操業している秩父の第二蒸留所。樽工場ではミズナラ樽の自作、修理、そしてバーボン(トウモロコシを主原料とするアメリカ産の蒸留酒)の空き樽(約200L)を組み直して胴径を大きくした樽「ホグスヘッド」(約250L)の製作などを行なう。
「バーボンには『新樽しか使えない』という定義があり、1回使用したら廃棄するので、それを引き取ってバラして組み直すのです。1回使っているので木のえぐみが消えて熟成に向いているのです」と説明するのは四人いるクーパー(樽職人)の一人である永江健太さん。鹿児島にある焼酎メーカーの樽工房で10年ほどメンテナンスを担当していたが、新樽をつくる工場が建つと聞き、「樽職人として成長するため」に2015年に秩父へ。その後、定年を迎えた前の職場の上司に声をかけ、今また一緒に働いている。
「一から樽づくりをするのでやりがいがありますね。『こういう樽がほしい』となったときに自分たちでつくることができるのは、大きな強みだと思います」
樽の真ん中が膨らんでいるのは、転がしやすくするため、そして熟成で横向きに積んだときにも強度を保つためだが、樽は貯蔵庫で乾燥と収縮を繰り返すため、徐々にたがが緩んでくる。「たがの締め直しは勘です。締めがゆるければ漏れるし、やりすぎると割れてしまいます」と笑う永江さんに、なぜ樽の内側を焼くのかと尋ねた。
「焼かなくても樽としては機能するのですが、焼くことで樽の内部の木の成分が変わるんですね。焼き具合が甘いと生木の香りが強くなります。また、焼くと炭化して表面積が増えますので、木のより内側に液体がしみ込むという意味合いもあります」
さらに永江さんは「ミズナラの原木って、まだ水分を含んでいる丸太のときに、メロンのような甘い匂いがするんですよ」と教えてくれた。「イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ」のほんのり立ちのぼる甘い香りは、やはりミズナラ樽のたまものなのだろう。「ミズナラのことをもっと知らないといけないし、組み上げてから漏れチェックをし、材を取り替えなくても、絶対に漏れないミズナラ樽を一発でつくりたい」と永江さんは思い入れを語った。
肥土さんは「今は熟成の後期にミズナラ樽に移し替え、最終的にミズナラのマリッジ(ブレンド)タンクでなじませるという工程を経ていますが、将来は100%ミズナラ樽で熟成した商品を出したい。毎年どんどんミズナラ樽を投入していきます」と意気込む。
日本のウイスキーだからこそ国産のミズナラ樽で完全熟成を目指し、世界に類のないフレーバーを極めたい。イチローズモルトの挑戦にはそんな矜持がみてとれる。
(2019年9月12日取材)