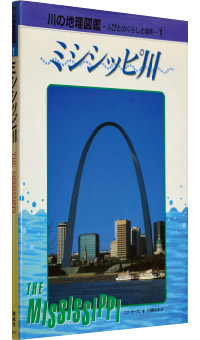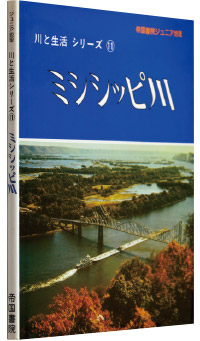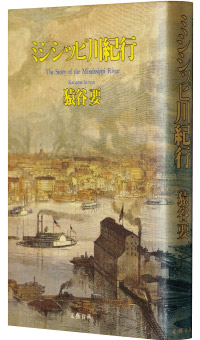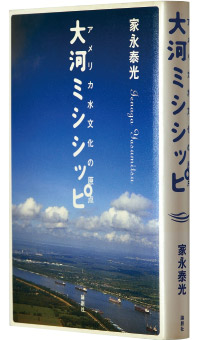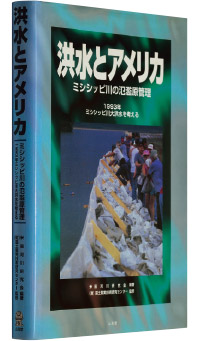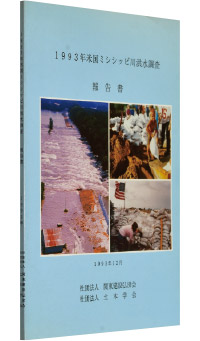機関誌『水の文化』63号
水の文化書誌53
アメリカを創りだしたミシシッピ川の偉大さ
-

-
古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
古賀 邦雄(こが くにお) - 1967年西南学院大学卒業。水資源開発公団(現・独立行政法人水資源機構)に入社。30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。2001年退職し現在、日本河川協会、ふくおかの川と水の会に所属。2008年5月に収集した書籍を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
平成26年公益社団法人日本河川協会の河川功労者表彰を受賞。
1.ミシシッピ川の流れ
アメリカではミシシッピ川は重要な河川の一つである。『全世界の河川事典』(丸善出版・2013年)によれば、ミシシッピ川は、ミネソタ州北部のイタスカ湖に端を発し、米国をほぼ南北に縦断し、ルイジアナ州ニューオーリンズ市付近メキシコ湾に注ぐ。長さ3780km、水系全体の流域面積325万km2。上流部にあたるミズーリ川(長さ4130km)、イエローストーン川(長さ1080km)と合わせるとなっている。そして水系を構成する主な河川は、ミズーリ川のほか、ミネソタ川、ウィンスコンシン川、イリノイ川、オハイオ川、アーカンザス川などである。「源から河川にかけて左岸にウィスコンシン州、イリノイ州、ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州、右岸にミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、アーカンソー州、ルイジアナ州とほぼ一貫して州境を形成しながら南下する。オハイオ州との合流地点のカイロ(ケイロ)市を境に上下流を区別する」と記している。
ニナ・モーガン著『ミシシッピ川』(偕成社・1995年)により、ミシシッピ川の上流から河口まで追ってみる。上流は渓谷になっており、ミネソタ州やアイオワ州に合流すると、水かさが増え、川幅が大きく広がる。流域面積は米国の国土の約40%を占め、米国の31州とカナダの2州が含まれる。海抜450mのイタスカ湖から北東に流れ、やがて南へ曲がり、ミネソタ州のセントポールの近くで、高さ22mもあるセントアンソニー滝を落下する。
セントポールを過ぎると次第に川幅が広くなり、石灰岩の崖の間を流れ、川のなかに500ほどの小島がある川はなだらかな丘の続く大草原と湿地帯に入る。このあたりがコーンベルト(トウモロコシ地帯)と呼ばれる穀倉地帯である。やがて、泥の川であるミズーリ川と合流する。セントルイスのあたりで川は広くゆったりと流れる。セントルイスの近くで育ったマーク・トウェイン(1835―1910)は、毎日のようにミシシッピ川の豊かな流れや蒸気船を観ながら、『トム・ソーヤの冒険』『ハックルベリー・フィンの冒険』を描き出す。
セントルイスから下ると、南部に入りケイロの町を過ぎると洪水を防ぐための堤防が高さ20mを超えるところもある。綿花の町メンフィスは、南北戦争(1861年~1865年)でイギリスからの綿花などの物資が輸入できなくなり、米国で綿花栽培が始まったところである。たくさんの奴隷によって栽培がされた。さらに曲がりくねった川を下り、アーカンソー・シティへ、そして、ビックスバーグの町では、川の水をコントロールするために、ミシシッピ川流域全体の縮尺模型があり、すべてのダム、水路、堤防が示されており、山や小川の位置や土地の高低差がわかる。これはミシシッピ川の治水計画を立てるためにつくられたものである。
河口デルタのニューオーリンズの町は、小さな通りや鉄製のバルコニーの付いた古風な家やカフェや土産物店が並ぶ。ジャズ音楽が生まれた町で、ルイ・アームストロングなどの有名な音楽家を輩出している。ニューオーリンズ港は3番目に大きな港で、ミシシッピ川なしでは町の偉大な発展はなかったと言える。同様にわかりやすいジュニア向けのスーザン・ドレルブラウン著『ミシシッピ川』(帝国書院・1987年)がある。
2.ミシシッピ川の歴史散策
猿谷要著『ミシシッピ川紀行』(文藝春秋・1994年)は、ミシシッピ川の河口から州ごとに遡る旅である。その州の歴史・文化・社会事情を浮き彫りにする。
ナポレオンはルイジアナの土地に植民地帝国を創ることを試みたが、計画は成功せずにアメリカへ1500万ドルで売り渡した。1803年ルイジアナはアメリカ領になった。ニューオーリンズの誕生である。この地は、先住民、フランス人、スペイン人、アメリカ人、という具合に所有権が変わってきた。そこへアフリカやカリブ海周辺から奴隷が連れてこられた。この町は混血の文化の特色をもっているという。
さらに遡り、南北戦争の古戦場、日系人強制収容所跡、クリントン大統領の故郷、キング牧師の暗殺地メンフィス、ブルースの父ウィリアム・C・ハンディの銅像、エルヴィス・プレスリーの邸宅がメンフィスの観光地となっている。さらに、リンカーン生誕地、暴れ川テネシー川を減災する40基のダム群、トムとハックとジムの世界、イリノイの風土大草原、ミネアポリスとセントポールの双子の都市、源流の旅を続け、再度河口まで戻っている。
3.ミシシッピ川七つの道
ジェームス・M・バーダマン著『ミシシッピ=アメリカを生んだ大河』(講談社・2005年)では、ミシシッピ川を七つの道として捉え、その意義と効用と重要性を論ずる。
- 探索の道……ミシシッピ川の発見、メキシコ湾に到達したラ・サール卿
- 輸送の道……蒸気動力の導入以前、回転パドルを取りつけるシュリーブの改良、1865年4月のサルタナ号の爆発事故の最悪の惨事と蒸気船レース、甦った水上交通
- 人が変えた道……防壁と閘門、ダムを通過する船団
- 移住と入植と政治の道……千載一遇の好機、ニューオーリンズとその周辺を買い取る、黒人たちの逃亡ルート、黒人が北部への逃亡にミシシッピ川が役立った
- 自然の道……鳥類の「ミシシッピ飛行経路」、ビーバーの毛皮商品、ミシシッピ流域で良品なボタンとなる貝殻イシガイが発見され、ボタン工場が経済の発展を促した。また、「ミシシッピにいる」という報酬、すなわち川から得られる天然源水と魚がとれた。氷は食糧を保存するために使用された。魚を木箱に入れ、氷を入れて保存。レジャーとして釣り人たちの聖地となる
- 文化の道……ルイ・アームストロングの船上演奏、デルタで過酷な環境から生まれたブルース、ショーボートミシシッピ川の黄金時代、フォスターの『おおスザンナ』はゴールドラッシュでカリフォルニアへ殺到した人びとの愛唱歌である
- 国家の精神的な中心としての道……ミシシッピ川は「偉大なる褐色の神」であるという。経済的な屋台骨と同時に「アメリカ人の精神的な中心」となっている
七つの道について、ミシシッピ川はアメリカという林檎を貫く「芯」であることがよく理解できる。
4.ミシシッピ川流域の自然と文化
家永泰光著『大河ミシシッピ』(論創社・2004年)によると、ミシシッピ川の流れをアメリカの水文化として位置づけて、次の内容の構成となっている。
- ミシシッピ川流域の自然と文化
上流域―イタスカ湖からケイロまで、ケイロから河口まで、アメリカ先住民族の農耕文化を述べる。 - アメリカの水制度とミシシッピ川
沿岸権・専用権によるアメリカ水法の特徴、ミシシッピ川の大洪水と治水を挙げる。 - ミシシッピ川流域の産業の発展
ミシシッピ川流域の稲作展開とプランテーション、米産業と農民を論じる。 - ミシシッピ川の水質汚濁と再生の思想
水質汚濁と環境破壊、ミシシッピ川の水質汚濁を論じる。
5.ミシシッピ川の洪水
米国河川研究会編著『洪水とアメリカ―ミシシッピ川の氾濫原管理―』(山海堂・1994年)によると、1993年6月~8月にかけてミシシッピ川の上流域を記録的な大洪水が襲った。洪水の被害は死者50名ほど、氾濫面積は4万1000km2に及びアイオワ州をはじめとする9つの州にまたがった。農業堤防の越流、破堤により浸水した農地、標準の出水防禦施設が設置されていなかった都市部を襲った。農地が砂に覆われた。資産被害は150億ドルに及んだ。この水害を契機として、ミシシッピ川上流域に体系的な河川整備がなされていなかったから、ミシシッピ川上流域に対しても下流域同様の統一的な治水対策が必要であるとの議論や、合わせて流域全体の観点から環境保全対策を推進することとなった。関東建設弘済会・土木学会編・発行『1993年米国ミシシッピ川大洪水調査報告書』(1993年)、水資源協会編・発行『講演録:米国における治水対策及び水資源開発の現状』(1997年)が刊行されている。
6.おわりに――スーパー台風
2005年8月末、ミシシッピ州、ルイジアナ州を襲ったハリケーン・カトリーナは大きな爪痕を残した。死者1836人、一時120万人が避難せざるを得なかった。トム・ウッテン著『災害とレジリエンスーニューオリンズの人々はハリケーン・カトリーナの衝撃をどう乗り越えたのか―』(明石書店・2014年)によると、被害者は過酷な状況のもとで決して屈せず、コミュニティの再生を図るために活動を続けた。また、国際交流基金日米センター編・発行『報告書:ハリケーン・カトリーナ災害復興協力のための日米対話プロジェクト』(2007年)、日本生態系保護協会訳・発行『21世紀に向けたアメリカの河川環境管理』(1995年)の書は、われわれに減災のための示唆を与えてくれる。
以上、ミシシッピ川の歴史、文化、経済、そして洪水について述べてきたが、ミシシッピ川はアメリカを育て、創りだした偉大な川である。その反面、水害を起こしてきた川でもある。今年(2019年)はスーパー台風がいくつも日本を襲った。気候危機の時代に入り、わが国はハリケーン・カトリーナなどの水害から多くの防災対策を学ぶことが重要である。