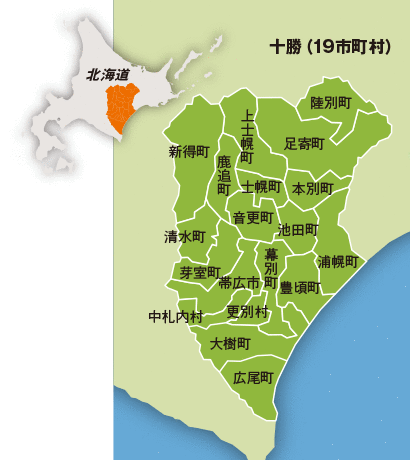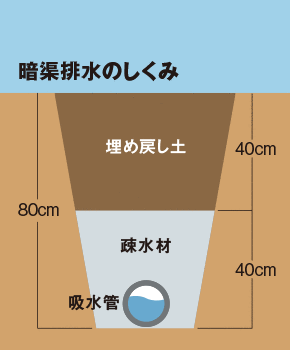機関誌『水の文化』63号
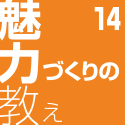
十勝を食糧王国に変えた開拓群像
――北海道 十勝
人口減少期の地域政策を研究する中庭光彦さんが「地域の魅力」を支える資源やしくみを解き明かす連載です。

民間開拓の歴史をもつ十勝。いまや日本有数の食糧供給地となった
-
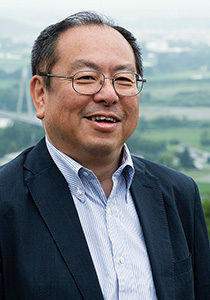
-
多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
中庭 光彦(なかにわ みつひこ) -
1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。専門は地域政策・観光まちづくり。郊外・地方の開発政策史研究を続ける一方、1998年からミツカン水の文化センターの活動に携わり、2014年からアドバイザー。『コミュニティ3.0 地域バージョンアップの論理』(水曜社 2017)など著書多数。
収益力が高い食糧王国・十勝
2018年(平成30)は、札幌に開拓使が置かれた1869年(明治2)から150年に当たる記念すべき年だった。
開拓とは、荒れ地を切り開いて農地、集落、道路をつくり、移住して農業を営み生活することを言う。北海道の開拓も多くの苦労があったというが、十勝地方(以下、十勝)(注)は今や日本最大の食糧供給基地となっている。
2015年(平成27)の十勝の耕地面積は25万5000haで、日本全体の5.7%を占める。農家一戸当たりの耕地面積は46haで、全国平均(2.1ha)の22倍だ。農家一戸当たり生産農業所得は約1200万円で、全国平均(152万円)の8倍。農家がもうかるのだ。
しかし、水文化の面から見るならば、十勝周辺は20種類以上の火山灰土が堆積する排水不良土壌だった。いったい、どのような開拓者たちが活躍してきたのか。
(注)十勝地方
帯広市を中心とする「1市・16町・2村」、合わせて19の自治体で構成される。人口は約34万人。
輪作と排水が土地改良のカギ
「もともと十勝は半分以上が排水不良土壌でして、最初のころは豆を主体とした作物体系だったと聞いています」と話すのは、国土交通省北海道開発局帯広開発建設部農業整備課の野口俊行さんだ。
第二次世界大戦後は小豆の値が高騰し「赤いダイヤ」と呼ばれ競ってつくられた。しかし、豆は冷害に弱く、豆類連作による障害が現れはじめた。1951年(昭和26)に設立された北海道開発局は、昭和30年代から排水改良事業を大規模に行なった。その結果、寒冷地作物と呼ばれるビート(甜菜(てんさい))、馬鈴薯が加わり、豆、小麦とともに「畑作四品」の輪作体系ができあがり、地力を維持しながら継続的な営農が可能になった。排水事業は、畑地の地下80cmほどの深さに孔の空いた管を通すと土中の水分が管に抜け、排水路に流れていく。これが暗渠(あんきょ)排水で、暗渠排水が普及する前は、畑に溝を掘り水を抜いていた。
現在は、例えば収益性の高い長いもを育てるには約1.5mの深さで排水する。作物に合わせて排水の深さも変えねばならず、攻めの農業に応じて排水も工夫しなくてはならないと野口さんは言う。
「でも開拓の初期は用水施設はなく、天水頼みだったでしょうね」
開拓の象徴となった先駆者・依田勉三
帯広開拓の先駆者として依田勉三(よだべんぞう)(1853-1925)の名前は、地元では有名だ。依田は静岡県西伊豆松崎の裕福な農家の三男坊だ。東京で慶應義塾大学に学び北海道開拓を志し、仲間とともに開拓団体「晩成社(ばんせいしゃ)」をつくり、1883年(明治16)5月に帯広へ入った。
依田たちは苦労した。牧畜を興し、田畑を拓くという夢のもと、多数の事業を試している。でんぷん製造、牧場経営、バター製造、食肉加工、函館での牛肉店営業と手を広げたが、結局成功せず、1925年(大正14)に没した。
晩成社の小作だった人は後に「晩成社の依田さんが、ミノをつけクワを抱えている銅像がありますが、そんな姿は見なかった。立派な背広を着て、農場に回ってこられたものです。…依田さんはなかなか温厚でよい人だったが、何をやっても運が悪いのか成功しなかった」と回想している。
なぜ成功事業を残さなかったのに依田勉三が有名なのか?帯広百年記念館学芸員の大和田努さんと話すなかで答えが見えてきた。
大和田さんの説明は、別の開拓者たちの大正期の姿から始まる。「十勝の地場産業が形成されるのが約100年前です。最初は雑穀ですが、規格も乾燥のしかたもバラバラだったので、小樽の商人に安く買いたたかれてしまう。そこで地元で検査して計画的に出荷していこうと『帯広農産商組合』を設立し、農産物検査場を設置した。それを主導したのが高倉安次郎です」と言う。その高倉は近江商人で知られる滋賀県の出身で道内外に販路のつてをもっていた。高倉はほかにも帯広倉庫株式会社、帯広電気株式会社、帯広信用組合(後の帯広信用金庫)を設立した。地場のインフラ、産業制度を整えた地域資本家だった。
観光面で同様の役割を担ったのは、現在の十勝毎日新聞の創業主だった林豊洲(ほうしゅう)である。十勝川温泉の開発や各地の絵はがきを制作し、十勝の観光化を大正末〜昭和初期に進めた。背景には、全国から集まった開拓民が二世の時代を迎え「地元らしさ」をつくる必要があったからだ。「産業だけではなく、メンタリティの部分も急速に整えられていく。観光は、自分の暮らしている土地はどのような所なのか考えるきっかけを与えます。十勝は特徴のない開拓地から脱皮していくわけです」と大和田さんは指摘する。
さらに「十勝らしさ」を象徴する人間として依田勉三をキャンペーンした人物がいた。大和田さんは「『最初に入植した依田勉三は地域の先駆けである』とがんばったのが、岐阜出身の中島武市(ぶいち)です。のちに市議会議員や商工会議所会頭を務めます。晩成社は、耕すだけではなく、加工して消費地まで送るという意図をもったところが、今の十勝の人の心に響きます」と言う。
実際に晩成社は夢を持ち込んだが、手工業的な団体から脱皮できなかった。一方、高倉、林、中島といったインフラや制度をつくった人々がいた。
大和田さんと話してわかってきたこと。それは、十勝開拓が、依田勉三の着想と苦労だけではなく、流通販路を実際につくり、消費市場から信用を受けるに至った制度をつくった開拓資本家たちによって成し遂げられたことだ。
十勝らしさを体現する全国区の製菓企業
十勝らしさを体現している企業の一つに六花亭製菓株式会社がある。創業者は小田豊四郎(1916-2006)。叔父が経営していた札幌千秋庵(せんしゅうあん)帯広支店の経営を1937年(昭和12)に引き継いだ。1952年(昭和27)帯広開拓70年記念菓子を市から任され、「ひとつ鍋」という人気菓子を創作。依田勉三の「開墾のはじめは豚とひとつ鍋」の句からとったものだ。1977年(昭和52)発売のマルセイバターサンドの包装も、晩成社のデザインをモチーフにしている。
ホワイトチョコレートの開発・過当競争を機に、千秋庵ののれんを札幌本店に返し、1977年に六花亭製菓(以下、六花亭)と改称した。
六花の森工場の隣に札内川(さつないがわ)の伏流水を引き込んだ「六花の森」という庭園がある。その管理を行なっている櫻谷(さくらや)康宏さんに多くの話を伺った。祖父は福井県出身の酪農家で、櫻谷さん自身は六花亭の正社員になった。創業者・小田豊四郎、長男で前社長の小田豊さんの話を伺ったが、「六花亭は北海道の六花亭なんだ。売り上げは求めない、ただし世間に出しても恥じない、おいしくて安心して食べられるものをつくってくれ」という前社長の言葉が櫻谷さんの口から自然と出てくるところに感じ入った。
六花亭は道外に出ないが、そのこと自体が味を求めて北海道に来てくれというメッセージ戦略になっている。開拓者たちの遺産をうまく活用していると私には思える。
信用金庫が育てる未来を拓く人材たち
高倉安次郎がつくった帯広信用金庫は金融業務のほかに、起業者を育成する「とかち・イノベーション・プログラム」に取り組んでいる。2015年から2018年度に設立された法人は7社。その事業も農家アルバイトマッチングサービス、複数会社副業型就業マッチングシステム、十勝のアウトドアDMO(観光地マーケティング組織)、オーダーメイド旅行企画、小型航空機シェアリングサービス、十勝移住コンシェルジュ、皮革などのアウトドア家具の製造販売ほか全14事業に及ぶ。
この起業支援と十勝開拓者スピリットはつながっているのか?営業推進部経営コンサルティング室室長の三品幸広さんは「つながっていると思います」と言う。
「十勝は民間開拓の歴史をもっている。晩成社もうまくいかなかった。そういうのを乗り越えて自分たちでやるしかないという気持ちは、あるでしょう。だから、周囲をあてにしていない。われわれ地域のなかにあるもの、自分たちでできるもの、好きなもので事業にすればいいと貫き通す。どんな荒れ地でも粘り強く開拓していった先に自分の目指す世界があるという感覚はあると思うし、私もプログラムメンバーにも言っています」と語った。
さらに常務執行役員の秋元和夫さん、地域経済振興部副部長の太田智也さんは「農業の多様化が重要」と言う。一般に農家はJAバンクから融資を受けるが、多様な作物を多様な販路へ広げたいと思う経営者はそれ以外の金融機関を意識しはじめた。必要に応じて仲介者を務めた高倉安次郎の精神は、今も生きているようだ。
過去の失敗は後世への宿題か?
自分たちで開拓する。この歴史と文化は現在も資産となって生きている。開拓群像を見ると、失敗を重ねた依田勉三や、インフラをつくった開拓資本家たち。さまざまな開拓者たちは協力・結束し、一大食糧生産地を生んだ。そして現代、付加価値を生む食品加工から十勝はスイーツ王国とも呼ばれ、若い世代はGPS制御のトラクターを使い、AI農業を営んでいる者もいる。
依田勉三は成功しなかったが、開拓者たちはインフラと制度を整え、後発者は事業チャンスをつかんだ。そう考えると「成功しない」は「失敗する」ではなく「解決すべき課題を残す」という次世代への宿題を意味するのではないかとも思える。本人は失敗と思っていても。
〈魅力づくりの教え〉
たくさん失敗しないと成功しない。これは現代も使われる起業者への金言だが、粘り強さだけではなく、自分の失敗は後世を助ける公共財ともなる。こうした心根こそが開拓者の条件だ。
(2019年8月21~23日取材)
参考文献
帯広市史編纂委員会『帯広市史』(2003)
十勝毎日新聞社七十年史編集委員会『十勝毎日新聞七十年史』(1989)
北海道新聞社帯広報道部編『十勝人』(北海道新聞社 1988)
上條さなえ(作)、山中冬児(絵)『お菓子の街をつくった男』(文渓堂 1999)