機関誌『水の文化』66号
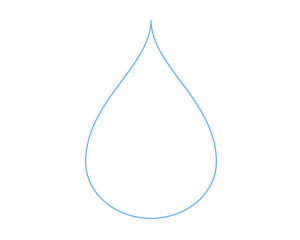
ひとしずく(巻頭エッセイ)
瑞穂の国・用水路の国

多摩川最古の農業用水「二ヶ領用水」。一時はどぶ川と化したが、市民と行政の取り組みによって再生された

-
地域エコノミスト
藻谷 浩介(もたに こうすけ) -
1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。米コロンビア大学経営大学院修了。株式会社日本政策投資銀行参事役を経て、株式会社日本総合研究所 主席研究員。NPO法人 地域経営支援ネットワーク 理事長も務める。著書に『実測!ニッポンの地域力』『デフレの正体』『世界まちかど地政学』『世界まちかど地政学 NEXT』、共著に『里山資本主義』『経済成長なき幸福国家論』などがある。
これまでに、平成合併前の全市町村と世界114ヶ国を自費で巡ってきたが、人生最初の“一人旅”は、生まれ育った山口県徳山市(現周南市)にあったデパートで、迷子になったときだと思う。3歳くらいだったらしい。いつの間にか消えた我が子を必死に探す母が、道行く人に聞くと、「向こうにそれらしい子が歩いて行ったよ」という。追ってみると、商店街を500mほど行った先の橋の上で、東川という小さな川の水面を、一心に眺めていたそうだ。
小学生になると、校区内のあらゆる水路が、どこから来てどこに流れているのか、土管となっている区間の前後まで調べて回った。自宅の裏山の小さな谷川の、源流らしき場所も突き止めた。山麓の溜池から流れ出す水路が、他人の家の裏庭のさらに裏を通って掘り込まれているのにも気が付いた。本で読んだとかそういうのではない。心の中から湧き上がってくる衝動に従い、水がどこから来てどこに流れていくのかを調べずにはいられなかったのだ。
高校時代から親しんだ自転車旅行では、少しの高低差も足にこたえるので、自然に「峠はどこなのか」を意識するようになり、日本全国の主要な水系が、どの稜線で分かれるのかを覚えた。社会人になるとレンタカーの利用も増えたが、自転車を喘ぎ喘ぎ漕いでいた時分には気付かなかった、棚田を潤す用水路網の仕組みにも目が行くようになった。どうやってこんなところにまでと思うような田にも。自然の落差を利用して水が供給されるようにできている。水が流れ下るところには必ず浸食が生まれるわけで、擁壁が崩れないように水量をコントロールし流路をメンテナンスするのはたいへんな労力だが、その地域の人たちは営々とその役割を受け継いできた。農民の勤勉さの結晶ともいえるそうしたシステムが、平成になって各地で消え始めたことに深い喪失感を感じるようになった。
コロナ禍で、家を借りている東京に閉じ込められたこの半年。遠出ができないゆえに近所の探索を繰り返した私は、近くに玉川上水の旧流路があることに初めて気づき、さらにはそこから分水した三田用水が、戦後しばらくの間まで拙宅のすぐ近くを流れていたことを知った。江戸の町は、人口100万人を超えた18世紀には世界最大の都会だったと言われるが、その住民の命を支え、近郊の谷地田を潤したのが、微妙に盛り上がって屈曲する尾根筋を慎重にたどって、極めて緩やかな傾斜をもって引かれた、これらの水路だったわけだ。3歳にして水路の魅力に目覚めたが、56歳にしてようやく足元の宝に気付いたという次第である。
瑞穂の国・日本の隅々に、命の水を配ってきた用水路。先祖の偉大な遺産であり、今も生きる現役の資産であるこの毛細血管のようなネットワークに、私は死ぬまで深い敬意と関心を抱き続けるだろう。今号の特集を契機に、そのかけがえのなさに気付く同好の士が一人でも増えることを願っている。




