機関誌『水の文化』68号
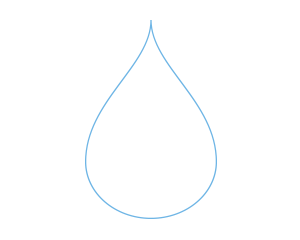
ひとしずく(巻頭エッセイ)
果物と日本人

色づきはじめた晩夏のリンゴ(青森県 岩木川流域)撮影:中野公力

-
文化人類学者
民族学者
石毛 直道(いしげ なおみち) -
1937年生まれ。京都大学文学部卒業、農学博士。専攻は文化人類学、国立民族学博物館教授・館長を経て、同館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。著書に『石毛直道自選著作集』全12巻(ドメス出版)、『日本の食文化史―旧石器時代から現代まで』(岩波書店)など多数。
果実は、糖分がおおく甘い味がし、ビタミン、ミネラル、食物繊維など栄養になる成分を含有し、消化のよい食べものである。そこで、ゴリラ、チンパンジー、オランウータンなどの類人猿は、果実を好んで食べ、果実の熟する季節になると果樹の近くに集合する。人類の祖先もおなじであったろう。
火を使用して、それまで生食ができなかった穀物、イモ類、豆類などが食糧資源に加えられ、肉や魚を加熱調理して食べるようになる以前の人類にとって、生食可能な果物は主食であったろう。果物をよく食べることによって、人類は進化してきたのであろう。
「くだもの」といったら、ナシやリンゴのように、甘く、水分のおおい果肉がやわらかく、生食できる果実を連想するのが普通であろう。しかし、クリやクルミの実などの堅い果実も、「堅果(けんか)」といって果実の仲間である。日本では、縄文時代の遺跡から、カキのほかに、堅果類のクルミ、クリ、ドングリ、トチの実が出土する。堅果類は保存することが可能なので、縄文人は堅果の果実を採集・保存して、主食として利用したものと考えられる。
農業を開始した弥生時代の遺跡からは、堅果類のほかにモモ、スモモ、キイチゴ、ヤマモモ、ウメ、カキ、ブドウなどの、果汁に富み嗜好品として現代にも受けつがれた果物類が出土するようになる。これらは、稲作農業とともに中国南部や朝鮮半島から伝播し、果樹として栽培されるようになったものであろう。
平安時代に中国から小麦粉を練って揚げた食品が伝えられると、これを唐菓子(からくだもの)とよんだ。日本では、食事以外の間食として食べられる嗜好品類を、果樹から生産される果物だけでなく、飴や餅など人工的に生産した菓子類も漢字で「菓子」と書いて「くだもの」とよんでいた。現在の「おやつ」にあたる食品をすべて「くだもの」と称したのである。
江戸時代に甘味を加えてつくる和菓子製造が発達すると、区別するためにフルーツを「水菓子」とよぶようになり、「菓子」ということばから果物の意味を排除するようになった。果物を「水菓子」というのは江戸であり、上方では「くだもの」とよんだ。
だが、「羊羹(ようかん)」や「わらび餅」のような、みずみずしい和菓子類を「水菓子」と称することもおこなわれた。
2011年の一人一日あたり果物消費量(ワインを除く)の国際比較では、1位オランダ444g、2位オーストリア400g、3位イタリア386gで、日本は31位140gである。そして、バナナ、パイナップル、メロン、グレープフルーツなど、カタカナ表記される外来の果物を日常的に食べるようになった。




