機関誌『水の文化』74号
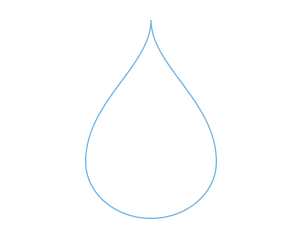
ひとしずく(巻頭エッセイ)
水の動線に自分を重ねて

昔から参拝に向かう人びとの喉を潤してきた「恐山冷水」。清冽なその水は「不老水」とも呼ばれる

-
脳科学者
茂木 健一郎(もぎ けんいちろう) -
1962年東京都生まれ。理学博士。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現在に至る。専門は脳科学、認知科学。フルマラソンに出場する市民ランナーでもある。初レースは40歳でエントリーしたつくばマラソン。出張や旅行先でランニングしながら、旅先の景色や自然、観光名所などを一人で楽しみながら走る「旅ラン」も実践中。
フルマラソンをもう10回近く走っている。小学校2年の時、ふと思いついて校庭のトラックをぐるぐる回って以来、なぜか走るのが好きになってずっと趣味のランナーを続けている。
走っていると、水のありがたさが身にしみる。夏の暑い時には汗をかいて、どうしても水分を補給しなければならない。冬でも、早めの水を心がける。マラソン大会では、ボランティアの方が用意してくださった給水で一息つく。思わず立ち止まって空を見上げる。この水は、もともとはあの空から降ってきたのだなあと思う。
自分で用意してペットボトルに入れて持ち歩く水も頼もしいが、やはりご縁やありがたさを感じるのは、マラソン大会の給水のように、他人にいただく水であるように思う。水は、人と人との心をつなぐ絆となるのである。
野山で蝶を追いかけていた子ども時代、近所の神社の境内に水道があって、よく、仲間たちと「お水飲ませてください!」と声をかけて利用させていただいた。夏の強い日差しの中で、蛇口に口を近づけていただく水は、少し鉄の味がした。
山をハイキングしていて、湧き水があるとほんとうに命が更新されるような喜びがある。みんなが美味しいおいしいと言って飲んでいる。近代的な浄水設備が整う前は、大自然の中でろ過されてきた水をいただくことに、私たちの祖先はどれほど励まされてきたことだろう。
人間の脳は、世界を理解するためにさまざまな認知の仕組みを発達させてきた。そのような世界知の真ん中に「言葉」がある。今急速に進化している人工知能も、人間たちが記してきた膨大な量の言葉から学んで、私たちのまわりの環境についての知識を得ている。
水は、私たちの世界の至るところに流れ、潜み、しみわたっていく。日本語には、さまざまな「水」にまつわる表現がある。「水が合う」、「水を得た魚」、「流れる水は腐らず」、「水の泡」、「水に流す」、「水は方円の器にしたがう」、「呼び水になる」。このような私たちの「水」に関わる表現から、人工知能ならばどのような「水」に関する理解を立ち上げるのだろうか。私たち人間もまた、「水」の意味、ありがたさを時に振り返る必要があるだろう。
これらの「水」に関わる日本語表現から伝わってくるのは、水が私たちの世界の中でさまざまなものを結び、その間を流れ、縁をつないでいく存在であるということだろう。命に水は欠かせない。水は万物をつないでいく。水の恵みを、どんなに科学やテクノロジーが進んだ時代でも、忘れてはならない。
私たちは人工知能なしでも生きていけるけれども、水がなかったら命をつないでいくことができないのだ。
私は出張先で「旅ラン」をするのも好きだ。初めての街で走っていくと、次第に、自分が何かとなにかをつなぐ補助線になっているような気がしてくる。
水は、世界を循環することで命といのちをつないでいく。私も、また、走ることで、水の動線に自分を重ねて、やがて更新されていく。




