機関誌『水の文化』77号
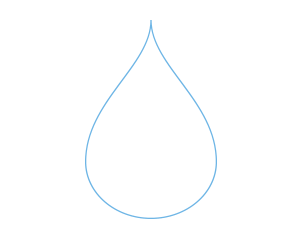
ひとしずく(巻頭エッセイ)
川ガキと共生する 地域の未来

長崎県川棚町を流れる石木川にて(2023年8月) 撮影:村山嘉昭

-
写真家
村山 嘉昭(むらやま よしあき) -
1971年に横浜で生まれ、鶴見川水系の環境で育つ。農業系出版社の写真部勤務を経て、2005年に独立。2017年に吉野川水系の徳島市へ移住。日本写真家協会会員。著書に『川ガキ』(飛鳥新社・2012年)『石木川のほとりにて〜13家族の物語』(パタゴニア・2016年)『サバニ 旅をする舟』(海想・2016年)など。
公園やプールと同じように川などの水辺を日常的な遊び場にしている子どもたちがいる。彼ら彼女らは自宅から水着姿のままで川へと向かい、友だちやきょうだいと競い合うように泳ぎ、水中へ潜って遊んでいる。中には網やモリを握りしめながら魚を追いかけ、度胸試しを楽しむために橋などから飛び込む子どもたちもいる。遊び疲れると河原の岩などで冷えた身体を温め、夕方近くまで水辺で過ごしたりもする。遊び方は環境や年齢、地域や季節によって様々だが、どの子もはちきれんばかりの笑顔をしているのが特徴だ。このような子どもたちをわたしは親しみを込めて「川ガキ」と呼んでいる。
川ガキが“生息”する地域では、そこに暮らす大人たちも元川ガキの確率が高く、水辺への関心が強い傾向にある。小さな頃から川に親しんできた人が多いため、子どもが水辺で遊ぶのはしぜんなことだと理解し、放任ではなく認知しているのだ。
川遊びは危険と隣り合わせでもあるが、このような地域では大人たちが川の流れや地形を把握しており、強い力で深みへ引き込まれる場所などを事前に子どもたちに教えたりもしている。楽しさを知るだけでなく、どこが危ないかを地域の大人が熟知し、見守っているのだ。子どもたちも経験を重ねながら楽しく遊ぶための知恵をつけ、年長者が年少者の面倒をみていたりする。川での事故を防ぐには起こり得るリスクを知ることが必要で、危ないところには近づかず、普段と違う水位や水温の変化に気づいた時には迷わず遊びを止めることが大切だ。子どもたちは親だけでなく地域の大人から時には叱られながら、川との付き合い方を学んでいる。
川ガキ生息地の中には、場所を指定して地区公認の水泳場を設けているところもある。長崎県川棚町を流れる石木川もそのひとつで、地域の子どもたちは気温が高くなる5月頃から川で遊びはじめる。石木川は県内でも有数のゲンジボタル生息地として知られているが、地区の住民はホタルと同じくらい子どもたちが遊べる環境を大切に扱い、守り続けている。川ガキが生息していくには彼らを見守る大人の存在が欠かせないのだ。
かつては至るところで姿を見かけた川ガキだが、現在はその存在が貴重に思えるほど全国的に減少している。水質悪化やダムなどによる河川開発の環境変化も減少要因のひとつだと言えるが、水辺を必要以上に危険視する社会の風潮が絶滅に拍車をかけていると、わたしは考えている。川から人が遠ざかり、地域社会が水辺を含む自然環境に対して無関心になればなるほど、川ガキは姿を消していく。
青空を映して流れる川面には、セミの鳴き声をかき消すような笑い声が良く似合う。水しぶきを上げながら自然の中で遊ぶ川ガキの姿は、未来へ残したい大切な日本の原風景とも言える存在だ。川ガキを絶滅させないためにも、身近な水辺環境に関心を向けて欲しいと思う。


