機関誌『水の文化』78号
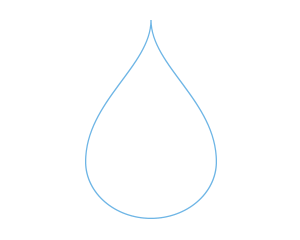
ひとしずく(巻頭エッセイ)
あの香りのコーヒー

フラスコ内の水を沸騰させ、その蒸気圧で抽出するサイフォン式コーヒー。コポコポと湯が沸く様はずっと見ていられる
撮影協力:珈琲専門店 蘭

-
フォークシンガー
なぎら 健壱(なぎら けんいち) -
1952年、東京銀座(旧・木挽町)に生まれ、葛飾区や江東区で育つ。1970年、岐阜県中津川で開かれた全日本フォークジャンボリーに飛び入り参加したことをきっかけにデビュー。コンサートやライブ活動を続け、テレビやラジオ、映画に出演。また新聞、雑誌で執筆。エッセイ集として『絶滅食堂で逢いましょう―なぎら健壱が行く東京の酒場・食堂・喫茶店』『酒場のたわごと』『夕べもここにいた!―なぎら健壱の東京居酒屋』などを、写真集として『東京のこっちがわ』『町のうしろ姿』『町の残像』などを上梓。
サイフォンのお湯がロートに上がってきて、竹ベラで攪拌(かくはん)をする。そしてコーヒーがフラスコに完全に落ち終わるのを見ていた。その昔、そんなコーヒーの淹(い)れ方をしていた。あれは何年ぐらい前だったか。
ドリップ式のコーヒーに慣れてしまった昨今、そうしたサイフォンで淹れるコーヒーが懐かしい。サイフォンとドリップで淹れる方法とは似て非なるものなのかもしれないが、そこまでこだわりもないので、あたしには違いがよくわからない。しかしサイフォンと、ドリップではやはり趣が違う。時間に余裕のない時は、俄然ドリップが重宝なのだが、サイフォンで淹れるコーヒーは時間がかかり面倒くさい分、それが一種の儀式のように感じるのである。しかしいつの間にかサイフォンでのコーヒーはやめてしまった──どうしてだったか?
あたしが最初にコーヒーを意識したのはいつの頃だっただろうか。確か小学校低学年の頃だったと記憶するが、銀座の某デパートの地下にコーヒーを飲ませてくれるスタンドがあった。その側を通るといつもコーヒーのいい香りが漂ってきていた。子供心になんていい匂いだと思っていたのを覚えている。母親はその匂いに誘われコーヒーを注文した。あたしはココアを飲んだ。あのコーヒーのいい香りは忘れられないし、今でも喫茶店の前を通る時、焙煎の香りに同じような思いに駆られる。ただその匂いに誘われて喫茶店に入って注文したとしても、あの香りに勝るコーヒーに出会うことはまずない。
コーヒーとは香りだけなのか? いや、当然そんなことはないだろう。しかし味覚とは舌で感知するのはなんとわずか5%で、匂いが95%ということであるらしい。つまりコーヒーの場合、芳しい香りが重要な要素だと言えようが、実際は産地、コーヒー豆の種類、ブレンドによって香りが微妙に違ってくるのであろう。しかしそこまでは知り得ないし、追求もしない。なんと言ったらいいのだろうか、香りと味が一致するコーヒーを口にしたいのである。
コーヒーを嗜(たしな)む店、昔はまず喫茶店と相場が決まっていた。高校3年生の頃だろうか、喫茶店に入り浸っていた。一日に2、3軒ハシゴということもあった。喫茶店という空間が好きだったんだろうし、友達との会話が楽しかったんだろう。長居する我々に店員がいったい何回水を注ぎ足しに来たことだろうか。最近はほとんど喫茶店に足を向けないようになってしまった。セルフサービスの、カフェ形式のチェーンが増えてから、そうなってしまった──理由は定かではない。
しかし昔ながらの構えのいい喫茶店や、名曲喫茶など見るとついふらふらと吸い寄せられてしまう。
そこで眼にする、律儀なマスターが、律儀にサイフォンで淹れるコーヒーの店なら言うことはない。そうした店で、子供の頃のあのコーヒーの香りをふと思い出すことがあるのだ。




