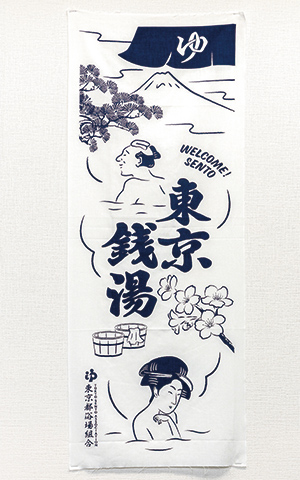機関誌『水の文化』79号

【銭湯】
銭湯が災害時の避難場所に
──個別の事故や火災でも無償で入浴
東日本大震災、そして先の能登半島地震でも「銭湯」の存在がクローズアップされました。銭湯の広い脱衣所なら体を休めることができますし、上水道ではなく自前の井戸を備えている銭湯が多いため、汲み上げておいた地下水を生活用水として提供することもできるからです。そのため、行政と浴場組合が災害時協定を結ぶ動きが出てきています。長い間、地域に根づいて営業してきた銭湯が、災害時に果たす役割について探りました。

撮影協力:久が原湯
家庭風呂の普及で減っていった銭湯
広々とした湯船にゆったり浸かってリフレッシュできる銭湯は、地域住民の交流の場として親しまれてきた。一方で、近年は災害時の避難場所としての役割も担っていることは、あまり知られていないかもしれない。
1957年(昭和32)に設立された東京都公衆浴場業生活衛生同業組合(以下、東京都浴場組合)は、銭湯経営者の組織だ。主に銭湯の経営を安定させることを目的に活動している。同組合の副理事長・佐伯雅斗(まさとし)さんに銭湯の歴史と現状を伺った。
銭湯の歴史は古く「庶民の方がお金を払って入浴する施設は、江戸時代から始まっています」と佐伯さんは説明する。
「当時はお風呂というより足湯。水と燃料がとても貴重だったので、本当に少ないお湯を沸かして入っていました。そこに大勢で入るから、お湯はドロドロになってしまう。一番風呂が気持ちいいというイメージは、ここからきています」
イメージといえば、昭和時代の銭湯のお湯は熱すぎるくらいの温度だった。これにもわけがある。
「ろ過装置が今に比べてよくなかったので、お湯が汚れてくるんですね。だからあえてお湯を熱くしておく。すると、お客さんがどんどん水を入れるから、お湯があふれ出て入れ替わっていくんです」
そんな昭和の時代が銭湯の最盛期。全国で銭湯の軒数がもっとも多かったのは1968年(昭和43)で、当時は東京都内に約2800軒もあった。ところが現在、都内にある銭湯は約420軒だ。
「1964年(昭和39)の東京オリンピックあたりから家庭風呂が普及していき、銭湯が減りつづけています。1週間に1軒、1年に50軒ぐらいのペースでなくなって約50年経ちました。全国でも1700軒ぐらいで、銭湯があるのは大都市圏だけになってきています」
銭湯が減少の一途をたどっている背景には、銭湯の区分の違いがある。「一般公衆浴場」と呼ばれる昔ながらの銭湯は、公衆浴場法に基づいた許可を取得し、さまざまな規制に則って営業している。他方で娯楽施設の要素を備えた、いわゆるスーパー銭湯は「その他の公衆浴場」と呼ばれる。
「一般公衆浴場の場合、他の銭湯から約300m以上離す、物価統制令による入浴料金の上限といったルールが定められています。特に料金の上限がネックで、ここ50年ぐらい、新たに一般公衆浴場の許可を取ったところはありません。だから減る一方なんですよ」
銭湯と行政が組めば高齢者の見守りも可能
そんななか、近年注目されている銭湯の役割の一つが、高齢者の見守りだ。佐伯さんは「お年寄りには適度な運動と適度なコミュニケーション、清潔であることが必要」と言う。日常的に近所の銭湯へ通えば、この3つはすべて解決する。
「お客さんのなかには、どんなに天気が悪かろうが毎日やってくる人もいます。開店30分前には店の前の椅子に座り、来た人たちとおしゃべりしながら待っている。生活リズムの一つとして毎日のように銭湯に通いつづけることが、健康維持のために大事なんです」
銭湯が高齢の常連客に欠かせない存在だからこそ、地域によって利用者を見守るための取り組みがある。例えば江戸川区では60歳以上の人に入浴証を配布、各銭湯でバーコードを読み取って利用状況を把握するシステムを導入しているという。
「昔は常連さんがどこに住んでいるか知っていて『何かあったら連絡するわ』ぐらいの感覚があったんです。だけど今は個人情報の問題で名前や住所、家庭のことを聞きづらい。でも毎日のように来る常連さんだと、認知症の兆しがわかりますし、『家にあやしい訪問者が来た』という話も聞かなくはない。一人ひとりを例えば番号で把握できれば、そういうことも役所に伝えられる。我々と行政が組めばできるなと思っています」
高齢者の見守りに加えて、夜間も営業している銭湯は、時には親とケンカして家出した子どもの駆け込み寺にもなっているそうだ。
「自分の親や子どもを安心して預けられる場所、困ったときに頼れる施設として、銭湯を再認識していただきたいですね」
災害時に求められる「入浴」を無償提供
地域に根づいて営業を続ける銭湯は、2011年(平成23)の東日本大震災を機に、その役割が見直されはじめている。
災害時に電気の供給が止まっても、銭湯には何トンもの水が蓄えられているため、生活用水を賄うことができる。「食料」と「寝泊まりできる場所」に次いで被災者が求める「入浴」を提供できる価値は大きい。災害に見舞われた直後は誰もが命の心配をするが、数日経つと入浴していないことが気になり出すそうだ。銭湯があれば、被災者の衛生面の問題も解消される。
今も銭湯が多く残る地域では、万が一の有事に素早く対応できるよう、浴場組合と行政が協定を結んでいる。大田区と東京都浴場組合大田支部(以下、大田支部)は「災害時における貯蔵水の優先提供」「各浴場の施設及び敷地における被災者の救援活動」などの支援を定めた協定を2014年(平成26)に締結。区内の銭湯が、災害時に必要な生活用水や設備を提供する場となった。
「東京都浴場組合の本部からは、東日本大震災以降、災害時には1日でも早く銭湯を開けて、被災者に無償で入浴させるように、と言われています」
大田支部の支部長・山岸勝利さんと、副支部長・小林千加史(ちかし)さんは、そう口をそろえる。「お金云々ではなく、まずは開けよう」という姿勢だ。公衆衛生がいかに重視されているかが伝わってくる。
また、大田区総務部防災計画担当課長の長谷川敬(けい)さんは「石破総理大臣の就任以降、スフィア基準を踏まえた避難所環境の改善がキーワードになってきた」と明かす。スフィア基準とは、災害の被災者が生活を営むための人道上の最低基準のことで、災害関連死を防ぐために定められている。
「1人のスペースが3.5m2、水は1人当たり1日15L、入浴設備は50人に1基などと決められています。ただし大田区は想定で約20万人が避難しますので、浴場組合さんに早く銭湯を再開してもらえれば、こんなにいいことはありません」と長谷川さんは言う。
大田支部に加盟する銭湯は、災害時の一時避難所になっている。受け入れ可能な人数は店舗によって異なるが、クラッカー、飲料水、毛布の3点セットを備蓄しているそうだ。
浴場組合と行政の協定は、災害時に限らない。集合住宅における火災やインフラ事故などで避難生活を余儀なくされた人びとが無料で入浴できる防災協定も結ばれている。一例として佐伯さんが教えてくれたのは、2025年(令和7)1月に発生した埼玉県八潮市道路陥没事故にまつわる入浴支援だ。
「事故の影響で、埼玉県が下水道の使用を制限すると宣言したとき、これはみんなお風呂に入れなくなる、と。そこで八潮市に隣接する足立区の支部長に『無料入浴の受け入れ準備をすぐに開始してくれ』と連絡しました。それが夜中の12時頃です。翌日の朝10時には足立区が受け入れを決定し、その日から無料入浴が始まりました」
これほどスムーズに対応できたのは、区と浴場組合との協定がしっかり整備されていたからこそ。最終的には葛飾区や台東区の浴場組合も足立区に追随し、1週間で約2万人の八潮市民を受け入れた。
地域の大切な役割を担う見過ごされがちな存在
行政と浴場組合の連携は、地域や銭湯の振興の面でも積極的に行なわれている。都内では最多とされる33軒の銭湯がある大田区では、浴場施設への改善助成金や大田支部が実施する各種イベント(スタンプラリーなど)を通じて支援している。
こうした取り組みの最大の目的は、銭湯の廃業防止だ。
銭湯「改正湯」四代目でもある小林さんは「一般家庭の人が1週間に1回でも銭湯を利用すれば、二酸化炭素の排出量を相当抑えられます」と力説する。銭湯「久が原湯」三代目の山岸さんも同意見で「CO2削減は15年ぐらい前からずっと言いつづけています」とのこと。「薪でお湯を沸かしていた店は都市ガスにして、二酸化炭素をなるべく排出しないようにしています。昔ならエコ、今ならSDGs。そういう任務を我々はずっと担っているんです」
公衆衛生はもちろん、災害時の一時避難所から観光振興まで、銭湯の役割は幅広い。これを小林さんは「街の何でも屋さん」と形容した。そんな銭湯には、街に存在することで果たされる任務もある。
「子どもをお風呂に入れるとき『10数えたら出なさいよ』ってよく言うじゃないですか。あれってお風呂に入る教育、浴育なんですよ。昔の銭湯には『おまえ体を洗ってから入れよ』って、よその子を注意するお客さんがいらっしゃった。そういったアナログな魅力が、銭湯にはまだまだ残っています」
災害時の受け皿、高齢者の見守り、子どもの教育など、大切なのに見過ごされがちな役割を担う銭湯。もし近所にあるのなら、たまにはふらっと足を運んでみてほしい。かつて身近な存在だった銭湯が、今もそこにある尊さをしみじみと感じられるはずだ。
(2025年4月30日、5月1日取材)