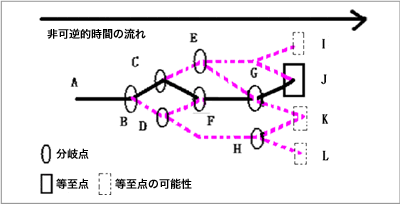水の風土記
人間を支援するための社会関係とは
〜ボトムアップ型人間関係をつくる〜
当センターでは、水をめぐる「人々の関わり」を大きな研究テーマとしています。この「関わり」にもいろいろな形があるわけで、りっぱな父親が子どもを見守ってやるような上下関係もあれば、住民同士の関係に行政が介入するような三者関係もあります。 こうした多様な社会関係の中で、「支援」という言葉をキーワードに、強い個人からなる社会に異議申し立てをしているのがサトウタツヤさんです。サトウさんの目には、現代社会に何が欠けていると映るのでしょうか。
-

-
立命館大学文学部心理学科助教授
サトウ タツヤ -
1962年生まれ。東京都立大学人文学部卒業。福島大学行政社会学部助教授を経て現職。
主な著書に『日本における心理学の受容と展開』(北大路書房、2002)、『「モード性格」論』(紀伊國屋書店、2005)他多数。
ボトムアップ型人間関係論の構築?
私は、ボトムアップ型人間関係論の構築ということを提唱しています。簡単に言うと、水平型の人間関係の構築ということです。特に、私たちがターゲットとしているのは職業上の人間関係ですね。例えば、医師と患者の関係、先生と生徒の関係、このような関係をいかに水平にしていくか。ボトムアップ型人間関係論の構築というのはそうしたことを考える枠組みです。そのような関心から、いま、法における人間関係にも注目しています。
いま日本で議論されている裁判員制度にも関心があります。裁判員制度は、刑事裁判に国民が参加して判決と量刑を裁判官と共に決定しようという制度です。日本では2009年までに実施予定ですが、評判が悪い。しかし、私は導入していかなくてはならないと考えています。一人一人の国民が投票という形で政治に参加するのと同じように、裁判員という形で司法にも国民が参加すべきだと思います。
裁判員制度から見えてくる人間関係
ではなぜ評判が悪いのでしょうか。一つは実施までの持って行き方が悪いというのがありますが、それはおいておくとして(笑)、日本の文化では、裁判というものはお上がやってくれるという発想です。お上がダメな場合はどうするの?というと水戸の副将軍がきて悪い人を懲らしめてくれる(笑)。そういう世界観をもっている。お裁きに自分たちが関わるのは役割過剰ではないか、という発想があるから、裁判員などにも忌避感情が強いと思うのです。
アメリカはお上に裁きをまかせる文化ではありません。アメリカはもともと植民地ですから、自分たちで裁こうという意識が強く、多少まちがいがあってもいいから自分たちで行いたいということで、陪審員による裁判になっています。ただし、間違いがあったらたいへんだから、刑事裁判の判決は慎重になるというシステムです。O.J.シンプソンの裁判が典型で、刑事裁判は無罪となりましたが、損害賠償金は支払っています。本人も民事的にはほぼ罪を認めているとも言えます。日本でも最近、刑事と民事の判断が分かれた事件がありましたが、憤っている人が多かったようです。刑事が有罪なのに民事の損害賠償を認めないのであれば大変ですが、その逆の場合は慎重な判断だとして尊重されるべきでしょう。
日本では司法に国民が参加するという意識がまだないので、「裁判員のつとめをはたすために、一日とられるのは困る」という次元の話が多いようです。しかし、実際にやるとしたら何が必要なのか、もっと議論する必要があるでしょう。何が問題になるでしょうか。
大事なことは「理解の支援」をどうするか、ということです。広い意味で「対人援助」と呼べると思いますが、人が何かをする時に主体的に判断できるようなバックアップシステムをつくらないと、いくら良い制度であっても、機能しません。裁判人になった人が「裁量の判断」ができるような「支援」を進めてほしいのですが、実はこれが先行きが明るいわけではないのです。たとえば、一般の人がホームページで裁判員制度を調べてもまったくわからないのではないでしょうか。単純に言えば、ホームページの漢字にルビをふるとか、そういうことから国民の理解を支援してほしい。おそらく法曹関係の方々は裁判員制度について「ホームページに情報を掲載している」=「国民に周知している」と考えているのだと思いますが、理解を支援しているとは思えません。それなのに、理解できないのは国民の責任、みたいなスタンスをとるとすれば、裁判員制度がうまく回っていくとは思えません。 俗に裁判所、検察、弁護士のことを法曹三者と言いますが、これらが別々に裁判員制度のHPを作っているのに、相互リンクが張られていないのです。まず法曹の人たちが一致団結して物事にあたってほしいと考えるのは私だけではないはずです。
理解の支援が大事なのです
裁判員制度を始めるとしたら、裁判員が安心して仕事をできるような工夫をすべきです。この場合の仕事とは「良い判決を下す」ということです。私はあるところで、裁判員を支援する法曹関係者は「孫の写真を見るか、犬を抱け」と半ばふざけて半ば真剣に書いたことがあります。どういうことかというと、笑顔が大事ということです。高齢者施設等で犬などのペットを飼うことが流行っています。それはお年寄り自身の仲間が増えるということではなく、犬と接している光景を見ることで、他の人がお年寄りに関われるようになるんですね。例えば、19歳のボランティアがいて、無口のお年寄りがいる。そのボランティアの方は、知り合いでもないお年寄りにはなかなか関われないですね。黙っている姿を「機嫌が悪いのかな」と解釈してしまう。でも、もしお年寄りが犬に接していると、ボランティアの方は犬について話しかけることができる。犬を媒介にすることで、関係ができ、表情を変える。それがコミュニケーションを活発にし、犬は理解の支援に重要な役割を果たすわけです。
同じ事が裁判員制度にも言えるので、裁判官などの法曹関係者は「孫の写真を準備しろ」と書いたわけです。裁判員制度が実施されても、市民にとって裁判官はやはり恐い存在です。裁判員は「こんなことを言って間違ったらどうしよう」と思ってしまうかもしれないし、そうなると自由にものが言えなくなる。それでは、何のために裁判員制度をつくったのかわかりません。裁判員と市民の間の上下関係がそのまま持ち越されるのでは、現行制度を変える意味がない。この関係を水平にするためには、コミュニケーションのしやすさをつくり、理解の支援を進める必要があるのです。「犬をだけ、孫の顔を見ろ」というのはこれをやれというわけではなく、シンボリックな主張です。良い判断をするためには知識「のみ」が必要なわけではないのです。ゆったりした気分で判断することが大事なのです。
まぁ、こういう主張は受け入れられませんが、あえて言い続けることが私の仕事でしょうね。
専門を半分おりる
裁判官もそうですし、この後で述べる医師もそうですが、専門職が自分の役割を半分降りるということができるかどうか。そこが、相手を支援する時のキーポイントになります。これは、なかなかできないですよ。できないのならば、せめて相手とフレンドリーにコミュニケーションしてほしい。
例えば、北海道浦河に社会福祉法人「ベテルの家」があります。ここには心の病をもった人達が当事者として生きるための支援施設なのですが、ここの医師が大人物で、役割を半分降りながら責任は取るということを実践しています。例えば、医師と患者が話をしていて、医師が「どう、薬をやめてみる?」と尋ねる。問われた本人も恐いし、医師も恐い。でも、できてしまう。
専門職が半分役割を降りる人間関係というのは、双方が主体的になり、自分で考えるということです。専門家だけが知識をもっていて、「こうした処遇がいいでしょう」と言っているのではだめなのです。これは「あなたがたは専門職の言うことを聞いていなさい」と言っているのと同じであり、こうしたパターナリズム(父権主義)的関係は変わっていくべきでしょう。専門職は仕事をするために知識を得ているのであって、べつに偉いわけではない。相手に還元するための専門知識なのですから、「教えてやる」のではいけないということですね。
支援者としての医者
では、どうしたらそうした関係を変えていけるか、といえばやはり訓練システムを変えることだと思うのです。例えば医者が病院で訓練を受けるインターンシップという制度がありますね。医者のインターンシップで研修医は病院に行くわけですが、それは常に正しいとは限らない。研修は病院ではなく、患者さんの家に行くという発想があってもいいでしょう。なぜかというと、医療のもっている「患者を治す技術」ばかりが強調され、「病を得た人間を支援していく」という側面が忘れられていると考えるからです。
いまの医療は、病気を切り刻んで専門的に見ているだけで、人を支援するということをしていないと思います。もちろん患部というか病気の根本原因への治療が大事なのは当然です。ただ、現在では慢性病が増えてきており、病と一緒に生きる人をどう支援するかという側面がいやがおうでも求められてきます。病と共に生きる人を支援するとは、「生き方や考え方」を支援するわけです。したがって、対人援助、医療、法務の専門能力によるサービスを与えるだけではなく、人が生きていく上での決定や生活を援助していかなくてはならない。ここでも、患者と医師が水平的になっていくことが求められるわけです。
ケアの本質とは
そこで気を使わなければならないことは「語ること」「語りに耳をかたむけること」です。
病気になる人は、何かを語ります。語られた医師も、普通の医者なら「○○病ですね」と宣告して終わりです。こちらとしては、「三日前から痛かった」とか、一生懸命話しますが、結局、医療の枠組みだけで解釈され、効率的に治療され、直ればもう来なくていい。
語ることは治療行為にとって邪魔なのでしょうか。そうではなく、語ることは病の本質なんです。これはカナダのアーサー・フランクという医療社会学者が強調することです。
病気になるといろいろな人から病気について訊かれます。家族は家族の関心から、友達は友達の関心から、同僚は仕事の関心から、看護婦は「朝どうですか」と、全部訊かれます。繰り返し訊かれること、繰り返し答えることは、病の本質の一部なのです。
そのように病が語られあう中で、医師だけが超然として、診断という自分の語りだけを優位なものにしておくのは、考え直さなくてはいけません。直接診療に関係ないように見える患者の語りをどう支えるかは、医師と患者の関係を水平にするために大事なことなんです。
自分が自分のことを語っているのに、相手側が必要な所のみ回収されてしまうことを表すのに、「語りの譲り渡し」という概念があります。例えば、友達が見舞いに来たら、「もうすぐ良くなる」なんてことも語ることになる。すると、そこだけを友達は回収していく。病人である自分が相手に気をつかっている。同じように医者は診断名をつくような語りだけを回収する。では、本人の気持ちはいったいどうなのかというと、誰にもくみ取られず、まったくケアされていない。そういうことを考えると、医療関係で、医者という専門家と患者のどちらが主なのかを見ていくことが医療の人間関係を変えることにつながります。
支援者としての占い師?
媒介するということは、専門知識をわかりやすく説明するだけではなく、相手が意思決定を行うことを支援することです。
おもしろい話がありまして、例えば、ある医療コーディネーターの人が自分の値段を1時間あたり5千円と決めたのです。その価格はどんな職業を参考にしたのかと尋ねますと、「占い師」。
手術をするかしないかという相談を、占い師にする患者さんが多いそうですね。家族にも相談できないし、自分の心の内では7割方手術すると決めていても、それでOKとは誰も言ってくれません。ところが、占い師に相談に行くと、話を聞いてくれ、ちゃんと見てくれるので、「手術をする方に7割方傾いているな」という気持ちが分かるわけですね。占い師という職業は、相手が考えていることを、ポンと言うのが仕事でもあるわけで、それに違う理由をつけて、「手術をうけるべし」と言う。だから本人の満足度も高いわけです。
でもそうたやすく意思決定できないグレーゾーンも当然あるわけで、そういう場合には医療コーディネーターのような人々による決定支援が必要です。それはやさしく語るのではなく、具体的に誰かが何かをしなくてはならない時に、役立つようなものがあればいい。
支援のためのモデルづくり
その流れの中で、いま私が取り組んでいるのは、養子縁組をしている人のインタビュー調査や妊娠中絶、あるいは化粧にいたるインタビュー調査です。化粧を除けば、本人にとってはどのような判断をすればよいのかわからないことです。
例えば、妊娠中絶の場合。「大学生が自分の妊娠を知った時にどうすればよいか」という問題ですが、この場合、あからさまに相談することもできないし、みんなに話をして意見をもらうということでもない。ですから、たいへん限られた人の中で、その女性は話をして考えていきます。その過程で、いろいろな対応が考えられる中で、結果として例えば「中絶」を選ぶかもしれないし、「シングルマザーとなる覚悟で産み育てる」というように、必ず到達する結論はあるわけです。このような、結論にいたる径路を調べ、他の方の参照例になるようにモデル化するわけです。発達の過程を下の図のように考えたいのです。ゴール(図では等至点)も複数、径路も複数。人生はしなやかな構造であって、発達段階のように達成しなければいけない何かがあるわけではないんです。
たとえば進路について、ニートはダメだとか言っても、ニートになった人に対してどういう恢復過程があるのかを示せなければ意味がない。あるいは、ニートの状態も人生の径路のうちの一つにすぎないという発達モデルが必要なのです。こうしたことは他にもたくさんあります。それをぼくは掘り起こして、こういう選択肢もあるよと示したい。
メタ理論のレベルでは選択肢を提示することの重要性を喚起していく。それも私の仕事の一つです。特に、あからさまに相談できないことは、どのような選択肢があるかわかりにくい。本当は、いろいろな選択肢があるのに、選択肢があることさえあからさまには出てこない。そんなときでも掘り起こしてみれば必ず選択肢は見えてくる。そういう努力をエンカレッジ(勇気づける)ような発達モデル、生活モデルを作りたいのです。
また、どのようなことであれ、選択肢が一つしかない場合には、人間関係はどちらかが従属的になる。だから、人間関係を水平にすることと多様な選択肢の呈示は裏表のことだと考えています。医療であればセカンドオピニオンとかジェネリック医薬品とか出てきました。それによって私たちの行動の自由は拡大したのです。選択肢は文化的・制度的に可視化していく必要がある。そして心理学の理論もそのようなお手伝いができればいいと思っています。
見通しをもって促す
支援できる人というのは、見通しをもって促す力をもっているということです。
災害対応には、そういう役柄の人間をシミュレーションを重ねて育てていくしかない。
教師も同じですね。教師は、見通しをもって、自分から上手に生徒を手放す、つまり親離れを促すのが仕事です。これが下手だと、いつまでの生徒を抱え込んでしまう。
教師論でいうと、ボクサーでエディ・タウゼントという人がいまして、大勢の弟子をもっていた。今俳優の赤井秀和もそのひとりです。彼が言うには、「みんなかわいがられたと思っていて、自分が一番弟子だと思っている」と言うわけです。自分を振り返ると、私の師匠もそうでしたね。みんな一番弟子と思うような扱いをしてくれて、ちゃんと手放す。良い選択や判断のためには、知識があること、選択肢があること、選択を安心して行える環境、この3つが絶対に必要なのです。ところが、医療や裁判では、1つ目しか重視されていない。そんなことを考えると、日本は支援の情報は多いですが、支援のモデルが少なかったり、支援の選択肢を見えなくさせている面がずいぶんあるのかもしれませんね。
最後に一つ提案のようなことを言っておきます。専門家と、そのサービスを受ける側の違いがあるということを分かった上で、専門の知識をきちんと媒介できる対人援助が大事なのです。医療だと国家試験を落ちた人、裁判でしたら、司法試験を落ちた人が、落伍者なのではなく、専門職と普通の人をつなぐ新しい対人援助という役割を担えるようにするといいと思っています。複線径路という発達モデルとも合致すると思いますが、どうでしょうか。
補記:名前をカタカナ表記にしているのも、単なる選択肢を増やすということですが、これが結構難しい。メディア特に新聞はカタカナ表記にしてくれない(つまり何かの制度的社会的なものに抵触している)。今回、カタカナ名での登場させていただいて、大変うれしく思っています。
(2005年9月12日)
【参考サイト】
立命館大学文学部心理学科 助教授・サトウタツヤ(佐藤達哉)
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~satot/
ボトムアップ人間関係論の構築プロジェクト
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hs/kenkyu_2004/bottomup.htm
【参考文献】
佐藤達哉 2004 「ボトムアップ人間関係論の構築」 21世紀フォーラム、NO94,24-32
サトウタツヤ 2005 クリニカル・ガバナンスからみた医療・法曹職のあり方に望むこと 『現代のエスプリ』458号「クリニカル・ガバナンス」、199-208。