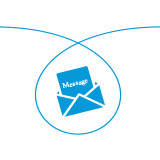水の風土記
日本における水法の現在
〜水資源の利用と保全のルール
―― 水法の視点で水を見る〜
河川法によれば、流水の占用許可がなければ、河川の水を勝手に取水することはできません。また、河川の流水は、財産権の目的となることもできません。一方で、地下水は、一般的に土地所有者が自由に採取することができると解されています。身近にある水でも、存在の形態が違えば、自由に利用できるかどうかも異なってきます。このような差異は、なぜ生じるのでしょうか。水資源の利用を考える際には、一筋縄では解決できない法的問題に直面します。 健全な水循環系の構築のために、「水とはいかなる存在か」という水資源の性質をめぐる問題に迫りつつ、水資源の利用と保全の調和を図る「水基本法(水に関する体系的な統一法典)」を制定するには、どのような課題があるのでしょうか。創価大学法学部教授 宮崎淳さんに、日本の水法の現状と課題をうかがいました。
-

-
創価大学法学部教授
宮崎 淳 みやざき あつし -
1964年三重県に生まれる
1987年創価大学法学部卒業後、法学部教授。研究テーマは水法(水資源の利用と保全の法理論)及び人格権法。
水法を学ぶきっかけ
学問の師との出会いが、水法を学ぶきっかけとなりました。私の大学院時代の指導教員は、板橋郁夫教授です。同教授は、『米国水法研究』(成文堂 1972)で法学博士(早稲田大学)を取得され、「水資源・環境学会」の初代会長も務められた水法研究の第一人者です。
その板橋先生を創価大学に招聘するときに、水法の講義が開講されました。水法といえば、明海大学に三本木健治先生(現在、同大学大学院教授 国際水法学会理事)がおられますが、水法という講義をもたれてはいないと思います。日本で水法の講義を開設している大学は、本学だけではないでしょうか。現在では、その講義を私が引き継いでいます。
もともと板橋先生は民法がご専門でしたので、当初、私の興味は民法の領域しかありませんでした。今から20年ぐらい前でしたから、水も最近のようには注目されていません。そのうえ、水は素人目に見ても厄介なものだと感じていました。流動する水は、資源といえばそうですが、洪水などの災害が起これば資源ではなくなって不要なものになる。そういうことがおぼろげながらわかっていましたので、そんな厄介なものを研究対象とすることに二の足を踏んでいたのです。しかし先生から「水は大事だから」と諄々と諭されているうちに、その気になってしまいました。
当の板橋先生がなぜ水法を研究するようになったかというと、指導教授であった斉藤金作先生の影響であったと聞いています。斉藤先生は著名な刑法学者でした。
斉藤先生は実家のある埼玉で、水不足からくる水争いを目の当たりにし、「これからは水の時代だ」と確信されて、板橋先生に水法を研究するように指導されたそうです。
斉藤金作 (さいとう きんさく 1903〜1969年)
法学者で共犯論の大家。1928年早稲田大学法学部独法科を卒業。助手、助教授を経て、1942年同大教授に就任。1954年に学位論文「共犯理論の研究」法学博士(早稲田大学)。
日本における水法の位置づけ
アメリカのカリフォルニア州では、UCバークレイ校やスタンフォード大学といった有名な大学には水法の研究者がいますし、水法領域を専門に扱う弁護士もいるくらいです。海の向こう側では、水法が盛んに研究されているのに、なぜ日本ではそれほどではないのでしょうか。まず考えられるのは、日本は降水量も多く、水が比較的豊富であるために、地域的な水争いはあるものの、一般的にはそれほど深刻な水事情ではないことが挙げられます。
もう一つは、日本の行政は、官僚主導で治水、利水、水質と完全に権限が分かれています。いわゆる縦割り行政です。それゆえ、小間切れに規制法ができたわけです。このような状況が、水に関する法領域の形成を、体系的に行なう足かせとなったといえるかもしれません。
現在では、水に関する統一法典の制定に向けた共通認識が芽生えつつあります。水基本法や水循環基本法をまとめよう、という動きがそれに当たります。
水に関する統一法典の制定を契機に、水を一元的に管理する行政機関ができた場合には、そこに権力が集中するという懸念もあります。現状の良い点は、権限が分散していて勝手に触れないところにあります。各省が牽制し合っている。それで結果的に、水資源の保全につながっているという側面もあると思います。縦割りの弊害ばかりが強調されがちですが、プラスの面もあるというのは言い過ぎでしょうか。でも、もう少し横の連携があってもよいことは事実です。そういう意味で、「健全な水循環系の構築」という理念が唱えられたのは、よい機会になったと思います。「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」もできました。
水循環基本法
典型的な縦割行政になっている日本の水制度を改め、健全な水循環サイクルを取り戻して国民の生命と安全を守るために、「統合的水資源管理」の基本理念に基づき、水循環基本法案及び水循環政策大綱が研究された。 国会議員と有識者の代表からなる共同座長会を設けて、研究会が運営された。
「万人共有物」としての水
水法とは、一言でいうと「水資源の利用と保全のルール」のことです。
ローマ法に起源がある「誰のものでもない、みんなで使えるもの」という考え方には、「公」の性質が前面に出てきます。
水資源には、このローマ法起源の「公」の性質が反映されます。水の持っている「みんなが使える公共物」、つまり「万人共有物」という性質です。
河川を流れる水は「公共物」ですが、流水の占用許可または流水使用の慣行が社会的に承認されれば、水利権を取得します。その権利に基づいて流水を使った後に、それを河川に返すと、再び誰でも使える「公共物」に戻ることになります。
水利権について、私法(民法)の立場からみれば、水利用の利益を享受できるという私権(財産権)性が表に現われます。これに対して、公法(行政法)の立場からは、水利権は河川管理者が特別の使用権を設定する公物使用権の特許と解されますから、公権性が前面に出ることになります。水を「物」といってよいかどうかは別にして、「公共物」といった場合には、みんなが使えるものをどう管理するかという行政法の問題とも直結します。これらの関係について、いかに接合し調整する理論を構築していくかが、我々がなすべき課題の一つだと考えています。
水資源のコアとしての公共性
水というのは法律的にみると、どういう存在なのでしょうか。
アメリカには各州に水法典があり、そこで「水はパブリックに属する」と定めている州があります。そして、水はパブリックのものだから、州政府の水資源局などに管理させるという構図になるのです。
日本では、公水私水区分論のもとで水の性質が語られる場合があります。しかし、公水か私水かという二元論は、できるだけ避けたほうがいいと思います。この水は私水でこれは公水、と分けて考えているのは、あくまでも人間です。河川に流れているときは公水だけど、地下水になったら私水になるから自由に使っていい、でも使ったあとの水が河川に流れ込んだら、また公水になるというような考え方は、人間の都合で水の性質がさまざまに姿を変えるということを意味します。このような見方は、法的に考えて妥当といえるでしょうか。
河川管理者によって、いったん流水の占用許可がなされると、つまり許可水利権が与えられると、私権性を帯びて権利者が排他的に使用できることになります。許可をもらった人は水を自分の支配下において使用し、水がその支配領域から出た段階で、また「公共物」に戻るのです。私は、「水のコア(核)には公共性があり、許可された時点でそこに私権性が覆い被さる」と考えています。例えて言えば、あんパンのようなものです。コアであるあんには公共性があるが、パンの生地が覆い被さることで私権性が公共性を包み込み、河川に戻るとその私権性が剥がれ、あんだけになって公共性が露顕すると考えるのです。
また、流水利用の慣行が社会的に承認されたり、流水が地下水となって土地所有権の効力が及ぶようになったときも、水の公共性が私権性で覆われていると解することができます。要するに、「水資源のコアには公共性が存在し、それが私権性で覆われる、剥がれる、覆われる、剥がれる、という過程が水循環である」との見解に至るようになりました。つまり、水の公共性に対する私権性の被覆が、水の排他的利用をもたらし、その剥離によって水の公共性が露顕されるという考えです。
「物権的権利」という概念
慣行水利権は、一般的に慣習法上の物権であると解されています。しかし、慣習によって成立した水利権を、民法典で規定された典型的な物権と捉えることに、私は少々違和感を覚えます。なぜなら、物権の一般的な性質とは異なった側面を有するからです。
例えば、典型的な物権には観念性があります。つまり、所有権を持っている人は、所有物を利用してもしなくても、その権利が消滅することはありません。ところが、慣行水利権の場合は、水を利用しなくなったり、もしくは水利用の必要性がなくなったときには、その時点で水利権は消滅してしまう。そもそも水源が枯渇してしまった場合にも、水利権はなくなってしまう。したがって、典型的な物権が有する観念性を欠くなど違った側面があるので、私は慣行水利権を「物権的権利」と呼んでいるのです。水利権は、ほかの物権との性質の違いを重視して、「物権的権利」と解すべきではないでしょうか。
水利用と土地との関係
水は土地の表面か地下を流れていきますから、土地に制約を受けます。つまり、水の受け皿としての土地との関係が重要視されるわけです。水利用と土地との関係が最も顕著に現われるのは、地下水利用と土地所有権との関係です。地下水は、水質がほぼ一定で、アクセスも容易なため、震災時にも利用できるし、使い勝手のよい水として認識されています。
地下水利用と土地所有権との関係については、原則的に地下水には土地所有権の効力が及ぶと解したほうが、法律上の救済を考える上で都合がよいと思います。例えば、Aさんが地下水を汲み上げ過ぎて、Bさんの土地が地盤沈下した場合、Aさんの土地所有権の効力が地下水に及ぶと解し、BさんはAさんに対して土地所有権の侵害に基づく差止請求や損害賠償請求ができると考えるのです。これに対し、地下水は公水であって土地所有権の効力が及ばないとすると、公水の管理主体である公共団体などに管理上の瑕疵(ミス)を追求することを認めることになります。地下水の管理責任は、地下水が管理可能であることを前提に理論構成されていますから、地下水の流動メカニズムが把握され、その管理が可能でなければ、管理責任を問うことはできません。
また、地下水には、地盤を支持する機能もあるので土地の構成部分と捉えたほうが自然だと思います。
したがって、地下水の管理可能性を理論的前提とした上で、地下水を保護する必要がある場合には、条例などによって公水と定めることができると解すべきでしょう。
ともあれ、原則は、地下水に土地所有権の効力が及ぶと解して、原因者に直接、法的救済を求めていくのが救済のあり方の基本だと思います。管理主体に対して管理責任を問い、そして管理主体が原因者に対して求償するという迂回策を認めることは、管理主体である公共団体などに責任を負わせることにより、小さな行政の構築とは逆の方向に進むことにもなるでしょう。単純明快に、「被害者と原因者との間で直接やりなさい」とすれば足りると思うのです。
地下水は、地域によって流動のメカニズムが異なります。熊本地域は、水道水の水源をすべて地下水に頼っています。そのため、当地域における地下水の流動メカニズムに関する調査研究が積極的に進められ、今ではその仕組みが概ね解明されています。このような事情を背景に、熊本市は地下水保全条例で地下水を公水(市民共通の財産としての地下水)と規定しています。
一方で地下水が多すぎる、地下水過多による障害が発生しているところもあります。数年前には東京駅でも問題になりました。
今までは地下水採取をどう規制するかに重点が置かれてきましたが、適量を汲み上げたほうがよい地域もあるのです。したがって、その地域の地下水の流動メカニズムを調査し、地下水の適正な管理に関する条例などを制定することが重要であると思います。
地下水流動のメカニズムを把握する上で、重要な要素はリチャージ(涵養)が十分になされているかどうかです。充分なリチャージがなされていない場合には、地下水障害の影響が大きく及びますので、地下水の採取を制限する必要性が高まると考えられます。
熊本はリチャージに効果がある場所を重点的に湛水しています。それができるのは、地下水の流動が解明されているからです。東京でも雨水浸透枡の設置を推進している地域がありますが、地下水の流動が解明されている所は少ないように思います。どこの雨水浸透枡が役立っているのかわからないのが現状です。だから闇雲にやりましょうという話になってしまう。
水の値段
異常渇水時の水融通策として、アメリカ・カリフォルニア州の渇水銀行が有名です。州の水資源局の主導で、水利権のレンタル市場として比較的うまく運用されています。そこでの最も重大な理論的問題は、水の値段の問題です。「水はパブリックのものである」とすると、値段をつけることは許されないことになります。カリフォルニア州では水自体は無料です。水道料金が設定されているのは、取水施設や配水管などの建設や管理に経費がかかっているからです。水道施設の建設・管理費として料金が設定されているわけで、水自体はタダというのが原則です。この点は、日本も同じです。
ところが、その渇水銀行にとって重要な仕事の一つは、水に値段をつけることです。そこに、矛盾が生じます。この不整合を理論的に乗り越える必要があるでしょうが、難しい問題です。
異常渇水のときに水利転用を認めることは、緊急避難として許されるとは思いますが、水自体に値段をつけることを正当化できるかは疑問が残ります。私個人としては、水は人の生存に不可欠なものですから、値段をつけることには抵抗を感じます。
また、これまで水関連事業に対して膨大な投資をしてきていますから、財政事情が悪化したからといって、上下水道事業を私企業に丸投げすることには、賛同しかねます。これらの事業は我々の社会生活を支える基盤ですので慎重に考えないといけないと思うのです。
そうは言っても、世界的には水ビジネスの気運が高まっています。少なくとも上水道については、住民に安全な水を供給することが公共団体の重要な責務であることに変わりはありません。経済的弱者が安全な水を入手できないような社会構造にしないために、水道事業の根幹は公共団体が担うべきでしょう。そのうえで、サービスに関する部分をアウトソーシングすることは構わないと思います。この場合、公共団体の責任については、委託業務に関する監督義務の内容が問題となりますが、このような業務委託によってその責任が軽減するものではないと考えています。
(2010年4月22日)