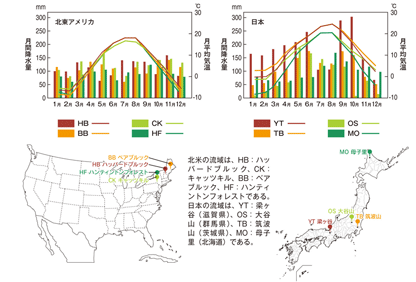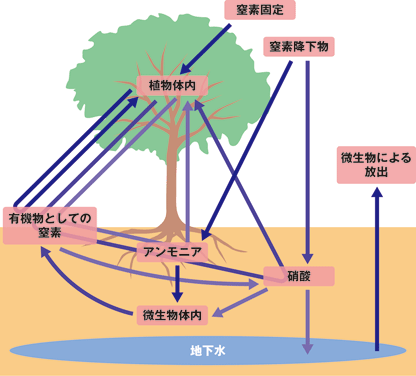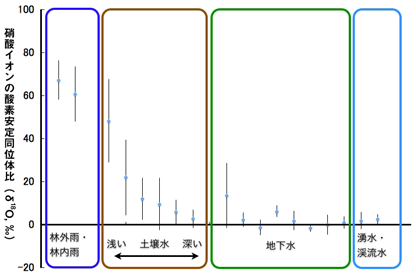水の風土記
森林の物質循環を水から解き明かす
〜「森林水文学」から分野を超える連携がカギ〜
森林水文学(しんりんすいもんがく)をご存じですか? これは、森林を巡る水のダイナミクスを追究する学問です。森の中では、多様な物質が水という〈乗りもの〉に乗って循環しています。森林水文学の成り立ちから森林の水と物質の循環の仕組みを解き明かす研究への道、現代社会が生み出した〈窒素飽和〉の問題点、さらに福島第一原発事故に伴う放射能汚染の研究などについて、大手信人さんにお聞きしました。
-

-
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授
大手 信人 おおて のぶひと -
1964年生まれ。奈良県出身。1987年3月京都大学農学部林学科卒業。1989年3月京都大学大学院農学研究科修士課程林学専攻修了。農学博士。京都大学農学部林学科助手、京都大学大学院農学研究科講師、助教授を経て、2006年10月東京大学大学院農学生命科学研究科助教授に就任。2007年4月から現職。森林の水と物質の循環の仕組みを解き明かす研究に取り組んでいる。
主な著書に、『エコロジー講座4 地球環境問題に挑む生態学』(共著/文一総合出版 2011)。
出発点としての森林水文学
水文学とは英語でhydrology。つまり水にかかわるあらゆる現象、事象について研究する分野で、水循環を対象とする地球科学の一つです。水の物理的な性質や循環をベースに、生きものがかかわる生物学的な水の動きや、社会科学的なことまでを範疇とした幅の広い学問です。学生には「水にかかわることはすべて水文学(すいもんがく)だよ」と説明しています。
今、私が研究しているのは森林生態系における物質の循環です。森林の中にあるさまざまな物質が、水に乗ってどのように循環しているのかを調べています。水は、たとえるならば「森林生態系という体をめぐる血液」のような存在。水は植物や動物や微生物の養分となる物質を運んでさまざまな部位を流れていき、生きものはそのエネルギーを使って生活している。つまり、森林生態系は水による物質循環によって維持され、成長しているのです。森林水文学は、この物質循環をコントロールする水の循環を明らかにする学問なのです。
学部時代には農学部林学科に籍を置いていましたが、4年生のときに水文学の授業を選んだら、とても面白かったのです。日本ではまだ学問体系が確立していなかった新しい分野ということもありましたし、父が砂防工学の研究者だったので「同じ道を進むのはイヤだな」という思いもありました。
森林の水文学は、水がどうやって森林の中を流れていて、どこに溜まるのか、そしてどこから蒸発するかといったことを調べます。土壌中の水の動きが重要になる局面もあります。例えば、雨は断続的にしか降らないのに川はなぜ絶えることなく流れているのでしょうか。それは水を貯留している土壌があるからです。やや専門的な話になりますが、地下水とは、土壌や岩盤の隙間がすべて水で満たされている「飽和状態」である地下の水のことを指します。しかし、土壌や岩盤の隙間に空気と水があって、水がゆっくり動いているような状態は水が「不飽和浸透」しているといいます。私は、この飽和している状態と不飽和の状態を研究して、森林の土壌がどのような物理的特性を持っているかを調べて学位を取りました。
大学院に進んでからは、物質循環を研究するようになりました。すると前述した土壌中の水理学の知識も必要ですし、植物の生理学の知識も必要です。植物や微生物の養分利用のことを考えるならば、生態学も学ばなければいけません。このように、森林の物質循環を研究するには水文学に加えなければならない枝葉がたくさんあるのです。
研究者としてトラディショナルなメソドロジー(方法論)を追求していくタイプではない私には、あらゆることが研究対象になる森林の物質循環についての研究は性に合っていたのでしょう。
日本の森林は抜群に面白い
なにか特定の生物を扱うのではなく、私の興味は「森林生態系というシステムがどう動いていくのか」にあります。物質の動的な視点から生態系を研究する学問を生態系生態学といいますが、日本の生態学の世界では少数派ですね。必然的に他の分野の研究者と一緒に仕事をすることになりますが、それはとても面白いことです。
森林の動態をマクロな視点からとらえようとする研究は、アメリカやヨーロッパが先行していますが、我々の住んでいる東アジアの環境とは大きく異なっています。まず気候が違います。欧米で研究が進められている地域は、同じ温帯ですが西岸海洋性気候(注1)が多く、雨は年中同じように降ります。ところが、我々の住んでいる地域はモンスーン気候(注2)で、6〜9月に雨が多く降りますね。その差は植物や水の動き方にとても大きな影響を与えています。
注1 西岸海洋性気候
ケッペンの気候区分における気候区の一つで、温帯に属する。諸条件があるが、年間の降雨は平均しており、気温の年較差が少ないという特徴がある。
注2 モンスーン気候
同じくケッペンの気候区分における気候区の一つ。季節によって風の吹く方角(卓越風向)が変化するものをモンスーンと呼ぶ。この風の影響で、降雨量が季節的に大きく変動するほか、気温に関しては夏に高温で冬は比較的寒冷と年較差が大きく、四季の別が非常に明確という特徴がある。
夏は生きものの活性が高いので、物質の循環も盛んです。日本では物質のよく循環する時期に雨がたくさん降るので、いろいろものが流れるのです。例えば、夏にはカビやバクテリアなどの微生物が有機物を分解して養分をたくさんつくりますが、雨も多く降るので流れる量も多くなります。日本では養分が流れやすいために、たくさんつくらないといけないのではないか。つまり、バクテリアが養分をつくる総量は日本のほうが多いかもしれないのです。
それに対して欧米は夏でも雨がそれほど降らないために、土壌がやや乾燥気味になって養分が効率よく保持されます。そのため、植物と土壌との間で養分のやり取りが東アジアのモンスーン気候下よりも効率よく行なわれているのではないかと考えられるのです。
とにかく日本の森林は、抜群に面白い。研究者として「日本に生まれてよかった!」と思えるくらいです。
森林が地球上に占める割合はさほど多くないのですが、モンスーンがある東アジアは人口がかなり多い。論文の数では欧米に負けているかもしれないけれど、私たちは「欧米の研究だけではユニバーサルには語れないよ」と言える立場にある。われわれのフィールドでのデータをつき合わせて考えることで、もうワンランク上の普遍的な理論を提示することができると考えています。
森林と水をマクロの視点で
かつて私は、マクロな視点から日本と欧米の違いを比較したことがあります。1990年代の半ば、酸性雨の問題に関心が高かったこの時期に、当時の環境庁が酸性雨モニタリングを実施して湖沼や河川の水に対する影響を調べていました。
ヨーロッパや北東アメリカは酸性雨による影響度が高かったのですが、日本はそれほどでもありませんでした。結論は「日本にも酸性雨は降っているけれど、湖沼や河川の水は酸性になっていない」というものでした。その理由は、日本の環境にありました。なぜ日本は欧米に比べて酸性雨が川の水に影響を与えないのでしょうか?
世界中のデータを集めて、川の水に流出している物質を調べると、日本はヨーロッパとは違うことがわかりました。
酸性雨の酸はマイナスイオンになりやすく、pHを低下させます。ところが日本の川の水は、カルシウムやマグネシウム、ナトリウムといったプラスイオンの濃度が高いのです。プラスイオンが多いので、酸性雨によって硝酸や硫酸などのpHを低下させやすい物質が入ってきても効率よく中和できるというメカニズムがあるから、日本の湖沼や河川の水は、ヨーロッパや北米に比べて酸性になっていなかったのです。
日本の土壌や基岩には、風化が進みやすいという性質があります。風化と聞くと岩石が風雨にさらされてボロボロになるというイメージがありますが、このときに、岩石の表面では〈化学的な風化〉も生じています。実は土壌の中でも〈化学的な風化〉は進行しています。鉱物は酸の影響を受けて溶けるのです。
日本は火山の国なので、基岩そのものはヨーロッパやアメリカ大陸に比べて圧倒的にフレッシュです。ご存じのように日本列島には今でも火山活動があって少しずつ隆起しながら、同時に浸食されてもいます。いわば常にフレッシュな土壌が供給される環境なのです。
その上、森林での斜面の崩壊もしばしば起きています。人間の寿命は100年もありませんので土壌の更新は実感としてわかりにくいかもしれませんが、日本の森林はアメリカ大陸やスカンジナビアの平坦な森に比べて圧倒的に崩壊や浸食が多いのです。崩壊が起きると、土壌は必然的に更新されます。
土壌そのものがカルシウムなどのプラスイオンを多く生み出せる。その上、雨が多くて気温も高い。風化が進みやすく、こうしたミネラルをたくさん出しやすい立地条件なので日本は酸性雨に強いんですね。こういうことは地質学者からすると当たり前のことです。
このようにマクロな視点で見るならば、地質、気候、森林の役割なども網羅して研究しなければなりません。だから私は、さまざまな分野の研究者と一緒に仕事をすることが多いのです。
〈安定同位体〉で植物の水使用効率を検証
少し遡りますが、マクロな視点に通じる印象的なフィールドワークがあります。それは、1990年代初頭に携わった中国の砂漠での研究です。
緑化をテーマとして、内モンゴル自治区の半乾燥地帯に行きました。日本に比べたら降水量は約6分の1、年間300mmくらいです。
その地域にはもともと在来性の木本植物(もくほんしょくぶつ 種子植物の内、地上部が多年にわたって繰り返し開花・結実し、茎は木化し肥大成長するもの)による自然植生があったのですが、農地と放牧地の開発のために剥いでしまったから砂漠化したといわれていました。
課題は二つ。「砂漠化のメカニズムを調べること」と「生態系修復の方法を導き出すこと」。ネイティブな植物と緑化のために持ち込む植物が、水をどのように利用するのかを調べた上で、緑化に適した植物を選択したり、密度を管理したりする必要があるのです。
実際には、調査のためとはいえ、ずっと現地に張りついてはいられません。そこで用いたのが〈安定同位体〉です。調査時に入手した土壌や植物のサンプルにおける、水の安定同位体と炭素の安定同位体を調べたのです。
やや専門的な話になりますが、同位体(注3)には〈放射性同位体〉と〈安定同位体〉の2種類が存在します。時間とともに崩壊する放射性同位体とは異なり、安定同位体は一定の割合をもって自然界に安定的に存在します。安定同位体を測定することで、それを含む化合物の生成過程や物質の起源を調べることができます。例えば、植物の中に存在する炭素の安定同位体を調べれば、その植物が光合成をして炭素を固定するときにどれくらいの水を使うのかを知ることができます。
注3 同位体
原子番号(陽子数)が同じで、質量数(陽子と中性子の数の和)が異なる物質のこと。同位体には、放射能を発して中性子を放つ不安定な放射性同位体と、常に安定な安定同位体とがある。
放射性同位体は時間とともに放射性崩壊を起こすが、安定同位体は自然界で一定の割合を持って安定に存在する。
その地域のネイティブの植物を調べると、水の利用効率に秀でた植物と、水の利用効率は悪いけれど水を使う生産のための期間を絞って「雨が降る3カ月だけ頑張って生産して、あとは種をつくって寝てしまう」という植物がありました。
こんなことも生態学の研究者にとっては当たり前のことかもしれませんが、私にはとても面白く感じました。それぞれが鮮やかな対比を持って生きていることがわかり、勉強になりました。
生態系の中で循環する〈窒素〉
2000年代初頭、プリンストン大学の研究者によって、硝酸イオン(NO3-)の安定同位体比の測定方法が大きく進歩しました。そこで、2003年(平成15)に測定方法を習うためにアメリカへ渡りました。なぜなら、そのころから森林の水による物質循環の中で、特に窒素(N)に着目していたからです。
先程、「水は森林生態系という体をめぐる血液のような存在」とお話ししましたが、水という血液によって運ばれる養分の中で、窒素は生きものにとってもっとも重要な養分の一つなのです。
細胞における生命維持と細胞増殖のための化学反応を〈生化学反応〉といいます。その多くは酵素という物質の働きによって起こるものですが、酵素の多くはたんぱく質でできていて、そのたんぱく質をつくるのに欠かせない元素が窒素。ですから生きものすべてが窒素を必要としています。
ところが、生きものが使えるような形の化合物としての窒素は、陸上の自然な生態系では不足している状態だといわれています。
窒素は身の回りにたくさんある元素で、窒素ガス(N2)は大気の80%を占めているほど。ただし窒素ガスそのものは、生きものにとってまったく使えないものなのです。Nを1個にして水素と結合させてアンモニア(NH3)にすると養分になりますが、自然の状態で窒素ガスをアンモニアにするには、2個の窒素をバクテリアが壊して1個にするしかありません。窒素固定菌という、バクテリアにしかできないことなのです。
いったん取り込んだバイオアベイラブル(生物学的に利用可能)な窒素は、取り逃がしたくない。だから狭い地域で循環させて、ローカルに再利用するという現在のシステムが長い年月をかけてできあがりました。野菜や果物を育てるとき、化学肥料を使うと大きく育ちますが、それは自然界では窒素不足の状態が常だからです。
ところが産業革命以前に比べて、現代では、人為的なやり方での窒素の循環が急激に変化しました。バクテリアによる窒素固定以外に、生きものに利用可能な窒素が生物圏にたくさん供給されるようになったのです。最も多いのは化学肥料の生成。そしてもう一つの要因が化石燃料の燃焼です。
1910年代に大気中の窒素ガスと水素を使ってアンモニアを合成するハーバー・ボッシュ法が開発されました。これによって化学肥料がつくられ、農業生産は増えたものの、大気中に放出されるアンモニアも増大しました。
アンモニアや硝酸などの窒素化合物が大気中に増えることで、地球上のいろいろな生態系にどんな影響があるのかは、現在もさまざまな側面から研究が進められていますが、例えば、窒素と酸素からなるN2Oなどの窒素酸化物の中には二酸化炭素の数十倍もの温室効果がある気体もあります。そのため、養分の循環が大きく変わるばかりでなく、いろいろな間接的な問題が生じるかもしれないと危惧されています。
窒素の起源から湖水の汚染源を特定
硝酸の安定同位体比の測定方法を習得してアメリカから戻り、2004年(平成16)から4年間かけて、琵琶湖の流入河川の窒素について調べました。これは京都大学のプロジェクトで、安定同位体比の測定手法を用いて水と生きものに関する環境を評価する仕事でした。
私は琵琶湖に注ぐ32の河川を選び、流入する硝酸の素性を調査。琵琶湖の流域全体を見るという大きなスケールの仕事ができました。
硝酸イオン(NO3-)という溶存物質は、養分として極めて重要です。硝酸イオンは窒素と酸素が結合しているので窒素と酸素の安定同位体比を測定すると、その硝酸イオンを誰がつくったか、どこからきたのかといった情報を得ることができます。それを追いかけるための指標という意味で、専門用語でトレーサー(追跡子)といいますが、硝酸イオンの安定同位体比を調べると、それが雨とともに降ってきたものなのか、それとも土壌で有機物が分解されて生成されたものなのかが分離できます。森林からのナチュラルなもの、人間が出す下水、生活排水、肥料などを調べ、その割合を把握しました。
私たちが窒素循環を研究するのは、生態系の仕組みを理解することに加えて、琵琶湖に流入する窒素を調べたように汚染物質としての窒素、富栄養化の原因としての窒素を把握したかったからです。窒素は環境科学的にも、生態学的にも重要な物質なのです。
私たちも窒素循環の中に生きています。食べものから窒素を取り込み、不要な分は排泄しますから、下水には窒素が含まれます。下水処理によって窒素が水系に流れないようにしているのは、過剰な窒素の供給によって富栄養化が進み、特定の藻類が異常発生し、枯死・分解が進むことで溶存酸素が不足して水生の生態系に悪影響を及ぼすことがあるからです。
また、やっかいなのは窒素が酸性雨などで大気中から森林に大量に入ってきた場合、渓流や河川に流出する窒素は増加することがいろいろな地域で報告されていますが、使い切れない余分な窒素が、森林を素通りして流れていくわけではないのです。
実は、外から供給された窒素は素通りするメカニズムにはなっていなくて、微生物がいったん土壌中に取り込んでいるようなのです。
余剰であっても、とにかく窒素をいったん取り込むことで、土壌中の微生物にどのような影響を与えているのか。過剰な窒素の供給の結果、渓流や河川に流れ出る窒素が増える〈窒素飽和〉と呼ばれる現象は、この先、より重要な問題になるでしょう。
放射性物質の拡散と食物網
東日本大震災で発生した福島第一原子力発電所の事故によって、放射性物質が大量に大気中に放出され、さまざまな場所に降り積もりました。2012年(平成24)4月から福島県のある場所に森林サイトを設定して、森林にもたらされた放射性物質の動態を調べています。事故の直後から、文部科学省と農林水産省による森林におけるセシウムを含む放射性物質の動態の研究は続けられています。しかし、有効な対策を見いだすためには、こうした行政主導の研究だけでなく、可能なかぎり多様なデータを取って情報を整理しておくことが必要です。私たち研究者がアイディアを出し合って調査するのは、そういう意味があります。
「放射性物質は生きものの間でどのように移っていくか」については、昨年(2011年)はあまり調査されてきませんでした。樹木はもちろん、生態系における生物の食物網(複数の食物連鎖が重なり合った生きもの間の喰う喰われるの関係を表わす)で放射性物質がどう伝わって、どこで蓄積されるのかを調べたいのです。
福島の森林サイトでは、森林の調査はもちろんですが、生きものの専門家にも参加してもらってサンプリングをしながら、定期的に放射性物質の濃度を測っています。
「野生の生きもののことなので関係ないよ」と思う人がいるかもしれませんが、生態系のあらゆるダイナミクスの中で放射性物質がどう動いていくのかは、必ず調べておく必要があると考えています。
スタートして半年ほど経ちましたが、今は森林から出ていく放射性物質をおさえることと、生態系内で食物網を介して拡散していくパスウェイを見ています。
水との関連でいえば、川に拡散していく放射性物質を見るために、①水に溶存しているもの、②(物質として)浮いているもの、③水生昆虫、魚などの生きもの、をそれぞれ調べています。
①の溶存物質については、2011年度(平成23)には、森林に近い渓流ではきちんと測定されていません。調査自体にかなり手間がかかるためです。
また、放射性物質が稲に達するメカニズムも特定したいと思います。山際の水田では森林を通ってきた水を用水として使いますから、放射性物質が①のように水に溶存しているのか、それとも②のように浮いているのかで対策がまるで変わってくるからです。仮にぷかぷか浮いているのであれば、取水口などにフィルターをかければいいのかもしれません。
生きものへのセシウムの移行を調べるときも、安定同位体比の測定技術を用います。
食物連鎖の階層は、一番下が一次生産者で、一次消費者、二次消費者となり、最後はトップ・プレデターといわれる捕食者ですが、その段階ごとに窒素の安定同位体比が上がっていく性質があります。ですから、サンプルを採ってきて窒素の安定同位体を測定し、セシウムの濃度を測定すると、セシウムが食物連鎖のどの段階まで到達しているかが評価できます。
昆虫やクモ、鳥といった陸上の生きものは到達レベルにばらつきがありますが、水生生物に関しては、既に捕食者にまで到達しています。また、落ち葉から始まる食物網(腐食連鎖)も捕食者まで到達しています。陸上では落ち葉を食べるミミズのセシウム濃度が高いため、そのミミズを食する爬虫類は高く、同様にイノシシのセシウム濃度が高いという報告もあります。川底の落ち葉を食べる水生昆虫を魚が食べ、さらに魚を食べる鳥がいるので、こちらも高次まで移行することが考えられます。
生きている植物を食べることから始まる食物連鎖を生食(せいしょく)連鎖といいますが、これではまだ高次に達していないので、これからどうなるのか調査していきます。
さまざまな領域の知恵を結集して
私が取り組んでいる森林における物質循環に関する研究では、水の流れや貯留といった物理的な性質に生きものの営みのベースになる養分の動態が影響を受けているという見方を念頭に置いています。こうした仕事には、さまざまな専門分野の知恵が必要で、一人の力だけでは太刀打ちできません。
私が「渓流の水の性質がどう決まるのか」を研究していた大学院生のころ、隣の研究室に植物と土壌の間の窒素循環の研究していた徳地直子さんがいました。今は京都大学フィールド科学教育研究センター森林生物圏部門の教授となっている彼女の知識が必要だったので、声をかけて一緒に仕事をするようになりました。
彼女は養分の動態を中心に森林全体をシステムとしてとらえていますし、私は水を中心に据えています。また、生きものの動態を軸に研究している人もいます。それぞれのプロセスにくわしい研究者と一緒に仕事をすることで、私は水を物質の乗りものとしてとらえて「森林の水と物質の循環の仕組み」を解き明かしていきたいのです。
ただし、研究者の生き方としては一つのことをじっくり研究していくほうがメジャーですし、効率もよいと思います。
自分が好きなことを研究するには、いろいろな人と組まなければできません。だから、私は分野の違う研究者と組んでいるのです。例えば、放射性物質の研究は世の中のため人のためになる、重要な研究だと思いますが、私個人は、それだけの義務感で福島に行っているのではありません。基本的には自分が知りたいこと、自然の生態系での放射性物質の動態の仕組みを知りたいという欲求があります。そのために、多様な分野の人に手伝ってもらうのです。
私のようなやり方をしている研究者は「それじゃ、だめだよ」と言われることもあります。実際に干されて、研究費がつかなかった時期もありました。
しかし、最近の研究ファンドプロジェクトを見ると、さまざまな領域の学者や技術者が協力し合うインターディシプリナリー(Interdisciplinary学際性)を求められるようになりました。いろいろな分野の研究者が集まって大きなプロジェクトに取り組んでいるのです。
ようやく少し風向きが変わってきたかなと感じています。
(2012年10月23日)