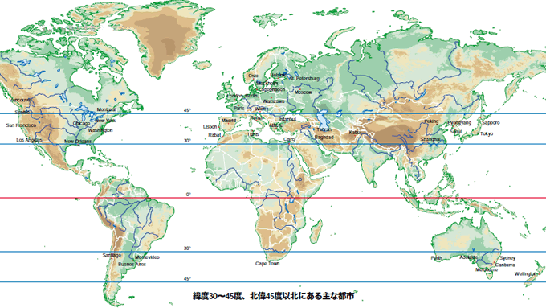機関誌『水の文化』21号
高温多湿でこそ発揮される日本の衣食住文化
湿気と仲良くするライフスタイル

高温多湿でこそ発揮される日本の衣食住文化 湿気と仲良くするライフスタイル
-

-
民俗学者・旅の文化研究所所長
神崎 宣武 (かんざき のりたけ)さん -
1944年生まれ。 主な著書に『祭りの食文化』(角川学芸出版、2005)、『江戸の旅文化』(岩波書店、2004)、『江戸に学ぶ「おとな」の粋』(講談社、2003)、『おみやげ−贈答と旅の日本文化』(青弓社、1997)、『湿気の日本文化』(日本経済新聞社、1992)、『吉備高原の神と人』(中央公論新社、1983)他。
湿気には日本独自の意味がある
実は私が湿気に興味を持つようになったのは、海外に出てからのことです。日本が位置する北緯30〜45度圏内のところでは、日本の夏と同じように気温が30度を超えます。しかし、日本で感じるような蒸し暑さは感じず、その対比で日本は湿気が強いんだなと意識するようになりました。
湿気という言葉は、英語にも中国語にもなく、翻訳できません。江戸時代には「湿毒(しつどく)」という言葉があって、過ぎた湿気は体に悪いということを表しました。この場合、湿気に含まれる意味は、湿度だけでなく、温度だけでもない。ヨーロッパの主要観光地や大都市は、もっと緯度の高いところに位置しますから、日本の夏の湿気を理解できませんし、日本に来ても耐え難いでしょう。
日本の場合、雨がよく降ることも湿気を増大させる一因です。日本の山はどこまでいっても緑に覆われています。コンクリートの割れ目からはしょっちゅう雑草が芽を出します。土の保水量も多いし、国土の60%強が森林面積というのは、同緯度圏ではなかなかありません。このためか、日本人に山を描かせると、まず間違いなく緑色に塗ります。しかし、海外からの留学生、例えば中国人に山を描いてもらうと稜線に岩松を描きます。つまり山水画に描かれている景色は、その中国固有の風土に根差したものだということがわかります。
中国はとても広い国で、地域差があるので一概に比べられませんが、韓国は距離が近いのに、湿度は日本より15%ぐらい低い。台風がやってきて雨が3日で1000mmも降る日本とは異なります。これは、韓国の南に日本があって、雨雲を塞ぐ屏風になっているからです。
湿気対応という異文化ギャップ
海外から日本にやって来た人は、初めて経験する湿気に大変苦労します。
高温多湿で寝ているときに汗をかくので、日本人は晴れた日に外に布団を乾します。ところが、敷き布団、掛け布団を使う点は日本と同じでも、韓国人にとって布団は下着と同じ感覚があるので、外に干すことは理解し難いといいます。韓国の留学生は、布団を外に乾すという日本の習慣に、まずカルチャーショックを受けるわけです。実際に韓国を旅行して、布団を干している光景を私は見たことがありません。
さらに、風呂にみんなで入る大衆浴もショックだそうです。ですから、韓国留学生はみんなが寝静まった夜になって終い湯にこっそり入ったり、シャワーだけで済ませたりという生活を、初めはおくるわけです。
ところが、梅雨を迎え、温度25度、湿度70%を超えると、そうは言っていられなくなります。他人が裸で一緒にいようがいまいが、外から帰ってきたらまず風呂に入り汗を流さないと食事もしたくない。朝、日が差していれば、「布団を干さなくては」と思ってしまう。梅雨に至って、初めて日本の流儀に習う気になるのです。これが多くの留学生や日本滞在者が経験するプロセスです。
プロ野球で海外から選手を呼ぶときは、最近では日本特有の文化について事前説明を行なうそうです。例を挙げれば、移動時にはネクタイを締めるとか、練習時間が長いこととか。それに加えて、梅雨への対策のレクチャーが欠かせないそうです。昔はこの説明をしなかったせいか、シーズン途中で帰国してしまう選手が続出して、プライド過剰のあまりのホームシック原因だろうと言われていました。しかし、笑い話のようですが、帰国してしまう原因の一つには水虫の発生があったようです。
遠い日本にやってきて、梅雨時の長時間練習の結果、水虫を患う。外人プレイヤーが少なく、仲間内の情報交換もできないため、水虫になると本当に驚いたそうです。女の人は理解できないでしょうが、水虫が出るときは、男は足だけでなくいろいろなところに症状が出ます。これは、大げさに言うと「民族としての初体験」なんです。こうなると、本人は「悪い病気にかかったのではないか」と悩んで野球どころではなくなり、梅雨時に成績が落ち、夏に帰国するというケースが多かったそうです。
われわれは水虫と呼びますが、これは湿気の少ない韓国でもヨーロッパでもアメリカにも存在します。軍靴病(ぐんかびょう)といわれ、兵役につくと罹る病気として知られています。汗をかいた足が革靴に包まれて長時間たつと、指の間が真菌に侵されて水虫にかかります。風通しのいい日本の下駄や草履は、この病気を防ぐための知恵ということがよくわかります。
外国人に奇異な目で見られ、説明しにくい、あるいは言葉にしにくいことが文化の根幹だとすれば、湿気対応はまさしく日本文化の一つと言っていいと思います。
夏を旨とする日本住宅
現代の住宅は、エアコンで湿気調整をしています。そのエアコンが無くなるとどうなるか。とても、いまの住宅の造りでは湿気を調整することができず、暮らせません。
もともと、日本の木造民家の造りは、床下と屋根裏を広くあけてあり、障子を開け放つと相当な空気が通ります。通気性をよくすることが、日本の家屋の工夫なのです。冬は少々不自由でも、夏向きに家を造らなくてはならないと兼好法師が記したことは、この工夫を言っているのです。
冬は寒いから火を焚きます。囲炉裏やこたつ、火鉢など、いくつか暖房器具がありますが、大々的に発達しなかったのは、ヨーロッパ、北米に比べて東北日本を除けば冬でもそれほど寒くならないから、重ね着でしのげたのです。西日本では冬の温度がマイナスになる日はほとんどありません。木造建築ですから火事のリスクのある暖房法は発達しませんでした。
このように考えると、私は、十二単(ひとえ)をもう一度見直さねばならないと思います。気象研究者の話では、平安時代というのは、約600年周期でやってくる寒冷期の時期だそうです。江戸時代の天明の飢饉の頃も寒冷期ですね。絵巻物で見ると、平安時代から鎌倉時代の住宅は見るからに寒いそうですよ。襖も無く、板戸だけで障子戸もない。寒さを防ぐ工夫をするわけでもなく、着ぶくれて寝ている姿が描かれています。しかし、そのように冬が不便でも、夏に対して備えをしなくてはならなかった。
このため、大陸や半島からいろいろな文化が流入したにもかかわらず、オンドルという、あれほど便利な暖房装置が日本には根付きませんでした。それは床下をふさいだら、日本の場合、家屋の耐久年数がもたないからです。湿気が強い地域に建つ木造建築は、通気口をふさいだら木が腐って何年ももちません。
日本では基本的には湿気が強い季節、それがたとえ梅雨時だけでも、冬への備えをある程度犠牲にしても、湿気への対策をしないと、家の造りがもたないのです。
ステテコは外出着だった
では、衣食住の衣はどうでしょうか。着物も江戸時代になると、三幅巻(みはばまき)のように帯で締めるようになってきますが、わかりやすく言うと、かつては浴衣、甚兵衛のような、ゆったりとした着付けが一般的でした。さらに、袴もスカート状です。これらも湿気対策以外の何ものでもありません。
風を通す通気口を広くとり、襟合わせの部分を下げて、首から風をおくるスタイルが生まれます。また、筒袖は仕事着として必要ですが、普段着では、八つ口といって、脇の所を開けた着物が出てきます。脇が開いた着物など、世界中探しても他には見つかりません。これはまさに湿度対策でしょう。襟口を開けて、袖口を開け、裾を開け、それでも足りなくて八つ口を開けた。
一方、明治時代になると、体を締め付ける洋装が入ってきました。背広上下はその典型です。
時代が下って高度成長期になり、ビルが建ち、エアコンが完備されると、背広姿でもよい。でも、エアコンが入る前はそうもいきません。ですから、昭和30年代までは、役場や国鉄では開襟シャツが公用着でしたよ。開襟シャツというのは和製洋服です。洋服が日本に入り、湿気対応のために襟が開き、日本化したわけです。
日本化のもう一つとして、ダボシャツとステテコが生まれます。今では下着の感覚ですが、以前は両方とも外出着でした。フーテンの寅さんもそうでしょう。東京でも下町では、ダボシャツ、ステテコでカンカン帽かぶった男たちが歩いていたものです。豆腐屋さんたちもそうでしたね。
いわば気候に合わせて洋服の日本化が通用していた時代があったのですが、オフィスビルが建つようになりエアコンが入ると、それらが見られなくなります。背広とネクタイでいても我慢できる人工的な環境が調ったからです。
さらに、決定的だったことは、海外旅行の普及です。日本のおじさんたちは、近所を歩く感覚でホテルの中をステテコで歩き回り、それが世界の基準ではうとましいし、目障りと感じられた。旅行会社すべてが「ホテルの廊下をステテコで歩かないこと」と説明文に一項を入れました。そして、ステテコは下着と見なされるようになります。これも高度成長期以降の出来事です。
いま、エアコンを無くし、海外旅行を無くしたら、ステテコ、ダボシャツ姿や開襟シャツ姿に戻るかもしれませんね。
たくあんはお新香ではない
湿気が食品にプラスになる領域というのは、やはり発酵品でしょう。ただ、非常にデリケートな発酵菌を利用して、しかも保存性の高い発酵食品をつくろうとすると、これは、やはり夏には無理です。そこで、発酵食品づくりは冬に集中し、酒造りは寒造りになるし、冬に漬け物が多くなります。
韓国にもキムチが発達しているように、世界の中では、日本と韓国は、野菜の漬け物の一大文化圏を成しています。つくった白菜の半分近くを漬け物にするのは、韓国か日本ぐらいのものです。
ところが、両国で違う点が一つある。それは、夏の高温多湿を利用してつくる漬け物が日本にはあるということです。浅漬けのことです。長くはもたないけれど、一晩で漬け物ができる。これは湿気がないと無理なんですね。仮に韓国で日本の浅漬けをつくろうと思ったら、極端に言えば、火鉢でお湯を沸かして閉めきった部屋で漬けなくてはならない。それくらい違います。
漬け物を「香のもの」と呼びますが、冬と夏で漬け物を表す言葉が違います。冬の漬け物は時間をかけて、熟成させます。外気温も低いので日持ちもします。これを「古香(こうこ)」といいます。たくあんや粕漬けの類です。
一方、夏の浅漬けは、一晩か、3日以内で漬けて、その日の内に食べてしまう。これが「新香(しんこ)」です。新香というのは、湿気の多い夏を上手に利用した、胡瓜や茄子などの夏野菜の漬け物です。温度が20度を越え、湿度が60%を越えることが好条件です。
日本人でも、古香と新香の使い分けが忘れらつつあります。たくあんを出して「お新香です」と平気で言う店もあります。しかし、30年ばかり前には古香という言葉が日常で使われていました。
高温多湿だと、食べ物の保存には敏感になります。食の保存という意味では、竹籠の発達が大きく貢献しました。
夏の食料を竹籠に入れ、通気性のよい所にぶら下げる。いまの冷蔵庫に代替されるようなものです。残ったご飯や、焼き魚なども入れました。竹籠は、蠅や蚊を通しませんから虫避けにもなりました。やがて竹籠は網に変わり、食卓の残り物の上に蠅張(はえちょう)をかぶせた時代もありました。
竹籠や蠅張には、中に濡れ布巾を敷いて使いました。そうすると気化熱で中の温度も下がるからです。夜中になると気温も下がるので、一晩くらいの保存ならそれで済んでしまうのです。田舎だと、流れ水の上に竹籠を置いてもいたそうです。
風呂好きは湿気対応か
日本人の風呂好きは有名です。風呂の歴史の最初は光明皇后(こうみょうこうごう)がつくった悲田院(ひでんいん)あたりでしょうか。大きい釜で湯を焚いて、木製の樋で部屋の中に湯を引き、水で薄めて体を洗いました。湯を溜めるようになったのは、江戸時代の銭湯からです。悲田院は明らかに病気治療を目的にした施設です。治療のためには、体をきれいに洗わなくてはなりませんでした。汗、ほこり、垢を流すには、水よりもお湯のほうが効果があります。風呂の出現で、皮膚病は大幅に後退しますが、それでもまだ多かった。
明治時代の初めに、イギリス人外交官の妻としてやって来たイザベラ・バードが東日本を一周しています。彼女が一番びっくりしているのは、皮膚病の多さです。特に東北地方では風呂が充分普及していないので、湿気が高い夏は皮膚病を止めようがありませんでした。裸に近い生活をしていても、皮膚病にかかりました。
ところで、岩風呂を利用していた土地もあります。つまり蒸し風呂ですが、その系統は漁村部に多く見られます。漁村では真水を得にくい上に、山の所有が少ないため薪の確保も難しかったのです。そこで、浜に打ち上げられた海草を岩穴に敷いて火を焚き、海水を蒸気にすることで蒸気浴をしました。もちろん、洗い水は確保しなくてはなりませんが。瀬戸内海に何カ所か残っています。『厳島図会』などを見ると、宮島の名物にもなっています。
湿気で育まれた文化を守る
現代生活を便利にしているのは、エアコンの存在です。これが自然とのつきあい方を狭めているため、生活の場での湿気とのつきあい方も見えにくくなっています。
とはいえ、湿気という要素は不快な気象条件であることは確かですから、湿気対応に人々が快適性を求めるのは当然です。日本と同様に高温多湿な東南アジアの大都市では、冷房を日本よりもずっと利かせているために寒いほどです。こうした現象は、湿気に対して過剰に反応しているようにも思えます。我々は、そこまではしていませんが、今後快適さを一層追求していくのか、それとも湿気対応の知恵を暮らしの中で見えるようにしていくのかが、問われていくでしょう。
日本では衣食住のほとんどが、高温多湿の夏場対策に重点を置いて発達をみました。湿気の高さは、住みにくい条件の一つです。しかし、日本列島に住む以上、回避するわけにはいきません。今の言葉で言えば、共生するという生活スタイルはこうした風土からつくり上げられてきました。ところが、現代の日本人は、そこで根づいた湿気とつきあう生活の知恵も忘れかけています。
夏の蒸し暑さをしのぐために、冬は多少寒くても我慢して暮らすということは、日本人が事象をうまくつなげて1年の中で生きる術を培ってきた結果ということもできます。言うなれば、「つなぐ能力」を育んできたのが、日本の湿気文化でもあるのです。最近社会問題になっている「キレる」子供の増加には、誰もが困ったことだと思っているでしょう。私は「キレる」ことは、「つながらない」ことだと考えています。本来すべての事象をうまくつなげて生きてきたのに、つなぐ努力しなくなっていることが原因のような気がします。その背景には、子供が自然と共生することを、家庭や社会が断ち切っている現状もあります。
生活の近代化は、人間と自然の共生を遠ざける方向で進められてきたために、子供の世界だけでなく、学問の研究分野、日常生活の中でも「分断」が見られます。例えばホテルではエアコンを止めて窓を開け風を通そうとしても、安全の保証がなければ開けることもできません。安心して窓を開けて自然と共生できる生活を取り戻すためには、湿気の文化に今一度学ぶべきことがたくさんあるのかもしれません。