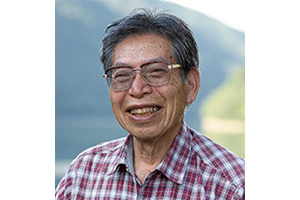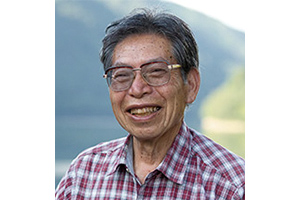機関誌『水の文化』27号
暮らしの中の水とのつきあい方と心を探った
水にかかわる生活意識調査13年
-
編集部
1995年(平成7)に、ミツカン水の文化センターが 「水にかかわる生活意識調査」を始めて13年が経った。東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)、大阪圏(大阪府 京都府 兵庫県)、中京圏(愛知県、三重県、岐阜県)に住む20歳から69歳までの男女計700人を対象に、年1回行なっているアンケート調査だ。当センターの活動開始に先駆けて、今まであまり注目されることがなかった「日常生活における水とのかかわり」について、改めて調べてみようと考えたのがきっかけだ。
実態を尋ねる項目もあるが、普段何気なく(無意識に)行なっている行為を思い起こして回答してもらう「意識調査」が主な目的である。
三大都市圏の居住者を対象としているが、日本全国どこに行っても都市型のライフスタイルが浸透し、上下水道の普及率も上がっていることを考えると、このアンケートから得られる回答は、ほぼ「今の日本の水意識」を表しているといっていいだろう。
こういった調査が継続して行なわれている例はほとんどないので、ホームページ上でも公開されているデータを使って、解説記事に引用される例も増えている。こうした記事をきっかけに、水に対する関心が高まることは、当センターとしても大変うれしいことだ。
その13年間のデータを通しで改めて見直し、世相を反映した結果から当時の出来事を思い返してみたり、13年間不動の地位にある結果に水への深層心理を見出したりできるのではないか、と考えた。
質問項目の中にも、変わったものと変わらないものがある。それは世相と連動させて旬な項目を提供しよう考えてきたこと、また当センターが新しい視点を見つけたこととも関係がある。
今号では、アンケート結果の変化を比較して、それらをもとにさまざまな立場の方にコメントをいただこうと思う。いろいろな角度から物事を見ることで、自分と違った視点が発見できたら面白い。
まずは、本論に入る前の準備体操として「水にかかわる生活意識調査」13年ダイジェストから始めよう。
地球の将来は20歳代男性が握っている
「地球温暖化をストップさせるために、いくらまでなら払いますか?」というのは、2007年から新たに加わった質問。金額を書いてもらったところ、その平均額は約2048円という想像以上の高額になった。
さて、詳細な集計データを見ていくと1万円以上と答えた人が5.9%もいる。その多くは、20歳代男性。金銭感覚の問題もあるだろうから、手放しで喜べないかもしれないが、地球温暖化への関心が高いことの表れと読むことはできる。
逆に0円と答えた人の割合も5.9%で、これも20歳代男性が最多。地球環境の将来は、どうやら20歳代男性の肩にかかっているようだ。
「おいしくない」は減った
私たちの暮らしの中で、大切な存在である水道水。その水道水に関する質問は、1995年開始当初から続けられている。
水道水につけられた10点満点の点数は、5.7点から7.1点に大幅アップ。開始当初は5.0点という最低得点だった大阪圏は、2007年には7.1点をマークし、7.5点をつけた中京圏に迫る勢いだ。同時に、水道水への不満のトップだった「おいしくない」という評価も、ぐっと減った。
ところが、飲料水にミネラルウォーターを選ぶという人は、8.9%(2002年)から13.8%(2007年)とわずかながら増え続けているし、飲用に使う水は浄水器を通した水とミネラルウォーターを合わせると58.9%にも上る(2007年)。
「おいしくない、という不満は減った。でも水道水をそのままでは飲まない」という理由は、なんだろう。もしかすると、塩素投入が増えたことなど、安全面への不安があるのかもしれない。そうであれば、私たちは命を支える水に「安全」と「安心」を求めていることになる。
ところが、おいしいと思う水のトップは断然「渓流の水」で、ミネラルウォーターを大きく引き離し、4割強の人から常に支持を受けている。
渓流の水は、もしかすると大腸菌で汚染されているかもしれないし、上流にゴルフ場があるかもしれない。「安全」と「安心」からいったら、生産管理の態勢が整っていてボトル詰めされたミネラルウォーターのほうがポイントが高いはずなのに、実際には渓流に軍配が上がる。人が水に求めるものは、奥深くて見えにくい。
排水の行方には無頓着
節水に対する意識は、調査を始めた当初から高かったが、近年の環境意識の高まりにつれて、いっそう向上し、69.6%に達している(2007年)。すでに個人の努力範囲を越え、洗濯機などの家電製品や水洗トイレの洗浄水など、家庭用品を供給する各メーカーは節水に対して真剣に取り組んでいる。節水は、もはや単なる謳い文句の域を越え、日常的で当たり前の行為に達した感がある。
水を有難いと感じ、大切に使う気持ちは、とても尊いものだ。
反面、使った水がどこに行くのか「排水先を知っている」と答えた人の割合が38.1%(1995年)から23.9%と(2007年)大きくダウンしているのは気がかりな数字である。
私たちはつい上水道の質ばかりを気にしがちだが、健全な水循環にとって、水の供給と排水をセットで考えることは欠かせない視点である。
排水の行方にも、もっと関心を持っていきたいものだ。
よい子は川で遊ばない?
水と親しんだ経験の有無はどう変化しているのだろう。
「プール以外で泳いだことがある」と答えた人の合計は76.1%(2007年)。
「思い出の水辺の遊びをどこでしたか」という質問には、20歳代、30歳代では海のほうが川よりも多いのに対し、50歳以上ではそれが逆転する。つまり、50歳以上は海水浴より川遊びのほうが多かった世代ということだ。
また50歳以上の人に、「その遊びをいつごろしましたか?」と聞いたところ、10〜11歳という答えが男女ともに圧倒的に多かった。
10歳だった時点を考えると、50歳の人で1967年、70歳の人で1947年だ。四大公害病であるイタイイタイ病が1955年、水俣病が1956年、第二水俣病が1965年、四日市ぜんそくが1960年に確認されたことを考えると、敗戦の年に生まれた今年62歳の人たちが、川で泳いだ最後の世代ではないかと推測できる。
「よい子は川で遊ばない」という看板が立てられた川を見かけることすらある現在、その世代の人たちが経験した楽しい川遊びは、はるか遠い昔話になってしまった。
きれいな川が復活したら、子供たちは川に返ってくるのだろうか。
ビール党の日本酒びいき
「水とかかわりの深い日本文化といえば?」という問いに、56.9%の人が「酒造り」と答えている。酒場で銘酒を楽しむのは飲んべえには堪らぬひとときだが、実は三大都市圏では日本酒党よりビール・発泡酒党のほうが多い。
日本酒の製成量は1995年(平成7)の98万klから2005年(平成17)には49万9000klとほぼ半減している。
一方ビールも679万7000klから365万klでやはりほぼ半減。ところが発泡酒とビール風味の第3のビール(統計では雑酒に分類)は、21万1462klから273万6969klへと大幅な伸びを見せている(国税庁『酒のしおり』2007)。味より価格、というのが最近の飲んべえのフトコロ事情なのだ。日本酒の1人あたり年間消費量第2位の秋田県でさえ、若者の日本酒離れが進んでいるという調査結果もある(秋田銀行秋田経済研究所)。
日本酒や焼酎には土地に縁のある地域密着型の酒蔵が、それこそ無数に存在する。それぞれの味の差を楽しむことが、日本酒文化を愛でることでもあるのだ。
一方ビールの場合は、大手4社体制のまま推移し、地ビールが解禁された1994年(平成6)以降は、地ビール工場が各地にこぞって設立された。一時のブームは沈静化したとはいえ、現在、日本地ビール協会に登録されている銘柄は全国で262に達している。
また「水とかかわりの深い日本文化といえば?」の次点には、「稲作」と回答した人が48.8%に上る。これも2007年現在、日本の農業従事者は100人に5人と低いにもかかわらず、高い支持を集めている。たとえ日頃の生活から遠くなっても、「酒造り」と「稲作」には、日本の水文化を感じさせる何かがあるようだ。
台風、水不足、雨による浸水が不安に感じる水の災害のワースト3
水には暮らしや命を支え、作物を育ててくれる正の側面と、災害という負の側面がある。
水を効率よく利用するという正の側面が、上下水道などのインフラ整備で進められてきたのと同様に、人の命や財産を守るために災害への対策も積極的に行なわれてきた。
その結果、自分の身に水の災害が降りかかる可能性は低くなった、と認識されるようになっていった。その安全神話を崩したのが1995年(平成7)1月17日午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災である。
不安に感じる水の災害は台風が67.8%、水不足57.8%、雨による浸水47.4%(すべて2007年)の順だが、地震は上下水道の断絶という思わぬ形で、被災者に深刻な水不足をもたらした。
電動ポンプと給配水管に頼る上下水道の脆弱さが、「渇水でないのに水不足」という想定外の結果を露呈することになった。
「水不足の不安を感じている」という回答は、63.4%(2004年)から57.8%(2007年)へとわずかながら減少している。
同じ失敗を繰り返さないためにも、災害に強い都市をつくるための対策を、今、講じる必要があるだろう。
身近な川より生物多様性が里川の条件
当センターが、2003年10月発行の『水の文化15号 里川の構想』で、「里川」という言葉と概念を提唱してから丸4年。2006年には『里川の可能性 利水・治水・守水を共有する』(新曜社)を出版した。
里川のイメージで一番に挙げられているのは、清らかな水が流れる川で57.8%。2位も、生き物がたくさん棲んでいる川で53.3%。3位にやっと、身近に感じられる川36.1%が登場する。我々が提言している里川は、地域密着型の身近な川なのだが、残念ながらまだその概念は一般には浸透していないようだ。
実際に里川と思う川の名前を書いてもらったところ、四万十川が断然トップで10.4%、木曽川5.9%、多摩川5.0%と続くことからも身近な川という概念とは遠い。「プール以外で泳いだことがある」と答えた人の合計は76.1%だが、自分の子供や孫の代になると28.4%(すべて2007年)と激減してしまうように、今の日本の川はどうやら身近に親しむ存在にはなっていない。
もちろん、清流であることも、生物多様性が確保されていることも大切だが、水辺で夕暮れを楽しむためにも、川がもっと身近な存在になることが不可欠だ。
しかしそんな思いに反して、「水辺では夕陽が沈む様子を眺めたい」という人が57.0%(1995年)から42.4%(2007年)に減り、「景観を楽しみたい」、「散歩を楽しみたい」という人も軒並み16%以上減少している結果には寂しいものを感じる。
忙しいのが原因なのだろうか。ちょっと心配な状態である。