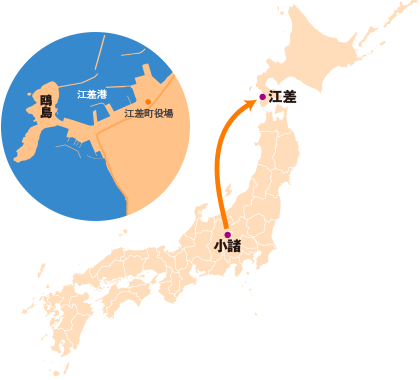機関誌『水の文化』54号
Story3
北前船が運んだ民謡
――江差追分と小室節

三味線と尺八の音色にのせて歌われる江差追分。江差追分会館では4月末から10月まで毎日3回実演がある。
この回は、唄は棚橋健蔵師匠、三味線は房田文江さん、尺八は山本滋さんが務めた
人と荷を載せ、沿岸を船が行き来する。そうするうちに、形のないものも長い時間をかけて伝わっていく。その一つが「民謡」だ。はるか信州から日本海を介して北上し、北の大地に根ざした「江差(えさし)追分」は全国大会を毎年開いており、その名を知る人もいるだろう。そしてその源流の一つとされるのが「小室(諸)節」。地元・長野県小諸市では、次世代に伝える活動も続く。「江差追分」と「小室節」が生まれた地をたどると、人から人へゆるやかに受け継がれた民謡という無形文化の成り立ちが垣間見えた。
ニシン漁に沸く港町で歌い継がれてきた古謡
初めて「江差追分」を聴いたとき「口があくほどびっくりしました」。
そう話すのは、札幌出身で今年から地域おこし協力隊として江差町教育委員会に赴任した奥山さとみさん。
かもめの なく音に
ふとめを さまし
あれが蝦夷地の やまかいな
正調江差追分本唄(ほんうた)の7節だ。これを2分半近くかけて歌う。奥山さんならずとも、江差追分を初めて聴く人だれもが、その悠揚として迫らぬ、雄大でゆったりしたテンポに驚く。
大海原をゆりかごに寝ていたら、かもめの鳴き声に起こされ、彼方を見やれば北海道の山々が迫る――。波にたゆたう船のように「かもめぇ〜ぇ〜ぇ〜……」と長く節を引くのが、追分節ならではの歌い方だ。
その船とは、日本海沿岸および瀬戸内海と北海道を結んだ北前船。一説に、信州追分宿付近の馬子(まご)唄が北国(ほっこく)街道を通じて越後に伝わり、参勤交代の北国武士、あるいは瞽女(ごぜ)と呼ばれる三味線を弾き歌う目の不自由な女性たちなどを介して北前船の船乗りたちの舟唄に転じ、海を越え江差にも行き着いたとされる。
江差が北前船の交易港として栄え始めたのは江戸時代半ば、17世紀末から18世紀初頭にかけてのこと。
「このあたりを治めていた松前藩は農民からの年貢取り立てではなく交易で経済を成り立たせていました」と江差町教育委員会社会教育課主幹の宮原浩さんが説明してくれた。
「交易を統制するために藩は、松前と函館と江差の3港を指定港として商人に交易の経営を請け負わせたのです」
本州への上り荷は主として海産物、本州からの下り荷は生活必需品。
とりわけ日本海に面した江差港は、ニシン漁の集積地として賑わった。
「ニシンは主に肥料として出荷されました。どろどろに煮たものを圧し潰して粕を絞りとった。江差だけでなく、渡島(おしま)半島の西海岸いたるところに加工場があり、江差港に集められ北前船で運ばれたのです」
なにを 夢見て
なくかよ 千鳥ネ
ここは江差の 仮の宿
(江差追分後唄(あとうた)より)
「入船三千、出船三千」と言われるほどの活況を呈した北前船の船頭や船子。ニシン漁で一攫千金を狙う日本海沿岸からの出稼ぎ漁夫。海の男や港湾職人を鼓舞する労働歌、ないしは港まちの夜を彩る遊興歌として、江差追分は連綿と歌い継がれてきた。
北前船が停泊した天然の防波堤「鴎島」
江差が交易港として栄えたのは、北前船が停泊するのに絶好の地理的条件を備えていたからでもある。それが「鴎島(かもめじま)」だ。日本海の波風を遮る天然の防波堤・防風壁であり、北前船の寄港地にうってつけだった。鴎島があったからニシン漁に沸く江差には続々と船が乗りつけ、それを商いとする人々が現れる。娯楽のない開拓地だから、遊芸人や遊女たちも商売になるだろうと渡ってくる。人が人を呼び、江差は「江差の五月は江戸にもない」といわれるほどの賑わいを呈した。
今は鴎島に陸続きで渡れる。老婆が神様から授かった瓶子(へいし)(注)のなかの水を海に注ぐとニシンが群れたとの伝説に基づく「瓶子岩」を過ぎたあたりに、北前船の係船跡が残る。打ち込んである木杭は後から立てて朽ちたものだが、岩場に穿(うが)たれた穴は当時のままだという。
鴎島の上に登ると、日本海側に千畳敷が見下ろせた。岩場に砕ける波しぶきの向こうに、日本海の荒波を越えてきた北前船の姿を思い浮かべてみる。空にはカモメが舞う。江差商人が北前船の船子たちへ飲み水を提供するため明治初頭に掘った井戸が残されていた。灌木の陰にひっそり佇む井戸が、北前船と鴎島と江差追分をつなぐ縁を今に伝えている。
(注)瓶子
酒器の一種。上胴のふくらんだ細長い器で口元は細首。「へいじ」ともいう。
節回しも歌詞も明治までは各人各様
現在は函館在住だが江差に生まれ育った樹木医の館和夫さんは江差追分の研究家。北前船によって民謡が伝わった傍証となる文献の写しを館さんに見せてもらった。1843年(天保14)に住久丸の船頭・山本嘉右衛門が、日本海沿岸の各地で歌われていた民謡の歌詞を筆録したもので、昭和40年代半ばに島根県温泉津(ゆのつ)町小浜の旧家から発見された。後背地に石見銀山をもつ温泉津も北前船の寄港地として栄えた。
「松前節」として紹介されている歌詞のうち一つは、現在、江差追分の前唄(まえうた)としてよく歌われる、
大島 小島の
間通る 船は
江差がよいか なつかしや
とほぼ同じで、原型といってよい。
館さんによれば、明治年間までの江差追分は節回しも歌詞も「各人各様」だったというが、大きく分けるならば三つほど流派があった。
「漁夫や船子相手の浜小屋という飲食街の遊興歌だった〈浜小屋節〉、花街の芸者や旦那衆が花街で三味線や踊りをつけ座敷唄にした〈新地(しんち)節〉、町内北部の馬方や職人による〈詰木石(づみきいし)節〉がありました。浜小屋派は早くに絶えましたが、新地派と詰木石派は最後まで競っていたのです」
江差追分の歌詞は千とも二千ともいわれている。庶民の娯楽といえば飲んで歌って踊るくらいしかなかった時代、各々の生活様式を背景に育まれ、長い年月をかけて歌い込まれてきたのが土着の民謡だとすれば、かつての江差追分が千変万化の様相を呈していたのも不思議ではない。
地域ブランドによるまちおこしの先駆け
それが今日のような「七節、七声、二声上げ」と呼ばれる標準的な曲調に統一されたのは1909年(明治42)。実はニシン漁の衰退と関係がある。
「有志たちが郷土芸能をバネに人心を奮起し町勢を建て直そうとしたのです。各人各様の曲調では広まりにくいので基本を定めました」(館さん)
平野源三郎、村田弥六、高野小次郎ら名人たちの普及宣伝活動で江差追分の声価は全国的に高まり、1935年(昭和10)、江差追分会が発足した。戦後は「NHK全国のど自慢大会民謡の部で地元の柿崎福松師匠が日本一の栄誉を勝ち取ったのを契機に江差追分のすばらしさに改めて注目が集まり」(館さん)、1963年(昭和38)から「江差追分全国大会」が開催され今年で54回を数える。
江差追分会の会長は発足時から町長が務め、町役場の「追分観光課」が事務局だ。2016年4月現在、全国各地に164支部(うち海外5支部)をもち、会員総数は3493名にのぼる。同課主幹の三好泰彦さんは、まちぐるみで江差追分を全国発信してきたことについてこう話す。
「まさに今でいう〈地域ブランドによるまちおこし〉。企画した昔の人たちの発想はすごいと思います」
江差追分全国大会「入賞者の歌声 一覧」
各大会の見出しをクリックすると動画を見ることができる
http://esashi-oiwake.com/national-conference/singing-voice
江差追分の源流を信州小諸に尋ねる
ここでいったん江差から目を転じたい。北前船の上り荷と一緒に越後の寺泊(てらどまり)港あたりに上陸し、いにしえの北国街道を南に遡ろう。江差追分の源流の一つとされる「小室節」のふるさと、長野県小諸市へと。
小諸出てみりゃ 浅間の山に
けさも 三筋の 煙立つ
(小室節歌詞より)
小諸市教育委員会生涯学習課の山東丈洋(さんとうたけひろ)さんに小室節の起源を聞いた。
「小諸近辺には東山道(とうさんどう)という古代の軍用道路が通り、平安時代の初めごろから朝廷に献上する軍用馬を飼育する『牧(まき)』と呼ばれる場所がいくつかありました。馬を育てる神様に捧げる祝詞(のりと)形式の祭礼唄と、牧のなかで生まれた馬追いの唄が合わさって小室節の原型になったといわれています」
小諸はかつて小室と呼ばれていた地域。北国街道と北前船を経路とし、小室節→追分(現・軽井沢)節→信濃追分→越後追分→江差追分という伝播ルートがおおまかにたどれる。追分とは街道などの分岐点を指すが、中山道と北国街道の分かれ目にある宿場町「追分」が有名で、江戸時代にその付近で歌われていた馬子唄を三味線にのせて歌い出したのが追分節の名の起こり。小室節は、追分節よりも少し早く成立していたのではないかと考える研究者もいる。
メディアのない時代、民謡の伝播に重要な役割を果たしたであろう馬子とは、信濃路で幕府管理の宿場を経ず荷主と直取引で荷物を扱った運送業「中馬(ちゅうま)」を担った人たちだ。馬を操りながらの労働歌を聞いた宿場町に泊まった旅人や働く女性たちの口伝から広まったのかもしれない。
小室節の起源は諸説あるが、「正調小室節保存会」会長の中山喜重(きよしげ)さんは〈渡来人起源説〉を紹介する。
「小諸市の御牧ヶ原にあった最大の牧でモンゴルからの渡来人が馬の飼育に携わり、望郷の念に駆られて歌ったのが原型ではないか、と。モンゴルの古謡『駿馬の曲』とメロディーが酷似しているんですね」
長野県モンゴル親善協会会長でもある中山さんがモンゴルで小室節を歌うと、現地の人は「なんとなくモンゴルの唄に似ている」と言うそうだ。生活や仕事から自然発生的に生まれた民謡の起源を定めることにこだわる必要はないが、遠い大陸の地と海を越えて唄の調べが共有されていたと想像してみるのも興趣(きょうしゅ)が尽きない。
小室節を「地元の方々にもっと知ってもらうのが課題」(山東さん)。正調小室節保存会が小学校で出張授業をしたり、7月の祇園祭で健速(たけはや)神社より出る神輿を小室節が先導する伝統の神事が今年から復活するなど、地道な普及啓発活動が続いている。
物心ついたときから生活の一部だった
江差の割烹「味処やまもと」で山本滋さんの尺八を伴奏に、女将、康子さんの江差追分を聴いた。やはり生の歌声はいい。きっとこんなふうに歌い継がれてきたのだ。遠来客が求めればお二人は披露する。康子さんは全国大会にも毎年参加。「両親が唄っていたので物心ついたときから生活の一部でした」。
全国大会には中学生以下の少年大会もあり、今年は50人が参加した。民謡もポピュラーミュージックに相違ないが、無拍子で節を長く引く江差追分は今どきの流行(はや)りの音楽とはあまりにも遠い。それが若い世代にも自然に受け継がれている。いくら幼いころから接する機会があっても楽しくなければ歌おうとはしないだろう。民謡に魅かれる心が日本人の遺伝子には埋め込まれているのか。
江差追分会学芸部門理事の館さんは北海道新聞の記事「江差追分の未来像」で「この唄が持つ伝統の力を信じながら(中略)表現の多様化に取り組むべきだろう。洋楽や他の芸術分野の協力も得て、江差追分を核としたさまざまな形の音楽や芸術作品を制作し発表する試みをもっと盛んにしてほしい」と述べている。今年から始まった青森県五所川原市の津軽三味線会館へ出向いての「ジョイントライブ」などはそうした試みへの第一歩だろう。
信州の山で生まれた唄が幾多の変容を重ね海の唄となって北の大地に根づき、全国へとその真価を広めた。かつて本州から北海道へと渡る北前船の下り荷の一つだった民謡は時代の荒波を乗り越え、今また、より広い世界へと届く上り荷として未来への航海を続けようとしている。
(2016年8月18日、9月6~7日取材)
参考文献
『江差追分物語』(北海道新聞社)
『小室(諸)節考』(鬼灯書籍)
『追分節―信濃から江差まで―』(三省堂)
『日本の民謡と舞踊』(大阪書籍)