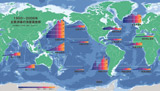水の風土記
資源論とは潜在的な利用を発見すること
〜タイの森林資源をめぐる人と力と利用機会〜
最近では、水も森も、地球規模での「稀少資源」と呼ばれます。そして、この枯渇するかもしれない稀少資源を、地域の共有資源「コモンズ」として守れないものかと議論されています。しかし、そもそも「資源」とは何のことなのか。 今回は、タイの森林等をフィールドに、開発と資源とコモンズという複合領域を切り開きつつある研究者の佐藤仁さんに、資源についての考え方や、タイのコミュニティ林についてうかがいました。
-

-
東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授
佐藤 仁 さとう じん -
1968年生まれ。ハーバード大学ケネディ行政学大学院修士課程修了。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了。2000年より現職。
主な著書に『希少資源のポリティクス〜タイ農村にみる開発と環境のはざま』(東京大学出版会、2002)他。また、ハーバード在籍時に師事した、アマルティア・センの『不平等の再検討〜潜在能力と自由〜』(岩波書店、1999)を共訳している。
富源から資源へ−資源という言葉
タイの森林の話に入る前に、資源についてお話ししましょう。
「資源」という言葉がいつ頃から使われるようになったかご存知ですか? 戦前の辞書を見ますと、この言葉は収録されていない場合が多く、大正時代には皆無です。ですから、資源という言葉は新しい言葉なのです。その前はどうかというと「富源」という言葉が使われていました。
石油や石炭、水、鉱物などを、なぜ資源として「まとめて」呼ぶ必要があったのか。この点に関心をもちました。明治や大正期の新聞でも「資源」という言葉が使われているのですが、この言葉が急速に普及する契機になったのは、1927年(昭和2)に、内閣資源局という部署がつくられた時でしょう。この部署の中心人物は松井春生という官僚です。
なぜこのような部局ができたのでしょうか。これより18年前、アメリカ第26代大統領のセオドア・ルーズベルト(在任1901〜1909)が、1909年に全米の知事を集め、西部開拓で荒廃したアメリカに、どのような天然資源があり、どうすればそれを長持ちさせることができるかをテーマとした大きな会議を開いています。資源の賢明な利用について会議が開かれているのです。この会議のことを、若き官僚だった松井春生は知り、「これは素晴らしい。日本では、総合的な視点から資源を管理するという発想がまったくない」と思った。昭和2年の段階で松井がどのようにして「資源」という言葉を知ったのかはわかりませんが、この概念を用いることで石油、石炭、木材・・・そして人間の体力や技能も含めて、それまでばらばらに扱われてきたモノを、何らかの有用な力に変えるために、まとめて表現する必要があったわけです。
松井が言うには、近代化というのは、いろいろなものが分かれていくことで、政府の機構も分かれ、無駄が出る。だから、日本の国力を高め、引き出すために、資源という概念でまとめてみる必要があるということなのです。ですから、国力に役立てるという意味と結びついて資源という言葉が使われ始めるのは昭和2年以降なのです。
これに先立つ22年前の明治40年頃、柳田国男もおもしろいことを言っています。彼は早稲田大学で農政学の講義をしているのですが、その中で、「富源」の種類を述べているのです。「私人に勝手に使わせると無くなってしまうものがある」と言い、現在のわれわれが使うコモンズに近い。柳田は将来世代への配慮していたのです。「今の人豊かなるときは、その結果、後の人に乏しからずあたわず」と。この他にも、「使えば使うほど価値が出るという富源もある」といい、土地など人の勤労によってその価値を増すもので、現在のソーシャル・キャピタル(人と人の絆で、信用などを生む)にもつながるような論点を示唆しています。そして、「みんなが勝手に使うと消耗して無くなってしまうものについては、国が責任をもって警察力を行使してもそれを管理しなくてはならん」と言っています。明治40年の段階で富源を分類して、誰がどの分類の富源を管理しなくてはならないと指摘しているのはすごいと思いましたね。
いずれにせよ、アメリカでは「コンサベーション:Conservation」という、資源を賢明に、節約して利用する、あるいは将来を見越した資源の利用という考え方が100年前から議論されていたということです。しかも、当時から「コンサベーションの基本問題は、現代世代と将来世代の対立の問題だ」と言われていました。われわれは1980年代に国際会議が多数開かれ、やっと持続可能な開発についてわかってきたかという風に思っていますが、実は100年前から言われていたことなのです。日本でも柳田の例にあるように、かなり以前から資源保護の重要性は指摘されていたのだと思います。
【松井 春生(まつい はるお) 1891〜1966】
内務省に入り、内閣調査局調査官、資源局長官、大阪府知事を歴任し、1937年には東京商工会議所理事長に就任。46年には貴族院議員に勅選されたが、直後公職追放となる。主な著書に『経済参謀本部論』(1934)、『日本資源政策』(1938)がある。
裏山の木がなぜ使えないのか
資源の問題を考える上でコモンズと呼ばれる共有資源の問題は大事です。コモンズは、環境問題の観点だけからではなく、その資源に依存している人々の生活の視点からも見ることが必要だからです。そこで、私自身は、「コモンズの管理を通じた環境と開発の接合」をテーマに、具体的にはタイの森林をフィールドに定めました。
実際に、タイ、カレンの村でフィールドワークするようになると、「自分の身の回りの森を自由に使えない」という現象に考えさせられるようになります。カレンという森とともに暮らしてきた人々が、たまたま自分たちの側にあった森が世界遺産に指定されたり、国立公園になったりしたために、そこに入るとパトロールしている人につかまってしまう。そこには山岳民族に対する蔑視もあったかもしれません。とにかく、森と共に暮らしてきた人が自分たちの裏山を自由に使えないという現象が起きている。
一方、日本人を見ますと、日本の山の木で家を造る人は少なく、どこか国外の木を持ってくる。そういう意味では、「裏山の木が使えない」という事例は、どこか重なって見えます。
要は、「自分の身近な資源を使えないという構造の中に生きている」ということがあるのです。これはグローバリゼーションの一つの兆候だと思います。そこを考え出すと、どうも村人の力や住民参加をあてにしているだけではだめで、「どうして村人は、自分たちの身近な森を使えなくなってしまったのか」ということを、もっと政策のレベルから考えねばならないのではないかと思いましたね。
当時、このような着眼は、欧米では始まっていたのですが、日本ではほとんどありませんでした。アメリカ、イギリスでは、「環境というものは政治だ」ということで、ポリティカル・エコロジーということばや研究グループがあり、資源や環境を、争いの対象として捉え、資源をめぐる権力関係に着目して、住民はどのように抵抗を試みるのかを詳細に調べることが始まっていました。私は、資源問題は人と自然の問題というよりは、本質的には「人と人の問題」であると考えていますが、日本では不思議とこの分野の研究が遅れています。これほど世界から資源をかき集めて暮らしている国で資源論が盛んでないのは不思議なことです。私は、社会科学の見地から新しい資源論を確立したいと考えているのですが、その内容のポイントについては、また最後に触れたいと思います。
「貧しい人が森を壊す」は本当か?
ところで、「貧しい人が、貧しいゆえに、森を壊している」という広く信じられ教科書にも載っている言説があります。「貧しい人々は将来のことを心配できず、森に入って木をこっそり切っている。かわいそうだ」という訳で、誰も疑わないのですが、本当にそうか調べた人はいないのです。
まず、私は「本当に貧しいのなら、環境を破壊する力など無いに違いない」と直感的に思いました。タイでも環境を深刻に破壊しているのは、ゴルフ場やダム建設等を進める金持ち層です。貧しい人の環境破壊とはいったい何のことなのか。私が『稀少資源のポリティクス〜タイ農村にみる開発と環境のはざま〜』(2002)を書く動機になっているのは、この問いです。そして、調べるプロセスで、貧しい人と貧しくない人をどうやって見分けるかが課題になりました。
結局、本の中では、「村人に訊く」という最も初歩的ですが、信頼できる方法をとりました。村人の名前をカードに書き、それを何人かの方々に仕分けをしてもらい、村の中でいい暮らしをしている人と、ちょっと苦しい人を分けてくれ、と御願いするわけです。すると、みんなが共通して「こいつら貧乏だ」というのは出てくるわけです。すると、その人たちはなぜそうなって、どのような暮らしをしているのか、その人たちと森との関わりを見たわけです。
結論としては、やはり、「貧しさ故の環境破壊」というのは、エリートのしていることから目をそらすためのフレーズでしかないということです。確かに、私有財をほとんどもたない貧しい人々は、森林などの共有資源に大きく依存して暮らしています。ですが、依存度が大きいことと破壊的であることは区別されるべきですし、依存度が大きいということは、その資源を大切に扱う理由があるということでもあります。貧困故の環境破壊が全くないとは言わないし、一部ではそういうことがあるかもしれませんが、環境破壊を人口増加と貧困だけのせいにして、大規模開発を棚に上げる議論が多く聞かれます。そのような「開発の構造」については挑戦していかなくてはならないと思っています。
コミュニティ林という「どうでもよい森」
タイには「コミュニティ林」と呼ばれる森があります。よく村人によるコミュニティ林の管理が話題になるのですが、「コミュニティ林がよく管理されているかどうか」という質問は注意しなくてはいけない質問です。なぜなら、管理の程度を問題にする前に、「どのような森がコミュニティ林と呼ばれているか」という点を私は大事と思うからです。
非常に粗く言いますと、タイでは政府が見放した「どうでもよい森」がコミュニティ林として村人にあてがわれています。つまり、政府が魅力を感じない森がコミュニティ林なのです。政府が資源としての魅力を感じ、「ここを使われては困る」という森林は、国立公園や野生動物保護区の指定を行い、政府が囲い込んで、そこに暮らしていた村人を排除する。ですから、コミュニティ林の多くは荒廃林で、その荒廃している森を、政府が村人を雇って木を植えさせたりする。これが政府の考える「コミュニティ林」なのです。
したがって、村人の視点に立てば、彼らがコミュニティ林の管理に本気を出さないのは当然です。管理するに値しない森に、村人が関わるわけがありません。「村人が管理していないからけしからん」とか、「村人を教育してやらないといけない」とか、「村人を研修して技術を導入しなければ」などと言う前に、「どのような森が与えられているのか」という、その一番大事な点を問題にしないといけないのです。
ただ、一部、村人が喜んで使うような森があてがわれている場合もあります。森の区分けは法律や閣議決定で行いますが、現場では区分けするためにフェンスを張ったりすることなどできません。すると、現場の役人としては問題を起こしたくないし、村人とも喧嘩はしたくないから、「ここは野生動物保護区だけれども、きのこや筍や、自分の家を建てるくらいの木なら伐ってもいいよ」と、それぞれの地域での裁量がまかり通っているのが現状です。ですから、役人が村人の生活に一定の理解をもっているような地域では、役人の裁量の範囲内で、村人にとっても価値のある森の利用を許すケースがあります。法律上は、国立公園の中の落ち葉も採ってはいけないということになっていますが、現実にはそこでたくさんの人が生活をしているのです。
将来の伐採予定地としてかつて森林局が囲い込んだ地区である「国有保全林」は全体の約4割ですが、たくさんの村人がその中で生活していますので、国有保全林という概念はほとんど機能しなくなっています。ただ、タイ政府としてどうしても守らねばならない場所、逆に言えばそれだけ魅力的な場所は、「野生動物保護区」と「国立公園」という形をとり厳格に守ります。
国有保全林というのは、森林を守るために囲われたわけではなく、将来の伐採により得られる利益を見込んで囲い込まれています。つまり「保全」というのは「伐採予定地」という政府の利権と同じ意味です。将来伐採しようと思って囲ったのですが、伐採のペースが早くなり、伐採する所がなくなってしまった。このため、89年に商業伐採も完全に禁止になりました。ただ、法律はすぐには変えられませんから、保全林という名前と土地の所有権の区分は残っています。しかし、伐採そのものはなくなったので、今度は荒れた土地を植林などでどのように復活させるかが問題になります。そのような土地の中で、ちょっと見込みのありそうな所、しかし政府が本気になって保護するに値しない所にコミュニティ林という美しい名前をつけているのです。
「どのような森がコミュニティ林と呼ばれているのか」というのが根本的な問いで、その問いを抜きにして住民の管理能力を云々するのは、話の順序が違うのです。管理に値する資源が与えられて、はじめて住民の資源管理能力を問うことができる、と私は考えています。
なぜ人々は森林を「守る」のか
人々が森林を守る誘因はどこにあるのか、という質問ですね。人によって、保全しようという理由が違いますので、私は「誰にとっての保全誘因か」という点が、重要と思います。つまり、森を利用する主体によって、狙っているものが全然違うということです。だから争われることにもなります。
例えば、住民にとって森林は、自分たちが生活していく上で役立つものを提供してくれる生活資源ですね。ただ、住民と一括りにするのもちょっと乱暴でして、住民の中にも、森と直接関わり無い人もいます。畑をある程度もっている人はそちらの方が稼げるし、忙しい。むしろ、畑をもっていない人が、森に入り、きのこや筍や動物を集めて売るという生活をしている。同じ村の中でも生業の中身や規模が異なると森との関わり方が全然違います。
むろん、一般的には森林は生活を支えてくれているものであり、ことによるとその土地の宗教や信仰と深く関係しているかもしれません。
それに対して、政府の保全誘因もいろいろあります。例えば、現在、環境を守るという目的で資金援助をする先進国は増えています。したがって、「われわれの国にはこれだけ多様な生物が住んでいて、でもそれを守る予算がありません。われわれの保全プランはこうです」と先進国から援助を引き出すことが保全の誘因となっていることもあるでしょう。
さらに、国立公園や野生動物保護区は森林局の許可なしには誰も入れないために、中で何が行われているか外からはわかりません。その結果、役人が率先して中の木を伐って売ってしまうという横領や、森林を管理するために職員を架空に雇ったことにして資金をプールするというような公共事業の悪弊が表沙汰になったりすることもあります。それも、彼らにとっては「保全」を前面に出す誘因になります。
とにかく山を囲い込んでおけば、そこでダムや鉱山開発をするとなれば森林局に許可を得なくてはならない。許認可、利用料の設定など、すべての権益を握るわけです。だから、森があってもなくても、土地を囲い込んでおけば、いろいろなことができる。これは保護区とか保全地域をつくる非常に強い誘因になります。土地の囲い込みと、結果としての森の保全は、まったく別の事柄です。
森林保全と一口に言っても、樹木など植生の側面だけを見たエコロジカルな保全だけを見てもだめで、その資源に対して、「誰が」「どのような利益を狙い」、「人々の政治的関係の構造がどのようなもの」で、「結果として、誰にどのような機会が開かれているのか」を見ないといけません。
現場だけ見ていてもだめ
このような問題は、「現場だけ」で考えても見えてきません。村の中やその周辺で作用するような人々の関係である「ソーシャル・キャピタル」や、地元の人々で共有資源を共同で管理することができるのではないかという一般的なコモンズの議論も、「地域で問題を解決できると」いう大前提があるわけです。でも、やはり今まで申し上げてきた通り、政治的力の異なる人々のやりとりというのは不可避で、それに目をつぶって「地域の人の力」にのみ希望を託すのは楽観的ではないかとも思うのです。
象徴的な例では、例えば、タイでは最も熱心な森林保護論者は都市に住んでいます。そして、森の側に住んでいる人たちが、むしろ森林保護の迷惑を被っている。そこに非常に不思議なパラドクスがあります。
やはり、現場だけを見るのではなく、「現場」と「現場の外」がどう関係しているのかを見ないといけないでしょう。例えば、「森の側に住んでいる人がどのような利益、不利益を被っているか」だけではなく、都市に住む人たちが家を建築する時にどこから木を買うしくみになっているか、値段はどのように決まっているかなど、そこにきちんとメスを入れていくこともしないといけません。地元だけを見ていても限界があります。
資源とは「あるもの」をみること
資源論の研究は、「うまくいっている」所から学ぶということが基本だと思います。コモンズの研究というのは、もともとは「個人が合理的にふるまうと、共有資源は枯渇してしまうという集団の不合理に結びつく」という失敗の説明から始まっているのですが、実は、成功したケースから学ぶことの方が重要なのです。なぜなら、失敗した事例の失敗理由を一つ一つ除去しても、それは必ずしも成功に結びつかないからです。成功というものは、失敗の裏返し以上のもっと複雑なものです。ですから、うまくいっているものを見つけて、それを励ます。少なくとも邪魔はしない、という制度的な工夫は考えないといけないと思います。
したがって、資源論ではモノのもつ潜在可能性をどれだけ見抜けるかがポイントになります。例えば、第二次大戦で焼け野原になった日本を視察したハーバード大の地理学者、アッカーマンは資源と人々の暮らしをみて「日本の未来は明るい」と結論する報告書を出し、多くの日本人を勇気づけたと言われています。それは、その当時の日本に何があったかではなく、日本人の活力に潜在的な資源を見いだした上での発言だったといってよいでしょう。
鉱石をただ、モノとして見るならば、先に述べた富源でしかない。しかし、そこに、鉄に加工して有用性を引き出す可能性を見出すことでモノは資源になるのです。
潜在性を見るということは、どういうことか。それは、モノの「ある」に着目することです。Aという特徴も「ある」、Bという利用法も「ある」・・・という風にです。一方、批判をするということは「ない」ものをみているのです。ここには、住民の知識がない、能力がない、財源がない・・・。途上国に行って「あれがない、これがない」とすぐ言う人もいます。でも、そういうことを言っていると、何があるのか、自動的に見えなくなってしまうのです。もっとも、援助機関の立場から見ると、「あれがない、これがない」と言えば、「では、それを助けるプロジェクトをつくろう」と自分の仕事を増やすことができますが。
私が、資源という概念に惹きつけられるのは、潜在的に役立つものを見ようとする発想を要求されるからです。不足点をあげつらうわれわれの癖を無くす上で、非常に重要なことですね。
―― あるものを見るということは、何かの文脈において発見するということですか。
そうです。したがって、同じモノを見ても、資源が見えるか見えないかは、その人の眼力によって大きく変わってきます。
文明の歴史を振り返ると、そのような力が重要であることを証明しています。日本のような天然資源の少ない国が、なぜここまで豊かになれたのか。逆に、石油や石炭が豊富に出る国で、少なからず経済成長できなかった国があるのはなぜか。そのようなことを考えると、モノ<富源>の量ではなく、モノを価値あるものに転換する力が国や人によって異なっていることがわかります。
実は「資源の呪い」という言葉があります。「資源に恵まれている国は、なぜ経済成長できないか」という実証研究がかなりあるのです。それは、石油や鉱物など、資源で食べていける国は、資源を切り売りして国が儲けることができるので、自国の国民から税金を集める必要がなくなるわけです。すると国民に対して無責任な政治を行ってもよいということになりやすい。無責任な政治を行っても、エリートは石油や鉱物があれば生きていける。したがって、資源が豊富にあると、かえって悪いガヴァナンス(統治のしくみ)になり、民主化とかいう面で非常に停滞するという有力な仮説もでています。資源に恵まれていると、かえって呪いになるというわけです。すべての国でそうなるというわけではないのでしょうが。
―― 水ももしかしたら・・・
井上靖の短編小説に「聖者」という作品があります。紀元前6世紀、中央アジアのある部族の集落の話です。そこに住む人間は一日一杯しか泉から水を汲むことが許されなかった。水が少ないと思われていたために、その部族は他から襲撃されることがなかったのですが、外からある若者がやってきて水を二杯汲めるようにしてしまいます。すると、生活が活発になると共に放埒になり、争いに巻き込まれていきます。
資源が魅力的でないということが、平和という観点からは重要な役割を果たしているのかもしれませんし、あまり注目されないということが大事な資源になっていることもあるのではないですか。
水が今後どのような資源として受け止められていくか興味あるところです。そのようなことを考える上で、井上靖のこの作品は非常に深い示唆を与えてくれ、考える種を与えてくれていると思います。ぜひ読んでみてください。結末は秘密にしておきましょう。
(2004年2月10日)