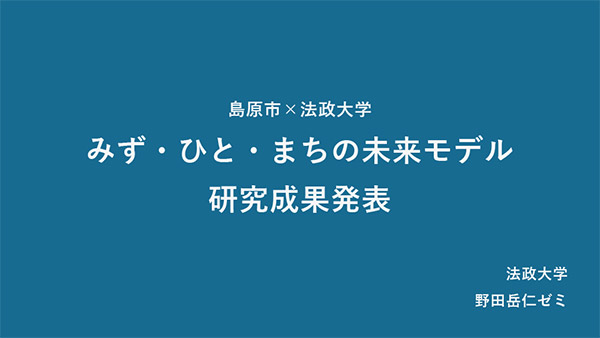2024 島原編(長崎県島原市)
水場の「価値」存続と地域住民のウェルビーイング

4年目は、名水百選の選定地である長崎県島原市の「島原湧水群」で研究活動を重ねました。水場の「価値」を存続させるために、どのような視点が必要なのでしょうか?
環境省が選定した1985年(昭和60)の「昭和の名水百選」から40年が経ち、存続の岐路に立つ名水百選選定地が出てきました。そこで、「みず・ひと・まちの未来モデル」のかじ取り役である法政大学現代福祉学部准教授の野田岳仁さんが着目したのが、長崎県島原市の島原湧水群です。なかでも「浜の川湧水」と「水頭(みずがしら)の井戸」の2つの水場は、水場の「価値」のわかる人を担い手に迎え入れたり、「価値」のわかる人を脱退させない工夫がみられました。本研究では、この2つの〈水場の「価値」存続〉の論理を明らかにするとともに、得られた知見から政策提言をまとめました。
初訪問から8カ月後の2024年(令和5)11月25日、島原市の方々を対象とした「研究成果発表会」を実施しました。研究活動と政策提言にあたっては、島原市役所にご理解とご協力をいただきました。
ここでは、機関誌『水の文化』で伝えきれなかった研究成果発表資料、そして研究活動を終えたゼミ生たちのコメントをご紹介します。
研究活動メンバー
法政大学現代福祉学部 野田ゼミ
准教授 野田岳仁さん(研究指導・連載執筆)
野田ゼミ3年生 11名

「研究成果発表会」終了後、島原市役所の原野聖さんを囲んで。発表を終えた学生たちの表情は晴れ晴れとしている
機関誌『水の文化』連載リンク
-
- 第10回 暮らしに根づいた水場の「価値」存続の論理
──名水百選「浜の川湧水」から考える生活と観光 
- 機関誌 水の文化77号「みんな、泳いでる?」(2024年7月発行)掲載
- 第10回 暮らしに根づいた水場の「価値」存続の論理
-
- 第11回 水場の「価値」存続と地域住民のウェルビーイング

- 機関誌 水の文化78号「街なかの喫茶店」(2025年1月発行)掲載
研究成果発表資料を公開
2024年(令和6)11月25日に法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎で「研究成果発表会」を実施しました。島原市役所と会場をリモートでつなぎ、また島原市を代表して市民部環境課主任の原野聖さんが会場に駆けつけてくれました。当日に発表・投影した資料を公開します。ぜひダウンロードしてご覧ください(一部非公開)。
島原市×法政大学 みず・ひと・まちの未来モデル
-
研究成果発表 資料(PDF3.37MB)
リンク先PDFファイルの内容は、著作権法により保護されています。以下の行為を禁止いたします。
・無断転載・再配布・転送
・内容の全部または一部の改変・複製・転用
8カ月間を振り返って
――学生たちの実感
島原市の方々に向けた「研究成果発表会」を終えた2024年(令和6)12月26日、野田岳仁准教授と野田ゼミ3年生がミツカンの東京ヘッドオフィスを訪問し、8カ月におよぶ研究活動を振り返りました。学生の皆さんに、島原で印象に残ったこと、研究活動を通じて成長したことなどを語ってもらいました。
(掲載は11月の「研究成果発表会」登壇順)

浜の川湧水チーム
-
-

-
重圧を乗り越えて
やりとげた島津元樹さん
しまづ もとき -
政策提言に向けてプレゼン資料をまとめる段階がもっとも苦しかったです。調査は順調だったので、周囲から「うまくいくだろう」と見られていて、その期待に応えたいという思いが逆にプレッシャーに……。完成形が見えないなか、チームのみんなと夜な夜なリモートで、ときには日をまたいでつくり上げました。ゼミで男性は僕ひとりでしたが、みんなが変に構えず受け入れてくれましたし、僕も出しゃばりすぎず、でもまじめすぎずにいようと心がけました。
-
-
-

-
困ったら人に
頼っていいとわかった上島小百合さん
うえしま さゆり -
私は思っていることや考えていることをなかなか言えないタイプでしたが、合宿や発表に向けて話し合うなかで、「自分はこう思っている」と少しずつ言えるようになりました。それは就活のインターンでも感じていて、「ここは言おう!」と思ったときはちゃんと言えるようになっています。グループワークでも、自分が困ったら聞いていいし、助けを求めてもいいんだ――そう思えるように成長したのは、みんなで苦労してつくり上げたゼミ活動の経験からです。
-
-
-

-
住民と仲間の刺激で
変わった自分成清颯花さん
なりきよ さやか -
今まで年上の人と話す機会があまりなかったこともあって、最初は「大丈夫かな……」と思いながら聞き取り調査に臨んでいました。しかし、岩永ご夫婦や満尾はるこさんなど浜の川の人たちは皆さん元気で明るくて、島原のこと、浜の川湧水のことをどんどん教えてくれたんです。ゼミの仲間が「自分の言葉」で話しているのを聞いて自分の足りないところに気づき、また刺激にもなって「もっと、がんばろう!」と以前より積極的に話せるようになりました。
-
-
-

-
「言葉を紡ぐ力」を
得たゼミ活動望月綾那さん
もちづき あやな -
ゼミ活動でもっとも身についたのは、住民からお聞きした話をほかの人にも伝わるようにする「言葉を紡ぐ力」です。今回は住民自身も把握していないような感覚的なものを研究したと思っているので、言葉にならないものをいかに言語化するかがカギでした。常に「なんで?」と思う気持ちをもち続け、矛盾を見逃さないことも意識しました。それは相手の立場に立って気持ちを察することでもあるので、今後にも活きる、とても大切な力を得たと思っています。
-
水頭の井戸チーム
-

-
よい意味で
図々しくなった藤澤珠奈さん
ふじさわ じゅな -
私たちは2年生まで調査やインタビューをする機会がなかったので、春に島原へ行ったときは不安でした。インタビューを雑談から始めても、本当に知りたいことを聞き出すための質問にどうやってもっていけばいいのかわからなくて……。それでも春と夏の合宿を経て、立場の違う人たちとのコミュニケーションが得意になりました。実はショップに行っても店員さんと話すのは苦手でしたが、今は「聞いてみよう!」と思えるので、よい意味で図々しくなりました。
-
-

-
ふだんの学びに
つながったゼミ活動鈴木いにさん
すずき いに -
今までは授業を受けて感想を書く際も、自分の考えではなく「こういうことがわかりました」と単調になってしまいがちでした。しかし、2回の合宿を経て、さらに政策提言も終わってからは、自分の経験やインプットしたものを「これはこれと関係があるな」と、まだなんとなくですが考えられるようになったんです。前回の授業で私が書いたものが次の授業で取り上げられることも増えました。ゼミの経験がふだんの学びにもつながったのがとてもうれしいです。
-
-
-

-
遊びの時間も
無駄ではない岩元咲紀さん
いわもと さき -
水頭の井戸は自分たち学生が興味をもってスタートしたので、住民にお話を聞いて正解を探すのもすべて自分たち。みんなで手分けして試行錯誤しました。浜の川湧水チームは順調そうだったので、「負けられない」というライバル心もありました。そのなかで身についたのはメリハリです。合宿では論理をまとめる時間と遊びみたいな時間の両方があり、遊びの時間から情報が得られたこともあったのです。その経験から、メリハリをつけたやり方を吸収できました。
-
-
-

-
危うい時期を
乗り越えたのは団結心長島麗奈さん
ながしま れいな -
春と夏の合宿で私たちは期待していた以上のものを得たんです。春は「これは楽しいぞ!」とわくわくしましたし、夏は時間が足りなくて悔しい思いをしました。秋からみんなで手分けして水頭の人たちに電話で調査を続けましたが、データは増えても論理をどう組み立てればよいかわからず、「水頭チーム、危ういんじゃないか?」という時期もあったんです。でも、住民の方の期待に応えたいという強い思いで団結して乗り越えました。大きな価値を得たと思っています。
-
-
-

-
「これなんですか?」と
聞けるように等々力あかりさん
とどりき あかり -
「この井戸のことを知りたいんですが」とアポイントもなく押しかけたら迷惑じゃないかな……と最初は不安だったんです。でも、水頭の人たちは親切で「あの人なら知ってるはずよ」と次の人につないでくれることがとても多かったんですね。人の温かさにふれられてうれしかったですし、やりがいにもなりました。その経験が生きていて、今は歩いていても「これ、なんだろう?」と興味をもったら知らない人にも臆せず話しかけられるようになりました。
-
商店街チーム
-
-

-
客観的に現状を
見つめる力がついた佐藤雪乃さん
さとう ゆきの -
夏合宿では岡部さんと二人で商店街をしっかり調査する予定だったので、台風で日程短縮となったのは残念です。しかし、これまでの私はトラブルが起きると「なんとかしなきゃ!」と焦って空回りしていましたが、今回は野田先生に相談し、岡部さんと話し合うなかで、主観的になりすぎず「今、何に対して取り組んでいるのか」「どこが課題なのか」と客観的に見つめ直すことができたんです。いい経験になりましたし、この経験を卒論にも活かしたいです。
-
-
-

-
逃げずに向き合って
成長できた岡部毬菜さん
おかべ まりな -
夏合宿は短い日程になってしまいましたが、座学では感じることのできないおもしろさを体験しました。お話をお聞きした商店街の皆さん、そして歩いているなかで出会った住民の皆さんがほんとうに温かく迎えてくださって、研究に対する焦りはあったものの、気持ちよく調査することができました。現地調査のおもしろさや辛さを肌で感じたこと、そして目の前のことから逃げずに向き合った経験から、人間的にも精神的にも成長することができたと感じています。
-