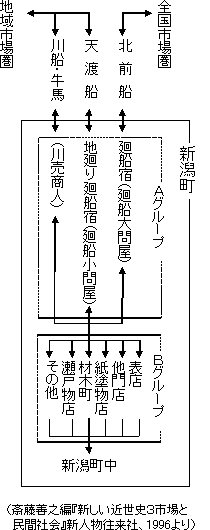水の風土記
海からたどる「商い」の時代史
〜現代地域経済圏の礎をつくった近世海運起業家〜
日本はまぎれもない海洋国です。明治時代に鉄道が現れるまで、各地で大量輸送を担っていたのは船でした。菱垣廻船、樽廻船、あるいは北前船などの言葉は高校生の教科書にも載っており、有名です。しかし、そのような船がどのような荷物を積み、どことどこを結び、船主はどのような商いをし、いかにして地域経済圏が育っていったのかは、意外と知られていません。 そこで、近世海運史に詳しい斎藤善之さんに、「海運−商い−地域経済の変化」の関係をうかがいました。
-

-
東北学院大学経済学部助教授
斎藤 善之 さいとう よしゆき -
1958年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科日本史専攻単位取得。早稲田大学文学部助手、日本福祉大学知多半島総合研究所嘱託研究員を経て現職。専門は日本近世史、海運港湾史。
主な著書に、『海の道、川の道』(山川出版社、2003)、『日本の時代史17近代の胎動』(吉川弘文館、2003、共著)、『新しい近世史3市場と民間社会』(新人物往来社、1996、編著)、『内海船と幕藩制市場の解体』(柏書房、1994)他。
海運史研究から日本社会がみえる
私が大学を終えて初めて赴任したのが、愛知県の知多半島・半田にある日本福祉大学でした。地域のことを研究したいと思っていましたので、当初は尾張・三河地域の経済史を江戸時代まで遡り調べたいと思っていました。それで知多半島を中心に史料調査を始めたところ、醸造家や海運商人(海商)の史料がたくさんあることがわかり、研究関心がしだいにそちらに向いていきました。海運というと、船とか航海術などに関心が集中しがちですが、私はむしろ運ばれる積荷商品に興味がありました。それらがどこで生産され、どのように運ばれ、どこで消費されていったのか、これを解明することで、単なる海運史にとどまらず、文化史や社会史や生活史といった世界まで豊かに見えてくるのではないか、と考えたからです。
つまり流通によって商品生産が盛んになった生産地は、そのことで地域の構造そのものが変わる。また消費地も、それまで無かった物資が送り込まれることによって、新たな消費が生まれ生活水準が変化して新しい文化が展開する。そして両者を繋ぐ流通勢力の興隆は、各地に港湾・流通都市を発達させ、独特な海運文化を展開させる、といったことです。
実際にこうした視点で海運を研究していくなかで、生産地から消費地までを総合的に捉えると同時に、社会全体のダイナミックな変化をリアルに捉えることができる、という仮説はしだいに確信に変わっていきました。そしてもうひとつ、伊勢湾海運史は、とりわけ「中部のものづくり」のルーツを解明する重要なカギではないか、という確信が生まれたことも、この研究にのめり込んでいく動機になりました。
とはいっても、例えばその後まもなくの1994年のことでしたが、こうした考え方を東京の歴史学の学会で発表したところ、討論で出された意見の大半は反論でした。その中心は「ローカルな海運が、全国の経済変動を引き起こすなどというのは、大それた話で到底承伏できない」といったものでした。しかしその後、賛同してくれる研究者も徐々に現れ、現在では若手研究者の間では、流通史の研究会もできてきて、次第にこうした考え方も受け入れられてきた感があります。
中部のモノづくりと伊勢湾海運
ところで名古屋のモノづくりは、いったいいつ頃まで遡ることができるのでしょうか。その原点のひとつは伊勢湾岸の古代製塩でしょう。塩づくりというのは単純なようで奥が深い。大量の燃料を使って海水を煮詰めるという過程は、実は様々な産業の原点のようなところがあります。
中世になると、知多半島では、その延長上に「常滑焼」の大量生産が始まり、さらに近世に入ると醸造業が飛躍的な展開をします。そのほか大野の鍛冶、岡田の木綿などもよく知られています。三河でも醸造とともに瓦製造が盛んになります。
ところで常滑の窯業も醸造業も、製品はみな重たい商品です。したがって海運と結びつかないと運べません。たとえば尾張地域の窯業産地としては、常滑だけではなく、内陸部に瀬戸や多治見などがあります。このうち常滑は海に面していたためか、大瓶など大型製品が多い。一方、瀬戸では「瀬戸物」という通り小型製品が多い。瀬戸から知多半島にいたるまで、原料となる陶土は帯状に分布しており、焼物の原料にさほど違いはありません。ただ海運と結びつくかどうかで「どこで何をつくるか」という製品のタイプが変わると考えられます。
こうして常滑では、大型製品に特化しました。あれだけの大瓶は、中世日本では常滑、瀬戸内の備前、日本海側で珠洲(現石川県珠洲市)でしか作れませんでした。それだけ高度な技術でもあったわけです。そのため常滑焼は、太平洋沿岸に広くもたらされ、とりわけ関東から東北太平洋岸で遺物が大量に発見されています。とくに平安末期に奥州を支配していた奥州藤原氏の拠点である平泉から膨大な量が出土しており、当時の広域流通を象徴するできごととして注目されています。
こうして常滑焼は、最初から地元向け製品だけではなく、全国製品として製造されていたという意味で、中部のモノづくりの原点らしい性格をもっていたと言えるでしょう。
ところで常滑が焼物で栄えると、知多半島の森林はいちはやく燃料として切り出されたものと思われますが、当然それだけでは足りなくて、三河や熊野の方からも船で運ばれてきていたでしょう。つまり海運があったので、地元で燃料資源が枯渇しても、遠くから安く大量に持ってこられるという利点がありました。
しかし技術だけはそう簡単に持ち運ぶことはできません。宮城県石巻市の近郊に水沼という場所があります。平泉に至る北上川水運と、尾張に至る太平洋海運が結びつく地点なのですが、ここに常滑焼の工人らが集団で移住し、現地生産をしたらしい痕跡が発掘で確認されました。海運によって、モノだけでなく、人の結びつき、交流が生まれていたのです。
中世の商人−水軍であり商人であり宗教勢力でもあった
ところで中世の常滑焼を運んだのはどのような人達だったのでしょうか。この点は興味深いけれども難しい問題です。中世史の永原慶二さんは、熊野の水軍勢力がそれにあたるのではと示唆されていました。当時、水軍は有事の姿であり、平時になれば彼らは商業や海運業などに従事したりしていました。中世では商人であっても武装して、自衛しなければ、商いや交易などとてもできませんでした。ですから商人も、支配者からみて味方側であれば水軍であり、敵側であれば海賊と呼ばれたりしました。
では熊野水軍によって常滑焼が伊勢湾から関東・東北地方へともたらされたとすると、どのようなルートでやってきたのかも当然問題になります。ここにも論争がありまして、江戸湾岸から内水面を利用して房総半島を横断し銚子や鹿島辺りで太平洋に出たという説と、房総半島の沿岸を廻ったという説とがあります。房総沖は海の難所として有名で、江戸時代になっても銚子から利根川を使った内陸水運ルートが使われましたので、中世ならなおのこと房総廻りなど無理であったというわけです。
このように学会の主流は内陸横断説のようですが、私は房総外廻り説をとりたいと思っています。房総外廻り説への反論は、要するに「江戸時代になっても房総沖の航路はなお難所であった。だから中世の船ではここを渡り切れたはずはない」というものですが、それは船と航海技術の発展がそのまま航路の拡大をもたらすという理解に基づいています。ところで中世から近世への商船への発展は、櫓走・帆走共用から帆走専用への移行であったことはすでに知られています。つまり中世の船は、帆走と櫓走を共用しており、たとえば房総沖も沿岸沿いに小刻みに航行することによって乗り切ることができる可能性がありました。ところが帆走専用とすることで乗組員を大幅に削減し経済性を大きく高めることに成功した近世の商船・千石船にとっては、この海域はむしろ航海困難な場所になってしまったといいます。
ところで熊野の海上勢力が奥州に到達していたことを窺わせる根拠のひとつとして、現在の宮城、福島の沿岸一帯に、熊野神社が多数分布し熊野信仰が盛んなことがあげられます。仙台のやや南の名取地域は、奥州有数の熊野信仰の拠点であったといわれます。
また熊野とは別の宗教勢力として、関東の香取・鹿島神宮の勢力も、奥州に足跡を残しています。例えば北上川の河口港の石巻や、阿武隈川の河口港の荒浜に鹿島神社がありますが、実は関東から仙台沿岸に至る太平洋沿岸の主な河川の河口地点には、鹿島・香取系の神社がかなり濃密に存在しているのです。そのことから私説ですが、これら神社そのものが、太平洋航路を支える寄港地として機能していたのではないかとみることもできます。つまり北太平洋の沿岸に点々と存在する河口の鹿島神社は、そこで補給を受けると関東から石巻あたりまで航海できる、つまり船の支援基地でもあったのではないかということです。ちなみに鎌倉・室町時代には、さまざまな宗教者が、手工業や商業や芸能活動にも従事していたことは、網野善彦さんの研究でも明らかにされています。
中世商人と近世商人の違い
このように中世では、商人とは、多面的な顔をもった存在でしたが、近世になると次第に商人としてより純化した存在になります。これが中世商人と近世商人が大きく違う点です。
中世の商人は、商人であると同時に、武士・海賊であり、宗教者であり、芸能者でもあるなど様々な顔をもっていました。中世では、資本を蓄え商品を輸送するためには、武力のほか、神仏の力、伝統の力などあらゆる力が必要とされたからです。熊野水軍もまた、熊野の御師との関係も指摘されています。
戦国時代には、商人は戦国大名と結び、時には道がない所にも兵粮を運び込むなどといった輸送にも従事しました。ですから自ら船や馬をもち、道や橋を造ったりして商品を輸送するだけの力すら備えた者もおりました。流通インフラが未熟な段階・地域においても自力で輸送を実現する力をもつような存在が必要とされたわけです。もちろん輸送のコストは全体としてかなり高くなりますが、それでよかった時代だったわけです。
これが近世になると、戦乱がなくなり、流通も軍事輸送から民生品輸送へと切り替わることになります。国内では流通インフラの整備が始まり、陸上交通では五街道が整備され、海上交通では東廻り航路、西廻り航路の整備も進む。こうなると中世商人のような力は、必要とされなくなります。様々な顔をもつ多面的な存在ではなく、商人に特化して、もっと安く商品を運ぶ純粋商人的なタイプが出てくるのです。
その過渡期、近世初頭に各地の港湾都市などを拠点として活躍したのは、いまだに中世商人の性格を濃厚に残した「初期豪商」といわれる商人でした。しかし交易路の整備がすすんだ結果、遠隔地間の商品価格差も下がり、そこから利益を得られる商人、すなわち近世商人への移行が急速に進展しました。こうした情勢のもと、初期豪商のうち何人かは近世商人への転身に成功しますが、ほとんどの者は転換できず、江戸時代の最初の50年ほどで衰退していきました。それ以降は、武士、農民、商人、宗教者といった職能の分離が進み、いわゆる近世商人が確立していくのです。
ちなみに、初期豪商から始まる江戸時代の商人像を、政治や市場、商人像や流通品と関連づけて時期的な類型としてまとめてみたものが次の図です。
近世(江戸時代)の商人の時期的類型(斎藤善之作成)
|
※________は、今日まで存続している商人・企業
新興商人の台頭
江戸時代中期、19世紀の前半になると、新しいタイプの商人が登場してきます。ちょうどこの頃、各地の特産物生産が発展し、その輸送を担う新興勢力として、特権的な商人や流通勢力の外側から出現してくるのです。例えば、江戸時代前期までは、江戸・大坂・京都などいわゆる三都が日本の流通構造の頂点として君臨していたのですが、江戸時代後期になると。江戸では浦賀や神奈川、大坂では兵庫や堺、名古屋(熱田)では四日市や常滑・半田などがそれにあたります。これらの新興流通都市は、単独ではなく、地域ごとにネットワークとして機能するようになるのです。また江戸時代前半には、流通商品の主流は領主階級向け商品でしたが、江戸時代後半になると民需向け商品が増えてくるのです。そうした新興商人は、生産者や消費者を中心とする地域経済と密接に繋がっていますので、顧客主義というか市場原理の経営哲学を持つようになります。北前船や尾州廻船はそうしたタイプの象徴で、そこから近代地域産業の育成者などが多数輩出されるのも、そのような特質と関連していると考えます。そしてそうした潮流のなかに、ミツカン中埜家の誕生と飛躍もみられるわけです。
他方、それまで特権を認められていた御用商人の側では、新興商人に押されて後退していきますが、多くの場合、新興商人と競争することはせず、領主に新興商人の活動を抑えてほしいなどと嘆願することが多いのです。領主の庇護を受けてきた御用商人は、地域経済に目が向いていません。殿様商売と言われてしまいます。
このように近世後期に、新しいタイプの商人が全国的に出現してくることの意味を、もっと考えるべきです。そうすると近代日本経済の見方も変わります。三井や三菱をはじめとする財閥系の商家からみた近代経済史ではなく、地域を拠点に活動する商人たちの歴史にこそ、今日の日本経済の強さや豊かさの源泉だと考えるのですが、どうでしょうか。
重層的な海運のネットワーク
江戸時代の前半の主力海運勢力だった菱垣廻船(江戸−大坂を結んでいた)は、最盛期の享保年間の船数200艘。菱垣廻船から分かれた樽廻船は、最盛期の寛政年間で160艘ほどであったことがわかっています。しかしその後、近世後期にかけて菱垣廻船・樽廻船ともに船数は減少気味となります。しかし近世後期に向けて、日本の物流量は明らかに増大しており、その担い手がどのような海運勢力であったのか、これまでほとんど問われてきませんでした。私は、これこそ北前船と尾州廻船、そして奥筋廻船であったと考えています。北前船は北海道から上方までの日本海航路に就航した船、尾州廻船は上方から江戸までの太平洋航路に就航した船、そして奥筋廻船とは、北海道から江戸までの太平洋航路に就航した船でした。この3つの海運勢力によって、日本列島はほぼ全周をカバーできます。しかも3つの海運勢力とも、天保期以降に飛躍的に勢力を増大しているのです。
これら新興海運勢力は、どのような流通圏を作り出していたのか、これを窺わせる興味深い事例があります。越後国(新潟県)に岩船という古くからの港があるのですが、ここに明治初年の入港・出航船の記録が残されています。これを分析してみたところ、この港に出入りした船はほとんどが10石から20石積で、小型帆船でした。地元ではこの船を「天渡船(てんとうせん)」と呼んでいました。岩船港の天渡船の航海圏が興味深いことに、南限は新潟、北限はと酒田・加茂で、その間の浦々を緊密に結んでいました。いっぽう全国規模の航海圏をもつ北前船は、新潟に寄港すると次に寄港するのが加茂・酒田でした。このことから、北前船の寄港地の両端で完結する地域市場圏に天渡船という存在があったことがわかります。つまり全国規模の北前船と、ローカルな天渡船とが重層的な市場構造を作っていたことが判明したのです。ちなみに近世中期までは、近距離輸送も遠距離輸送も同じ規模で船が就航していたようです。つまり市場は単層構造でした。それが近世後期になると遠距離輸送に従事する大型船と、近距離輸送に従事する小型船とが分化していったわけです。さらに新潟と酒田は、大きな川の河口に位置しており、河川舟運とも結びつく場所だったことも忘れることはできません。
このように重層的な市場圏が交差する新潟や酒田といった拠点港では、全国流通と地域流通がどのように結びつくのか、そこのところが大きな問題です。これについては新潟において、ある程度実態を解明することができました。江戸時代後期において、新潟港では、商品の流れは次のような構造になっていたことがわかりました。
運賃積みと買積−運送をめぐるリスク負担と情報収集
近世前期の菱垣廻船や樽廻船は「運賃積」で、今日の輸送業と同様、行先を指示されて輸送し、運賃をもらいます。船側の都合で、勝手に目的地を変更したりするわけにはいきません。ところが、近世後期に勢力を拡大する北前船・尾州廻船・奥筋廻船といった振興会運勢力は、「買積」といって、積荷を自分荷物として買い取ってしまう経営形態をとっていました。ですから何を積むか、積荷をどこに降ろすかは、船側の裁量にまかされていましたこのタイプの商船を買積船といいますが、運賃積船に比べて、より大きく市場原理が作用するようになりした。運賃積にくらべて買積は、ハイリスク・ハイリターンであって、たとえば北前船では、蝦夷地から大坂までの1航海で千両近くの利益があったといいます。
いっぽう買積船では、海難事故による損害も全て船主負担となります。運賃積船の場合、荷主が海損を協同負担する形態がとられておりました。この協同海損のシステムは、海上保険の先行形態といえるものでした。
また尾張国(愛知県)知多半島の内海を拠点とした尾州廻船・内海船では、船主同士で仲間組織である「戎講(えびすこう)」を結成していました。一船主では解決できない諸問題に対して、船主たちが協同で処理にあたり、営業環境の整備に努めていました。尾州廻船の飛躍的発展の背景には、この戎講の力があったと考えています。
また買積船の経営では、各地の商品価格すなわち相場情報を迅速に収集する力がものをいいました。これには伝統的な情報伝達手段、すなわち書状や口達が使われました。ただその密度や速度は、一般に考えられているよりもはるかに濃密で迅速でした。例えば北前船では、地域ごとに寄港地がほぼ決まっており、寄港地ごとに取引先の廻船問屋も決まっていました。各地の廻船問屋では、情報をあらかじめ集めておき、船の入港に備えます。
例えば、瀬戸内各地の相場情報は、瀬戸内の入口にあたる赤間関(下関)あたりの廻船問屋で集中しており、北前船はここに立ち寄って、その後瀬戸内のどこに向かうかを判断するのです。いっぽう船主が航海中の自分の手船に連絡したいときは、船が寄港しそうな廻船問屋あてに手紙を出しておき、廻船問屋では船を動きを捉えながらその手紙を転送していくのです。
教養ある船乗りたちが切り開いた近代日本
いまは東北地域の地元の古文書史料を探し、解読したり分析したりして、東北の海運勢力である奥筋廻船の実態を解明することに努めています。例えば石巻の奥筋廻船の船主に平塚八太夫(1805年生まれ)という人物がいました。この人が残した記録の中に「萬記録覚帳(よろずきろくおぼえちょう)」という史料があります。那珂湊の豪商に雇われて沖船頭をしていた頃から、独立して船主になるまでの記録なのですが、一介の雇われ船頭が船主へと成長する過程が克明に記された貴重な記録です。
たいへん興味深いのは、独立の直前に、江戸で蔵書を買いそろえていることです。船乗りというと荒くれ者のようにいわれておりますが、当時の船主や船頭は、それなりの教養がないとつとまらないのです。廻船の船頭の日記をみると、句や歌を詠んだりと教養豊かであることが窺えます。
平塚八太夫もそうした教養の持ち主であったことを知ることができます。平塚家は、蝦夷地で鮭を仕入れ、東北・関東で売るという買積経営を展開、石巻田代に本店を、箱館に支店を開設、とくに箱館の支店は後に大きく発展していきます。この支配人は平塚時蔵という人でしたが、蓄積した富を地元箱館の様々な社会事業へと投資・還元し、その貢献ぶりから「函館四天王」と称されるようになる人物です。さらにこの家が生んだ人物、平塚常治郎は、新潟出身の堤清六という冒険的商人と意気投合して、カラフト・オホーツク漁場へと進出し、やがて日魯漁業の創始者となります。つまり北洋漁業の開拓者をも生み出していくのです。
その他に、例えば北前船の代表的船主であった右近家は、日本海上火災保険を起こしていたり、また尾州廻船からはミツカン中埜家などを生み出すことを見ても、近世後期に登場する新興の地域の海商・海運企業家は、日本の産業近代化の中で重要な役割を果たしていくのです。日本の経済史では、中央で活躍した渋澤栄一や益田孝、また三井・三菱のような財閥系企業ばかりが取り上げられますが、実際に日本の近代化を土台で支えていたのは、地域の産業資本家たちであり、彼らはもっと高く評価されるべきだと考えています。
(2004年8月9日)