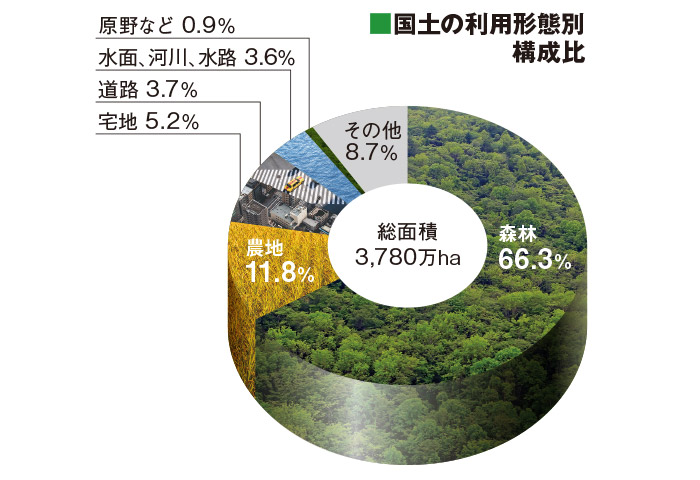機関誌『水の文化』66号

概論
日本人は自然を相手にどう生きてきたのか
人は自らの生息域を広げようと、山から平野、海辺へと進出してきた。時代の流れとともに人が集う場所はどう変わってきたのか。そして、集落という単位で生きていくために、水をどう扱ってきたのか。哲学者の内山節さんに、人が水を治めることと地域社会の関係の遷り変わりについてお聞きした。
-

-
インタビュー
哲学者
NPO法人 森づくりフォーラム代表理事
内山 節(うちやま たかし)さん -
1950年東京生まれ。1970年代から東京と群馬県の山村・上野村との二重生活を続ける。『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』『貨幣の思想史』『「里」という思想』『新・幸福論―「近現代」の次に来るもの』『内山節著作集(全15巻)』など著書多数。
土地を選んだ条件は「日当たり」「水」「安全」
昔の人間がどこに住んでいたかというと、日当たりがよくて、飲み水が確保できて、かつ災害に遭いにくい場所です。今も山奥に行くと「なんでこんなところに住んだのだろう?」と思うような場所に小さな集落が残っています。山の中腹なので日当たりがよく、近くに湧き水があり、大きな河川から離れているので水害も起きにくい。人々はそういう土地を見つけては移り住み、暮らしてきました。
人口が増えると、徐々に標高が低い場所、川のそばなど危ないところにも進出していきます。日本は暴れ川が多いので、大雨でも氾濫原にならない山すそ付近、あるいは河川が小規模で水害が起きにくい場所を選んでいました。古代政権が成立した大和盆地は紀の川水系ですが、大きな川ではありません。安全な土地なので有力豪族が発生したと考えてよいでしょう。海の近くに住む場合は、丘のような高台に集落をつくりました。これも災害を避けるためです。
私たちが農村景観と捉える平野に田畑が広がる場所は、実は江戸期に成立したものが多いのです。その典型は日本海側。江戸期はそれぞれの地域で海岸林をつくっていったはずなのに、青森から山口までつながっていますね。日本の川は、今でこそ流路が固定されているので海へ流れていきますが、もともとは海の水も混じった沼地に入り込んでいました。どこまでが川で、どこからが海かよくわからないような状態ですね。
その原因の一つが風です。風が海岸の砂を巻き上げて陸側に落とすと、そこで川がせき止められて水溜まりのようになっていく。ですから、まずは砂を飛ばす風を止めなければならなかったのです。海岸林は、砂が飛ぶのを防ぐ役割でつくられました。
水はありがたいものではあるけれど、人が住む場所を広げようとすると大変な苦労を強いられます。新潟平野などは沼地だらけでしたから、水を抜いて干拓しました。田んぼに水を入れる水利だけでなく、水を抜く水利も必要でした。
地元で話し合って水を治めた
その土地に水をどう取り込み、どう処理するかは、江戸期まで「地元の発案」が主でした。中心になるのは庄屋クラスの人たちで、村の人たちとともにある程度までは自力でやりますが、人を雇ったり費用がかさむ場合は藩や幕府に相談しました。藩や幕府も石高が増えるのは悪い話ではないので、うまく交渉すれば資金を提供してもらえました。
当時の人たちの、水を使う、あるいは治めるための「見る目」は大したものでした。信濃川の大河津分水路は1931年(昭和6)の完成ですが、計画そのものは江戸中期の享保年間(1716−1736)からあったのです。当時の人たちが「新潟平野の洪水を止めるには、あそこで分水するしかない」と標高差も含めて考えたんですね。
鹿児島県鹿屋市(かのや)に、マテバシイの枝を刈って束ねて置いて取水する「柴井堰(しばいぜき)」(注)があります。農業用水を得るためだけならコンクリートの可動堰にすればよいのですが、あえて続けることで「来月の何日にやろう」と相談したり、若い人は技をもつ人にやり方を教わる。終わったらお酒も飲むでしょう。それがまた地域をつくっていくことになる。
水の脅威から逃れる、あるいは水を確保する方法をその土地に住んでいる人が考え、話し合い、資金も調達する。水を治めることは、たんなる水量管理ではなく、地域づくりと分離できないものでした。
(注)柴井堰
『水の文化』60号の特集「水の守人」にて掲載。
伝統保存か近代化か── 選択を迫られる「柴井堰」
自分たちで選んだ集落の「水役人」
日本の農村は、どちらかというと水不足の社会です。水は豊富なように見えますが、谷底を流れている川からは水を汲み上げることはできません。生活用水なら桶に組んで天秤棒で担いで、ということもできなくはないですが、農業用水としては足りません。
そこで集落の上流で取水して、長い用水路をつくって水を引いてきます。ところが水路は土ですから、水がしみ込んでしまう。取水口で得た水が田んぼに到着するときには半分ほどになってしまう。そこで粘土質の土を持ってきてしみ込みやすい場所を固めるということをずっとやってきました。
そんな状態ですから、ちょっと渇水になるとたちまち水が足りなくなります。水田をもつ集落にとって水の分配は死活問題です。みんな自分の田には水が欲しいので、話し合いでは決まりません。ではどうしたか?集落が独自に「水役人」を立て、水の分配をその人に一任したのです。水役人の生活は集落が保障しました。
水役人は、みんなが「あの人なら公平に考えてくれる」と信頼できる人物で、しかもこれから雨が降るのか降らないのか予想できるほど自然のことにも精通していました。水を止めているうちに腐らせてしまっては元も子もないので、稲に関する知識も豊富でした。
水役人はお年寄りが務めることが多かったようです。弟子を養成している地域もありました。弟子が予想以上に早く一人前になり、師匠も元気な場合、他の集落から「師匠をうちにもらえないだろうか」と声がかかる。そういうネットワークもあったのです。師匠はよその集落に引っ越して水役人となり、そこでも弟子を養成するということが各地で行なわれました。
これは水の分配に限ったことではありません。今、農村では獣害が問題になっていますが、江戸期はもっとひどかった。そこで村専用の猟師を立て、彼らに一年中動物を追いかけてもらう代わりに、賃金にあたるものは村で保障しました。漁師には鉄砲が必要ですので、庄屋が藩と交渉します。ほとんどの藩が「わかった。30丁渡そう」などと許可しました。もちろん鉄砲はご法度ですが、幕府は黙認します。
かつて、役人とはその名の通り「一つの役をやる人」でした。地元の人は、必要だと思えばこうした役人を自分たちで立てていたのです。
したたかに進めた藩・幕府との交渉
江戸期は、基本的に正規の役人が地元にはいません。代官所や郡奉行は遠いうえ、彼らも勝手に村に入ることはできず「○月○日に行く」と通達してからやってくる。
今は、田んぼや畑のことを一括りに田畑(たはた)といいますが、もともとは田畑と畑田(はただ)がありました。田畑は、水が豊富な年は水田にしますが、水があまり豊富ではないと判断すると畑にする。畑田は、普段は畑だけれど水が豊富な年だけ田んぼにする。春にその年の気候を読んで判断しました。これも一種の水調整です。
そして、これは年貢のごまかしの手段でもあった。畑は年貢がかからない場合が多いので、代官には「ここは畑でございます」と言うけれど、実際には田んぼにしているケースがよくありました。また、「隠し田」とは、山奥の見えないところにひっそり田んぼをつくっているのではなくて、誰が見てもわかるところにあった。領主には「ここは遊水地でございます。大雨の時に水が溜まる場所に過ぎません」と言う。「稲があるではないか!」と指摘されても「上流から流れてきたものが、たまたま根を張ってしまったようですね」とごまかします。そうして年貢をできるだけ回避しようとしていたのです。
それでも罰金をとられることはありました。20両支払えといわれたらしかたがないと、庄屋が村人からお金を集めて支払うわけです。ところが、この20両は必ずあとで戻ってきます。領主は「お前たちがごまかすのは水路が不完全で水が安定しないからだろう。この金で水路を改修しなさい」と20両を差し出す。それがわかっているから村人も罰金に応じたのです。
このように当時の村人は「はい、わかりました」と答えるものの、従う気はまったくなかった。面従腹背ですね。一方、藩もあまり強硬に事を進めて一揆が起きると困るので、適当なところで収めるしかない。農民にはそれほどの力があったわけです。
田畑と畑田の使い分け、隠し田のあり方など、江戸期の自治は実に巧妙でした。それは、水や災害対策などその土地で暮らすために必要なことを、すべて自分たちの手でやっていたからなのです。
水を治める権利は地域から国へ
ところが、明治時代になると地元が手を出せなくなります。川を治める権利を、国が地元の人から取り上げたからと言ってもいいでしょう。そのあたりから地域社会がおかしくなります。
もちろん、明治時代も悪いことばかりだったわけではありません。西洋技術が導入されたことで、例えば揚水ポンプで川の水を汲み上げて、水が得られるようになった地域があります。また、水利組合がつくられたことで、複数の地域の合意と協力がなければできなかった大河津分水路のような大工事も進みました。
劇的に変わったのは、1952年(昭和27)に国産のコンクリートミキサー車が登場してからです。それまでコンクリートは現場で人の手でこねていました。ところがミキサー車が登場すると、大量かつ安価にコンクリートが使えるようになります。それで「コンクリを打っておけば大丈夫」という神話が生まれ、川だけでなく自然環境そのものがつくりかえられ、地域社会はさらに崩れていきました。
ただし、農業用水に限っていえば、水の分配だけは地元でやっているケースが最近まで各地にありました。その水の分配が地域社会を辛うじて保っていた。ところが、圃場(ほじょう)整備が進んで水路が暗渠(あんきょ)になり、水が目につかなくなる。つまり、田んぼの水さえ都市の水道の水と同じような存在になったのです。水を治めてどう生きていくかが抜け落ちるので、見た目は農村景観であるけれど、農村的地域社会ではなくなっているわけです。
これをどうにかするには、川を含めた自然を治めていく権限を、地域の人たちが昔のように自らの手に取り戻すことだと思います。今のしくみだと、住民は要求しかできない。住民が管理設計できるようにはなっていないのです。
かつては地域の人が発案し、それを藩や幕府が応援して地域社会が成り立っていました。もちろん、県や国は出てくるな、ということではありません。「主導権は地元の人たちにある」ということを尊重できる社会にどう戻していくのかが論点です。
水とどう生きるかが地域社会を左右する
皆さんは、「地域」といわれてどういう範囲を思い浮かべますか。
私は群馬県の上野村で暮らしていますが、隣の村の人とも付き合っていますし、買い物は近くの都市部へ出かけます。このように、時と場合によって地域の範囲は変わるものです。地域という言葉はもっと重層的な概念であるべきだと思いますし、その重層的な構造こそが本来の社会の姿だと言ってもよいでしょう。
ところが、明治時代以降の日本は、中央集権国家としてあらゆるレベルで全国的な一元化を推し進めました。それによって、地域の独自性はどんどん失われていきます。今日(こんにち)では、地域という言葉は市区町村という行政単位と一緒になってしまった。その結果、一人ひとりが孤立して、「行政に管理されている個々の存在」となっています。
先人たちがもっと立体的な地域社会で手を携えて生きていたことを、私たちは思い出すべきです。そして、地域社会の基本をつくっていた軸の一つが「水」だったことも忘れてはなりません。
自分たちの地域の水管理はこうあるべき、自分たちの地域の水害対策はこうあるべきということを自ら発案し、社会を形成していこうと考える──。それが今、もっとも必要なことだと思います。
(2020年8月25日取材)