水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
藻から生まれる「石油に代わる燃料」〜可能性秘める藻類バイオマスエネルギー〜
2014年01月21日
鈴木 石根 すずき いわね
筑波大学 生命環境系 生命環境科学研究科 環境バイオマス共生学専攻 教授
藻類バイオマス・エネルギーシステム研究拠点 代表今の私たちの暮らしは、石油や石炭といった化石燃料に頼っています。しかし、化石燃料は限りがあるうえ、利用することによって排出される二酸化炭素による地球温暖化や窒素酸化物による酸性雨など、さまざまな環境問題の要因ともな...
-
-
-

-
アカミミガメ1匹で入園無料に〜外来生物問題に一石を投じる施策〜
2014年01月15日
亀崎 直樹 かめざき なおき
神戸市立須磨海浜水族園 園長 日本ウミガメ協議会 元会長「ミドリガメ」と呼ばれ、ペットとして親しまれてきたミシシッピアカミミガメ(以下、アカミミガメ)。成長すると甲長30cmほどになる北米原産の外来生物です。日本の湖沼や河川で増え続け、生態系を乱す存在として問題になって...
-
-
-

-
第15回里川文化塾 拡がる雨水利用
2013年12月06日
まちを潤し、緑を育む雨は、まさに「空からの贈り物」です。雨水に着目して約30年前からさまざまな取り組みを進めてきた東京都墨田区は「雨水利用の先進都市」といわれています。雨水を貴重な水資源と考えて、暮らしに結びつける墨田区の取り組みを見聞きすることで、雨水利用の可能性について...
-
-
-
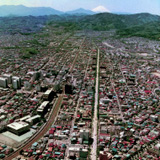
-
第14回里川文化塾 大久保長安・八王子の治水とまちづくり
2013年12月02日
ミツカン水の文化センターでは、「使いながら守る水循環」を学ぶワークショップ「里川文化塾」を行なっています。第14回は、大久保長安が築いた宿場町〈八王子〉の成り立ちと風土を検証しました。大久保長安が八王子で行なった治水と利水とまちづくりを例に取り、地域の宝を掘り起こし、どう生...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』45号 雪の恵み 水神様を祀るかまくら
2013年11月01日
照井 吉仁 てるい よしひと
横手市観光協会 かまくら委員会委員長14万〜17万人もの人が訪れる横手のかまくら祭は、「なければ生きていかれないのにあって当たり前だと思っているもの」に感謝する日でもあると、照井吉仁さん。さまざまな時代の洗礼を受けながらも、雪を楽しむ気持ち...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』45号 雪の恵み 札幌市と歩んだ〈さっぽろ雪まつり〉
2013年11月01日
齊藤 洋平 さいとう ようへい
一般社団法人札幌観光協会事業・イベントグループ統括係長〈さっぽろ雪まつり〉は2014年(平成26)に65回目を迎えます。市民の雪捨て場でささやかに始められた〈さっぽろ雪まつり〉は、世界中から人が集まる経済効果250億円の一大イベントに成長しました。マンネリ化...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』45号 雪の恵み 日本の雪道とスタッドレスタイヤ
2013年11月01日
土橋 健介 どばし けんすけ
株式会社ブリヂストン ウィンタータイヤ開発部ユニットリーダー昼間の気温が上がることで、融けた雪が氷やシャーベット状になる日本。雪道だったり、凍っていたり、除雪道だったり。日本の路面はさまざまな状態が同時期に交錯しています。このような特殊性に鍛えられ、日本のスタッド...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』45号 雪の恵み 新エネルギーとしての雪資源 克雪から利雪へ
2013年11月01日
媚山 政良 こびやま まさよし
室蘭工業大学大学院工学研究科教授 工学博士雪は、人間の基本的な生存権を大事にする〈環境未来都市〉をつくるのに有効だ、というのが媚山政良さんの考えです。視線の先には、いつも人の暮らしがある媚山さん。現代技術や科学を駆使することで、雪がいかに人の暮ら...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』45号 雪の恵み 最新の冷熱エネルギー活用 利雪の家
2013年11月01日
山田 正人 やまだ まさと
有限会社山良工務店代表取締役雪を貯蔵して、夏の冷房に活用している住宅があります。モチベーションを高めているのは、環境意識。システム導入にはコストがかかりますが、融けて消えてしまう雪が、エネルギーとして充分活用できることがわかりました...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』45号 雪の恵み 快適な北方都市の創造〈世界冬の都市市長会〉
2013年11月01日
今井 啓二 いまい けいじ
札幌市総務局国際部長〈世界冬の都市市長会〉の活動をご存知でしょうか。「冬は資源であり、財産である」というスローガンを掲げ、課題解決や冬の都市ならではの知恵を分かち合ってきました。ひと冬に6mの降雪があるのに多くの人口を抱え、...
-
