水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
第11回里川文化塾 野川を歩く〜都市河川の再生を考える〜
2013年06月07日
国分寺崖線(がいせん)からの湧水を集め多摩川に注ぐ長さ20kmほどの野川は、水車が点在するほど水量豊かな川でした。しかし、高度成長期に生活雑排水が流入してドブ川となってしまいます。下水道整備が進み、また積極的な市民の活動によってかつての清流を取り戻しましたが、現在は都市化の...
-
-
-

-
農業が自立しなければ国民は不幸になる〜農産物直売所「みずほの村市場」の挑戦〜
2013年06月07日
長谷川 久夫 はせがわ ひさお
農業法人株式会社みずほ代表
株式会社ELF代表取締役茨城県つくば市にある農産物直売所「みずほの村市場」には、週末には駐車場に車が入りきらないほどの人が押し寄せます。農家の意識改革を促し〈経営者〉にすることで、農業の〈産業化〉を目指す長谷川久夫さんは、厳格なルールを定...
-
-
-

-
自噴地下水〈うちぬき〉の恵みと保全〜「あって当たり前」からの脱却を図る西条市〜
2013年05月23日
愛媛県西条市
〈うちぬき〉という言葉をご存じですか?愛媛県西条市には、鉄のパイプを15mから30mほど打ち込むだけで良質な地下水が湧き出てくる地域があります。そうした自噴井(じふんせい)や自噴水を〈うちぬき〉と呼んでいるのです。...
-
-
-

-
ウナギにまつわるすべての謎を解き明かしたい〜ウナギ研究最前線と資源保護について〜
2013年04月03日
青山 潤 あおやま じゅん
東京大学大気海洋研究所
海洋アライアンス連携研究分野 特任准教授ウナギは日本人にとって非常に身近な魚です。しかしその生態は謎に満ちています。例えば、人類が初めてウナギの卵を見つけたのはほんの数年前です。その発見に携わった青山さんは、ウナギの謎を解き明かすために、世界中を駆け回っ...
-
-
-
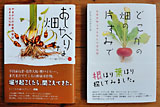
-
機関誌『水の文化』43号 庄内の農力 種を守る人々 山形に息づく在来作物の多様性
2013年02月28日
江頭 宏昌 えがしら ひろあき
山形大学農学部 食料生命環境学科 准教授 農学博士農学博士の青葉高先生が遺した「野菜の在来品種は生きた文化財」という言葉と、KJ法を考案した川喜田二郎先生の提唱した「〈野外科学〉的アプローチの重要性」に後押しされ、在来作物研究に取り組んできた江頭宏昌さん...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』43号 庄内の農力 藩校〈致道館〉に見る庄内人気質
2013年02月28日
酒井 忠久 さかい ただひさ
公益財団法人致道博物館代表理事、館長明治維新前後の動乱期には、武士の誇りと藩主を大事にし、会津藩とともに幕府のために、最後まで闘った庄内藩。人智に長けて真面目で堅実、しかし、柔軟性がある—庄内人のそうした気質は、この地を豊かに育んできた原動...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』43号 庄内の農力 目指せ、善福寺川再生! 荻小学校から始まった川へのアプローチ
2013年02月28日
編集部
学校の中を川が流れている、そんなすごい小学校が東京都杉並区にあります。井荻小学校の校庭には善福寺川が流れ、かつて子どもたちは自由に川を行き来していました。現在は、簡単に川に入ることはできませんが、井荻小学...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』43号 庄内の農力 赤川の流れを追う
2013年02月28日
古賀 邦雄 こが くにお
古賀河川図書館長 水・河川・湖沼関係文献研究会山形県の河川は最上川水系、赤川水系、荒川水系、摩耶山水系群、鳥海山水系群の五つに大別される。赤川水系は、灌漑用の大鳥池に発する大鳥川と月山、湯殿山並びに朝日連峰に発する梵字川との二大支流が朝日村落合地内で...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』43号 庄内の農力 庄内砂丘の水とメロン栽培
2013年02月28日
菊池 常俊 きくち つねとし
山形県庄内総合支庁産業経済部農村計画課 農林技監(兼)農村計画課長実際に防砂・防風林の中を歩いて、海まで出てみました。普通の海岸の松林を想像しては、大間違い。原始林のような力強さに圧倒されます。何世代にもわたって、営々と植樹されてきたクロマツが幾重にも梢を伸ばして、砂と...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』43号 庄内の農力 庄内の米づくり つや姫誕生までの道のり
2013年02月28日
冨樫 達喜 とがし たつき
因幡堰土地改良区理事長私たち消費者は、毎日当たり前のように米を食べています。しかし、生産の現場では、しのぎを削る努力を持って米が生産されていることを、冨樫達喜さんたちに教えていただきました。庄内では、米が早くから換金作物として...
-
