水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) コラート高原の溜池から見る タイ社会の移り変わり
2003年04月03日
森田 敦郎 もりた あつろう
東京大学大学院総合文化研究科博士課程、 日本学術振興会特別研究員「この村にわしらが移住してきたのは、ここに大きな池があったからだ。ほら小学校の前に池があるだろう。あそこに池があったから、わしらはここに村を建てることにしたんだ。あのころここは水が豊かで、ウドムソンブーン...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 微笑みの国 タイ
2003年04月03日
所澤 さやか しょざわ さやか
タイの大都会、バンコクに住んで驚いたのは、家では料理をしない人が圧倒的に多いということだ。日本でも、最近はコンビニエンスストアと安い外食産業の発達で、自宅にまな板がない人とか、包丁を持っていない人とかがい...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 輪中の智恵を伝える リスクコミュニケーション 木曽三川の「輪中根性」を「水防文化」に昇華する
2003年04月03日
編集部
長島、大垣は、ともに木曽三川によるデルタ地帯に広がる輪中の地として知られる所。輪中といえば、小学校のときに習った「堤防に囲まれた、水屋のある家々」を思い出すが、実はそんな数行の説明では語りきれない、多くの...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 《アジアの水》
2003年04月03日
古賀 邦雄 こが くにお
水・河川・湖沼関係文献研究会アジアの国々は歴史、民族、気候とそれぞれ異なるものの、水の文化については「水の神」「水辺空間」「灌漑農業」に関する書が数多く刊行されている。那谷敏郎著『龍と蛇〈ナーガ〉』(集英社、2000年)は、龍蛇ナー...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 雨期の世界単位
2003年04月03日
高谷 好一 たかや こういち
滋賀県立大学人間文化学部教授1960年代にはルースリー・ストラクチャード・ソサエティ(ゆるやかな構造をもった社会)という言葉が大流行でした。日本とタイの社会を比較して、J・F・エンブリーが日本はタイト(きっちりした)、タイはルース(...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 満水のタイ写真紀行
2003年04月03日
編集部
雨期が終わった11月のバンコクは、気温も低くなって、ようやく過ごしやすい季節を迎える。つまり、夜寝るときにクーラーを入れる必要のない気温になってきているのだが、タイの人たちは寒い寒いと言ってジャンパーを着...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 水資源 開発と保全のあいだ
2003年04月03日
中島 正博 なかしま まさひろ
広島市立大学国際学部教授――これまでの仕事の内容についてうかがえますか。私は、大学では農業水利(灌漑、排水等)を勉強し、アメリカで水資源計画を専攻しました。その後日本に戻り、(財)国際開発センターに入り、開発計画づくりや、政府開...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) アジアの水辺から見えてくる水の文化 タイ中部の水辺の住いと暮らし
2003年04月03日
アジアまち居住研究会
2002年の夏は世界の各地で洪水の被害が相次いだ。とくに被害が大きかった中国、チェコ、ドイツ、オーストリア、ロシアは、日本のニュースでも取り上げられて記憶に新しい。洪水による被災者は、この20年間で7倍に...
-
-
-
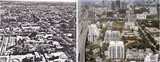
-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 地域プランナーが語る水の国タイ 開発におけるテクノロジーと習慣の共存
2003年04月03日
スワッタナー・タダニティー
チュラロンコーン大学社会調査研究所副所長・ 建築学部都市地域計画学科助教授――タイ国土の開発史の中で、チャオプラヤー川の占める位置についてうかがいたいと思います。日本では水が町にあふれたら、災害ととらえます。すぐに堤防を造り、水を遠ざけようとします。ところが、こちらに来て驚いた...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 《井戸》
2002年12月06日
古賀 邦雄 こが くにお
水・河川・湖沼関係文献研究会2002年9月現在、アフガニスタンは長年の戦乱と大旱魃を受けて、人々はいのちの源、水に難儀する日々が続いている。先日のテレビで「なによりも、水が欲しい」とアフガニスタンの子の訴える姿は、今でも脳裏から離れ...
-
