水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 盆地京都を庭園都市と見立てる 庭園は総合生活空間
2003年09月16日
白幡 洋三郎 しらはた ようざぶろう
国際日本文化研究センター教授NHKが『アジア古都物語‐京都千年の水脈』(日本放送出版協会、2002)の中で、地下水盆の上に平安京の都市発展があったというこれまでにない京都像を描いています。京都以外にも日本全国の盆地で、水とともに生き...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 領域感覚からの発見は何を生み出すのだろう 「何を見る」というよりは「どこから見る」
2003年09月16日
樋口 忠彦 ひぐち ただひこ
京都大学大学院教授私は、景観論の中でも「生息地景観論」というものに興味を持っています。『景観の構造』という本を約30年前に出したきっかけは、日本人がどんな場所を好んで住んできたのか、日本の都がどのような所に置かれ、その理由...
-
-
-
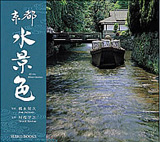
-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 《京都の水》
2003年09月16日
古賀 邦雄 こが くにお
水・河川・湖沼関係文献研究会「やがて山紫水明という言葉が感覚的にぴったりするようになる頃に平安京という都がこの盆地に出現した。今から千二百年ほどの前のことである。建設の指令者である桓武天皇は自分の理想とする土地を発見してさぞ満足をお...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 夏の京都 水風景
2003年09月16日
松井 惠 まつい めぐみ
京都環境アクションネットワーク代表6月の終わりから7月始め、京の町家ではふすまを夏の簾戸に替え畳の上には籐の敷物を敷く。軒先には簾をかけ陽が差し込まないようにする。表の格子戸から奥の庭に至るまで風が吹き抜けるように考えられている。梅雨も開...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 新聞発行から学ぶこころ言葉 第3回世界水フォーラムを取材する「水っ子新聞」
2003年09月16日
編集部
8日間に渡り国内外2万名以上の参加者が意見を戦わせた、第3回世界水フォーラム。その会場では、青と白のジャンパーを着て首からプレスカードを下げた子どもたちが取材に走っていました。彼らは「水っ子新聞」の子供特...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 歴史人口学から見た京都 水と町衆が生み出す暮らしの勢い
2003年09月16日
浜野 潔 はまの きよし
関西大学経済学部教授――浜野さんと京都の関わりからお話をうかがえますか。私は、京都をフィールドに歴史人口学という学問を専攻しています。これは昔の史料をもとに、出生や死亡、結婚、移動、家族など人口にまつわる事柄を調べようという...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 盆地都市と水の文化
2003年09月16日
米山 俊直 よねやま としなお
大手前大学学長、 京都大学名誉教授、 淀川水系流域委員会猪名川部会長京都は、冬は底冷えが厳しく、夏は蒸し暑い、と文学者たちが書いている。それは他所から京見物に訪れる人々の共通の感覚で、江戸時代の滝沢馬琴あたりまでさかのぼることができる。これは、盆地の典型的な気象である。た...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』14号 京都の謎 第3回世界水フォーラム報告
2003年09月16日
編集部
2003年3月16日(日)〜23日(日)の8日間にわたり第3回世界水フォーラムが、京都、滋賀、大阪という琵琶湖・淀川流域の3都市で開催された。参加者は世界約180カ国より24000名に及んだ。世界水フォー...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) チャオプラヤー川流域の近代物流史 水辺空間の価値を変えた交通モード
2003年04月03日
柿崎 一郎 かきざき いちろう
横浜市立大学国際文化学部講師――柿崎さんが、タイとかかわり始めたきっかけを教えてください。父親がタイに赴任したことで、中学校時代に3年間をタイで過ごしました。のちに進路を決めるときに、タイにかかわる研究がしたいと思ったのですが、元来...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』13号 満水(まんすい)のタイ(タイランド) 水を治める力
2003年04月03日
編集部
「戌(いぬ)の満水」と呼ばれる歴史的事件がある。徳川吉宗による享保の改革のただ中、寛保2年(1742)の出来事である。この年の7月末から8月初めにかけて、超大型台風が関八州、越後、信濃、甲斐を直撃し、江戸...
-
