水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
第9回 発見!水の文化
江戸の水辺街歩き(佃・築地編)
2018年12月27日
2017年よりスタートさせた「発見!水の文化」も第9回を数え、「江戸の水辺街歩き」企画に新ルートが登場。今回は、佃を出発して隅田川を渡り、築地エリアを巡りました。「江戸」の街を発展させる物流拠点となった佃島の役割や...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 ご挨拶 ミツカン水の文化センター設立20周年 60号発行にあたり
2018年12月04日
中埜 和英
ミツカン水の文化センター 代表1999年に開始したミツカン水の文化センターの活動も本年で20年目を迎えました。当センターが今日まで活動を続けることができましたのも、ひとえに皆様からのご支援、ご指導あってのことと、深く感謝いたしております...
-
-
-
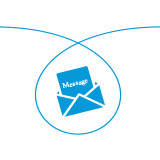
-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 20周年を迎えて―― アドバイザーからのメッセージ
2018年12月04日
沖 大幹 Taikan Oki
東京大学国際高等研究所 サステイナビリティ学連携研究機構 教授「水の文化」が産声を上げた1999年、私たちは2000年問題やノストラダムスの大予言に怯(おび)えつつも「夢の21世紀」の到来を期待していた。携帯電話の普及率がようやく7割程度になったばかりで当然スマート...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 人々をつなぐ川と水
2018年12月04日
川田 順造 Junzo Kawada
人類学者 文化人類学者ミツカン水の文化センター主催のフォーラムやイベントに参加していただいたことがある人類学者・文化人類学者の川田順造さん。アフリカの無文字社会の歴史・文化の研究で知られる川田さんは海外での生活が長かったが、自...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 「カバタ」の暮らしを守る住民たち ―― 琵琶湖畔の湧水文化
2018年12月04日
滋賀県の琵琶湖西岸に連なる比良山(ひらさん)系に降った雪や雨が伏流水となって湧き出ている地域がある。針江集落だ。住民は自噴する清らかな水を、飲料や炊事などに用いている。思わず見惚れてしまうような美しい湧水...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 地域おこしを支える「水への信仰」の記憶
2018年12月04日
岐阜県郡上市白鳥町(しろとりちょう)の石徹白(いとしろ)集落は、全国的に脚光を浴びている地域だ。それは集落のすべての世帯が参加した小規模な水力発電の取り組みによる。このエネルギーの地産地消の試みによって...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 雨水生活は成り立つのか? ―― 離島における小規模集落給水システム
2018年12月04日
笠井 利浩 Toshihiro Kasai
福井工業大学 環境情報学部 教授長崎県五島列島福江島の二次離島「赤島(あかしま)」は、日本国内で数少ない水道施設のない島だ。今も生活用水をすべて雨水に依存している。雨水タンクの研究・開発や雨水利用調査などを行なってきた福井工業大学の笠井...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 島ぐるみで守り、育てる水源林 ――北海道・天売島の挑戦
2018年12月04日
江戸時代から明治時代にかけて森林がほぼ消滅した天売島(てうりとう)。観光客が押し寄せた昭和40年代後半には断水が繰り返され、島外から給水を受けるという深刻な水不足に陥った。その後、苛烈な気候を克服して育て...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 目に見えない「水インフラ」を 可視化する
2018年12月04日
私たちの暮らしや経済を陰で支える「下水道」。共有の財産である下水道を未来へ引き継ぐため、国民一人ひとりに理解を深めてもらいたい、と発足したのが「下水道広報プラットホーム」だ。年に一度の「マンホールサミット...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』60号 水の守人 伝統保存か近代化か ―― 選択を迫られる「柴井堰」
2018年12月04日
鹿児島県大隅半島の鹿屋(かのや)市には、農業用水をとるために山野に生えている雑木を用いた「柴井堰(しばいぜき)」が残る。その土地で入手できる草木を使った堰は各地にあったが、今はここが日本唯一といわれている...
-
