水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-
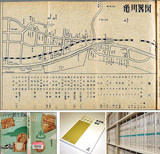
-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 住宅地図から電子地図まで
2011年08月03日
山下 弘記 やました ひろき
株式会社ゼンリン 執行役員 GIS事業本部長住宅地図から始まったゼンリンの歴史。足で稼ぎ、手間を惜しまず更新し続ける仕事ぶりが、データの信頼性を育んできました。いくらデジタル化が進んでも、根本にあるのは人がかかわる〈アナログ〉作業ということを教えら...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 江戸川区の水神様
2011年08月03日
沖中 千津留 おきなか ちづる
法政大学大学院博士課程後期近代的な土木技術や都市政策によって、市街地に新しい景観が生み出されていくにつれその土地の由来は、わかりにくくなっていきます。荒川放水路によって、都市化の波が緩やかであったお蔭で水神宮をはじめとする、豊かな...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 測量の歴史とその現場
2011年08月03日
政春 尋志 まさはる ひろし
国土交通省 国土地理院 基本図情報部長近代国家を成立させるために不可欠だった、測量に基づく国土の地図。国土地理院の地図は、さまざまな場面でオリジナルな原図として活用されてきました。アナログ・紙の時代から、デジタル・データの時代へ変わろうとも、...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 太田川の広島〈概説〉
2011年08月03日
編集部
都市に水の都が多いのは、河口部に開けたデルタが利用されるからでしょう。その中でも、群を抜いたデルタ都市が広島です。毛利輝元によって開発された近世都市は、水の恵みを受け入れ、災害と闘いながら、1989年(平...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 地図で表わす世界観
2011年08月03日
長谷川 孝治 はせがわ こうじ
神戸大学文学部教授ルネッサンス以降の近代化した地図に、目が慣らされている私たち。「世界観を育み、自分の居場所を伝えたいという思いを描いたものが地図」と長谷川孝治さんは言います。居場所とは、何丁目何番地だけではなく、コスモス...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 ヒロシマ復興の軌跡
2011年08月03日
石丸 紀興 いしまる のりおき
元・広島国際大学教授世界で最初に原子爆弾の投下を受け、軍都から平和都市へと変貌を遂げた広島。その背後には、都市計画の上からも大変な苦労がありました。戦争が終わって、66年。石丸紀興さんは、多くの犠牲の上に成立したこの平和の意...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 地図は河川研究の原点なり
2011年08月03日
古賀 邦雄 こが くにお
水・河川・湖沼関係文献研究会1828年(文政11)9月、シーボルト事件が起きた。オランダ商館付きの医師シーボルトが、伊能忠敬作成の「大日本沿海輿地全図」縮図を帰国の際に持ち出そうとして発覚。縮図の写しを贈った幕府天文方・書物奉行の高...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 四季 太田川
2011年08月03日
熊本 隆繁
太田川河川事務所では、緊急割り込み放送設備を利用して、テスト放送を行なっていました。広島のデルタを育み、洪水もあったけれど、多くの恵みも与えてくれた太田川には、たくさんのストーリーがあり、ファンがいます。...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 地図が拡げる未来の可能性
2011年08月03日
編集部
2011年(平成23)1月9日から2月20日まで、茨城県つくば市の国土交通省国土地理院「地図と測量の科学館」で第14回全国児童生徒地図優秀作品展が開催された。地図離れ、社会科離れが心配される中、オリジナリ...
-
-
-

-
つくり、調理し、蓄えて、食べる 〜米づくり 仲間づくり〜
2011年07月19日
佐藤 洋子 さとう ひろこ
食育スーパーアドバイザー、ホームヘルパー家庭菜園が流行っているとはいえ、米づくりとなるとハードルが高くなります。それでも「お米があると心強い」と佐藤洋子さん。その安心感は、「麦では得られないもの」だとも。日本人にとって、そんな大事な作物との〈心理的〉、〈...
-
