水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 ハレの日に食卓を彩る「ワニ」料理
2022年02月21日
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。広島県の北部で、秋祭りや正月に欠かせなかった「ワニ」料理を紹介します。
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 「公」の井戸の未来と「共」の空間の充実化
2022年02月21日
野田 岳仁 のだ たけひと
法政大学 現代福祉学部 准教授地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、その解決策を地域に提案する研究活動「みず・ひと・まちの未来モデル」。初年度は長野県松本市の公共井戸を研究対象としました。
-
-
-
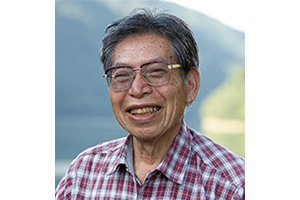
-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 文献にみる筑後川
2022年02月21日
古賀 邦雄 こが くにお
古賀河川図書館長 水・河川・湖沼関係文献研究会筑後川は、その源を熊本県阿蘇郡の瀬の本高原に発し、山岳地帯を流下し、大分県日田市において、九重連山から流れる玖珠川を合わせ山間盆地に入り、夜明峡谷を下り、福岡県うきは市、朝倉市を過ぎ、隈上川、巨瀬川...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 龍と亀
2022年02月21日
島谷 幸宏 しまたに ゆきひろ
もうかなり前になりますが、老荘思想などがご専門の蜂屋邦夫先生と龍と亀を題材に河川技術の思想について対談したことがあります。近年の気候変動による洪水の頻発を見ていると、龍と亀の思想、特に亀の思想が重要になりつつあるのを感じます。
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 「水の国」熊本に学ぶ 変わるもの、変わらないもの
2022年02月21日
今回の特集は、第4回アジア・太平洋水サミットの開催地となった熊本市に着目するところからスタートした。水サミットは当初2020年10月に実施される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大で延期。
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 牧畜文化を伝える沢水の集落
2022年02月21日
熊本市内から東へ向かい、外輪山の割れ目から阿蘇カルデラに入り、さらに阿蘇五岳の北側を回って奥へ。北外輪山の南側斜面にある、湧水で知られる「手野集落」を訪ね、水にまつわる暮らしを見た。
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 つくり直された配水システム
2022年02月21日
阿蘇カルデラ南側の火口原(平坦地)は「南郷谷(なんごうだに)」と呼ばれる。そこに位置する熊本県の高森町は宮崎県の高千穂町と鉄道で結ばれるはずだった。トンネル建設工事による出水事故で周辺の湧水が枯れてしまったが、その後に配水システムをつくり直した高森町を訪ねた。
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 阿蘇の湧水と人びとの暮らし
2022年02月21日
牧野 厚史 まきの あつし
熊本大学大学院人文社会科学研究部 教授阿蘇五岳を中心とする阿蘇カルデラは天然水が湧き出す水源の宝庫だ。そこには、熊本地域とはまた異なる水への接し方、暮らし方がある。そこで、琵琶湖から熊本へと研究フィールドを移した熊本大学大学院教授の牧野厚史さんに..
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 ふるさとを誇りに思う子どもたち
2022年02月21日
熊本県には、次世代育成において九州のなかでも有名な市民団体がある。八代市(やつしろし)を拠点に活動する「次世代のためにがんばろ会」だ。ほぼ毎月のようにイベントを行なっている。
-
-
-

-
機関誌『水の文化』70号 みんなでつなぐ水 火の国 水の国 熊本 高校生たちの動画チャレンジ
2022年02月21日
今、九州の高校生世代が自分たちの身近な水文化を調べ、その結果を動画として世界へ発信しようとしている。これはNPO法人日本水フォーラムが事務局となって進めている「ユース水フォーラム・九州」の活動の一環だ。
-
