水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 水と持続可能な開発 スペイン南部アルメリア地方の海水淡水化施設とその灌漑利用
2008年12月26日
編集部
沖大幹さんと編集部では、スペイン・サラゴサの万博に引き続き、南部アルメリア地方の海水淡水化施設とその灌漑利用の現状、及び下水処理施設を視察しました。適地適作を徹底させるEUの農業政策も含め、変わりつつある...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 地方都市と水の共生 人が核になって再生するチッタスロー
2008年12月26日
陣内 秀信 じんない ひでのぶ
建築史家 法政大学デザイン工学部建築学科教授まちは、時代とともに生きています。ヨーロッパでは、今、荒廃していた旧市街地が再生して活気を取り戻しています。その核を担っているのは、水辺空間と人。イタリアでの成功例は、日本の地域おこしのヒントになってくれ...
-
-
-
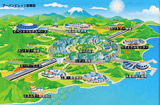
-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 必要なのは「どんな社会をつくりたいか」 ITで実現される理想社会
2008年12月26日
藤本 淳 ふじもと じゅん
東京大学先端科学技術研究センター特任教授Eメールやホームページ、インターネットを利用した通信販売などなど、今、私たちの暮らしはITなしでは想像もつきません。しかし、暮らしや社会への影響力が大きいITを、どこにどう使うか、ということが、問われる時...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 ニュースで共生はどう扱われてきたのか 今、必要な報道とは
2008年12月26日
池上 彰 いけがみ あきら
ジャーナリスト週刊こどもニュースで活躍した池上彰さんに、「共生」を説明してもらいました。池上さん流の分析で、大人も納得の答えが出ます。伝えたいという熱意と伝えたいことがあれば、スキルを磨くことで、継承できる事柄はぐっと...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 死を自覚することで、生は輝く 共生とは何か
2008年12月26日
山折 哲雄 やまおり てつお
暮らしが近代化する中で、私たちが遠ざけてしまった「死」。それを再び自覚し、無常の中にある「生」の喜びを知ることが、精神の荒廃や環境問題を解決する糸口になるのではないか。共生という抽象に陥りやすい概念を、山...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 進化する工場の水処理思想 水屋が提案する省水型産業の共生
2008年12月26日
今岡 孝之 いまおか たかし
オルガノ株式会社 プラント事業本部 プラント事業部企画管理部長 工学博士オルガノはイオン交換の原理を用いて、非常にきれいな水をつくる技術を産業界に広く提供してきました。廃棄物処理や地球温暖化をストップするための省エネが求められる現代、水屋を自認するオルガノに望まれる仕事も、様...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』30号 共生の希望 技術にも自治がある 自然と折り合いをつけて共生していく技術
2008年12月26日
大熊 孝 おおくま たかし
大熊河川研究室 NPO新潟水辺の会大熊孝さんは、新潟で自然や川と共生する人たちと親しく交わってきました。「阿賀に生きる」という自主制作映画には、彼らの姿が記録されています。自然や川と共生することで、心も体も鍛えられると実感を深め、川の再生...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 川上から川下まで、すべての人に正当な利益をマグロのフードシステム
2008年08月18日
小野 征一郎 おの せいいちろう
近畿大学農学部水産学科教授ハレの日のご馳走である寿司や刺身。マグロはその代表選手です。回転寿司やスーパーマーケットで驚くほど安いマグロが食べられるようになった今、川上の生産者にまでその恩恵は届いていない、と小野征一郎さんは言います...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 漁師が育んだ氷見の歴史 資源管理につながった台網漁
2008年08月18日
小境 卓治 こさかい たくじ
富山県氷見市立博物館館長寒ブリ人気で近年にわかに脚光を浴びている富山県氷見市。ここで中世末期から行なわれてきた定置網漁は、水産資源を捕り尽くすことのないサスティナブルな漁法としても注目されている。氷見市立博物館長・小境卓治さんに...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 おさかなで生きる
2008年08月18日
さかなクン
フィッシュギ(不思議)ですね〜。子供のころからお魚を大好きでい続けたら、魚屋さんや漁師さん、研究者の先生、水中カメラマンさんなど、大の憧れの、お魚に情熱をかけておられる素晴らしいみなさまと知り合うことがで...
-
