水の文化を知る
水と自然の記事一覧
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 水路を公園にする夢を描いて 都市に水と緑の回廊をつくる
2006年12月22日
石川 幹子 いしかわ みきこ
慶應義塾大学環境情報学部教授20世紀は、都市が急速に拡大した時代でした。そのために自然が破壊され、多くの緑地が失われていきました。私は失われたものをただ惜しむのではなく、緑地を確保するための知恵を理念や計画、政策、財源、人のネットワ...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 《親水と公園》
2006年12月22日
古賀 邦雄 こが くにお
水・河川・湖沼関係文献研究会街なかの公園に住みつくホームレスが社会問題化して久しい。アル中が高じ、自らホームレスの体験を赤裸々に描いた吾妻ひでおの『失踪日記』(イースト・プレス2005)が第10回手塚治虫文化マンガ大賞などに輝いた。...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 鎮守の森は都市公園の原形の一つ 小自然から中自然へ
2006年12月22日
上田 篤 うえだ あつし
京都精華大学名誉教授公園の発祥をどこに求めるか。いろいろな説があるでしょうが、私がおもしろいと思うのは、チェコスロヴァキアにある伝説です。昔々、イージークという若者が悪魔に出会い、「20年間、美しい姫との愛に生きられるなら悪...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 ランドスケープにおける音風景の復権 五感で味わう公園
2006年12月22日
鳥越 けい子 とりごえ けいこ
聖心女子大学教授・サウンドスケープ研究家サウンドスケープとは「音の風景」のことですが、「音」だけではなく、「静寂」やその場の「気配」も問題にします。最終的には耳だけではなく、五感で風景を感じ、味わうことが大切だとする考え方です。景色というと、私...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 都市公園の常識を変革するワークショップ <岐阜県各務原市(かかみがはら)> パークレンジャー
2006年12月22日
編集部
岐阜県各務原市では、2001年(平成13)に緑の基本計画を定めました。緑の基本計画とは、それまで国が主導してきた緑化政策を、新たに地域自治体が主体となって進めるためのマスタープランで、都市公園整備も含まれ...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 一人ひとりの物語が潤いを育む 利用者がつくる都市公園
2006年12月22日
白幡 洋三郎 しらはた ようざぶろう
日本文化研究センター教授公園には、公園自身の物語ができなくてはいけない。ところが明治以降新設された都市公園には、物語がないんです。歴史もない。自然の美しさは、わざわざ人間が作為的になにかしなくても、在るだけで美しいでしょう。グラ...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 造園業はコミュニティの結節点 公園は育てるもの
2006年12月22日
伊藤 幸男 いとう ゆきお
株式会社日比谷アメニス当社の源流は、1872年(明治5)に葛飾区堀切で植木業を始めたころに遡ります。そのころは、個人邸の庭を対象に造園業を営み始めたようです。現代では、造園業と植木屋さんは同じに見えるかもしれませんが、造園業と...
-
-
-

-
機関誌『水の文化』24号 都市公園 全国の晩ご飯を見た
2006年12月22日
ヨネスケ(桂 米助) かつら よねすけ
今は「突撃リアル!隣の晩ごはん」という形で3週間に1回くらいやっていますけど、これまで20年、3千軒以上のご家庭の晩ごはんを見てきました。日本で行っていないのは、小笠原諸島くらいですね。やらせなし、打合せ...
-
-
-
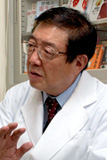
-
「寄生と共生」の理解が人間を救う 〜サナダムシ・キヨミちゃんからのメッセージ〜
2006年12月14日
藤田 紘一郎 ふじた こういちろう
人間総合科学大学教授
東京医科歯科大学名誉教授「カイチュウ博士」として知られる藤田紘一郎さんは、世界中の水を巡り、微生物学の第一人者でもあります。今回お話しをうかがった「寄生虫と免疫」というテーマは、生物が共生することの意味をあらためて問い直してくれる内容でした。
-
-
-

-
地域の資源を磨くことで「もてなし力」がつく 〜ほんものの地域活性化を考えよう〜
2006年12月11日
堀 繁 ほり しげる
東京大学アジア生物資源環境研究センター教授「空間の日本らしさとは何か」を研究テーマにしている堀繁さん。水の郷百選の委員でもありますが、いまは地域づくり支援のために全国を飛び回っているといいます。その堀さんに「もてなしによる地域振興」についてお話しをうかがい...
-
